看護師としての仕事にも役立つうえ、自分のためにも知っておきたい精神医学の話を紹介!今回は、「病名に気持ちがとらわれてしまう」という質問に答えます。
*
こんにちは、精神科医・産業医の西井重超です。
この連載では、普段、忙しく働くナースに役立つ精神医学の内容をお届けします。医療従事者ではなくても、現代社会で生きるうえで、メンタルヘルスの知識は誰もに必要な内容だといえます。
初回は、よく聞かれる質問の1つにお答えできたらと思います。“精神科の病名を気にしてしまいすぎて、気持ちがとらわれてしまう”という内容です。
特に、知り合いや近しい人が病気になった場合、病名ばかりを気にしてしまうのですが、どう考えればいいかという話でした。
病名は、患者さんの「道しるべ」となるもの
日々診察しているなかで、病名を伝えると、患者さんからいろんな反応が返ってきます。「今の状態がはっきりしたので安心」というコメントが多いですが、一方で、「自分が不調なのはうすうす気がついていたが、認めたくはなかった」という方もおられます。
精神科の病名は非常にあいまいです。診断基準自体はありますし、重症度をはかる心理検査などのスケールも開発されてはいるものの、病名を白黒つけられるものではなく、グレーゾーンといった考え方が存在します。
なお、病名を白黒つけられるのは感染症が代表的ですね。いずれにしろ、病名は道しるべです。患者さんを傷つけるものではありません。
発達には濃淡があることを理解しよう
まず発達障害に関しては、「スペクトラム」という考えが大切です。発達には濃淡があって、ある一定の問題の濃さ以上の人が、発達障害の基準を満たすと考えてください。
軽症やグレーゾーンの人は重症の人よりも多く、発達障害の診断をギリギリ満たさなくても、発達障害の特徴を色濃くもっている人はさらに多いです。
また、精神疾患の診断基準には、「社会的」「職業的」という言葉が多用されています。疾患によっては「文化的」という言葉もでてきます。途上国ではADHD(注意欠如多動症)が少ないという報告があり、生きにくい社会が発達障害の境界ラインを引き上げている可能性があるという意見もあります。
と、考えると極端な話ですが、発達障害のグレーゾーンと診断された人は、違う国では診断を満たさない可能性だって出てくるのです。
ですから、病名がついたかどうかは、何かを申請したりするなど書面上は必要になるかもしれませんが、病名がつかないから治療の対象にならないというわけでもなく、共通のアプローチをして未来をよくしていけばよいのです。
逆に病名がついていても、症状が落ち着いたら病名など気にせず生きていけばよいのです。
基準を満たすかどうかではなく、その人に合った生活のヒントを
発達障害は、自分の得意なことで活躍していく人もいます。二次障害や生きにくさが出なければ問題ありませんので、置かれている状況や環境との相性で大きく困りごとが変わるとも言えます。
この言い方は、「しんどいのはすべて環境の責任だ、まわりが悪い」という誤解を生む可能性があるので、そうではないとお伝えしておきます。
病名の有無にかかわらず、環境に慣れていくようにしつつ(本人因子への対応)、より相性がよい環境を探すこと(環境因子への対応)をしていきましょう。
発達障害は得手不得手があり、ASD(自閉スペクトラム症)は危険が伴わない技術系・専門知識系に相性がよいことが多く、ADHDは日々単調にならないクリエイティブな業務に相性のよいことが多いです。とはいえ、本人の興味具合で相性がまったく合わない場合もあるため、断定できない部分が大きいです。
ですから、発達障害の基準を満たすか満たさないか自体はさほど重要ではないため、私は日常で発達障害の人向けの生活のヒントを、発達障害でない人にも伝えています。 発達障害の人向けの生活のヒントは、不器用な人でもできるようになるヒントでもあるからです。
「ウチの子は勉強に集中できないので発達障害ではないだろうか」と心配して受診される方がいます。ADHDなら治療薬がありますが、そうでないと治療薬は使えません。
一方で、発達障害の人に有用なヒントはどのような人にも使えます。発達障害であろうがなかろうが、どんどんヒントを活用して人生を豊かにしていけばよいと思います。
例えば、パーカーのフードを被ると左右の視界が遮られて目の前のことに集中でき、勉強がはかどるADHDの人がいますが、こういうヒントはADHDではない人でも利用できます。
もし、ご自身の子どもが発達障害ではないかと疑っている人がいらっしゃれば、「ウチの子は発達障害とは診断されていないので発達障害の本なんて読みたくない」というのではなく、ぜひ発達障害にかかわる知識を増やして、よいところ・よい方法を取り入れていくことをおすすめします。
また、医師はよく病気をベースに見てしまいがちになりますが、人そのものを見ることに長けている看護師は、特性という枠にとらわれず、その人そのものをみて支援できる方が多いかもしれません。
その人が「ある病名そのもの」ではなく、 「その人の一部にその病気をもっているという部分がある」だけなのです。 発達障害という枠をいったん外して、その人に何が今必要かを考えて支援を進めてみてください。
診断・病名は治療薬の決定のために大切なもの
「うつ病」「躁うつ病」「適応障害」の薬物療法は、診断に基づき適切な治療を行うことが必要です。
一方で、これらの精神療法や心理的アプローチについては、基本的にどの疾患でも共通した対応で問題はありません。代表的なものが共感・傾聴を軸とした支持的精神療法や、認知行動療法などです。
診察当初では「適応障害」と診断していたものが、うつ病の診断基準を満たし、「うつ病」になる場合もあります。「うつ病」と診断していたものが、躁状態が出現して「躁うつ病」になる場合もあります。
精神疾患の薬物療法は根治薬というものが存在せず、内服をしたからといってウイルスが消えるように疾患が消失するわけではありません。
例えば、うつ病は一度よくなってから再発せず一生を過ごされる人もたくさんいますが、再発緩解を繰り返す場合もあります。よくなってからも内服を継続するのは、治療薬を飲みながら再発を抑えるという考え方のためです。
内服の継続が必要な代表的なものは、双極性障害や統合失調症です。 診断・病名は治療薬を決定するのに大切なものになってきます。
看護は「病名」だけで計画されるものではないはず
一方で、思い出してほしいものがあります。「看護計画」は病名だけで計画されるものなのかと。病名に注目するより、むしろ患者さんそのものを見て、その人に合った計画を立てていくものであると私は聞いています。
そう考えると、私は看護師によるケアは、 病名という垣根を超える素晴らしいものだと思っています。
近しい人が不調になったら、慌てるのはとてもわかります。そういうときは病名から少し離れてみて、今できることをやっていってはいかがでしょうか。
.jpg)
.jpg)
「働くナースのための精神医学」の記事一覧
ただいま『エキスパートナース』本誌で連載中!
近年の精神医学では、「発達障害」は「神経発達症」というなど、呼び方が変わってきている疾患もありますが、この連載では、あえてみなさんになじみのあるであろう名前で呼んでいます。
この記事は『エキスパートナース』2022年4月号連載記事を再構成したものです。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。


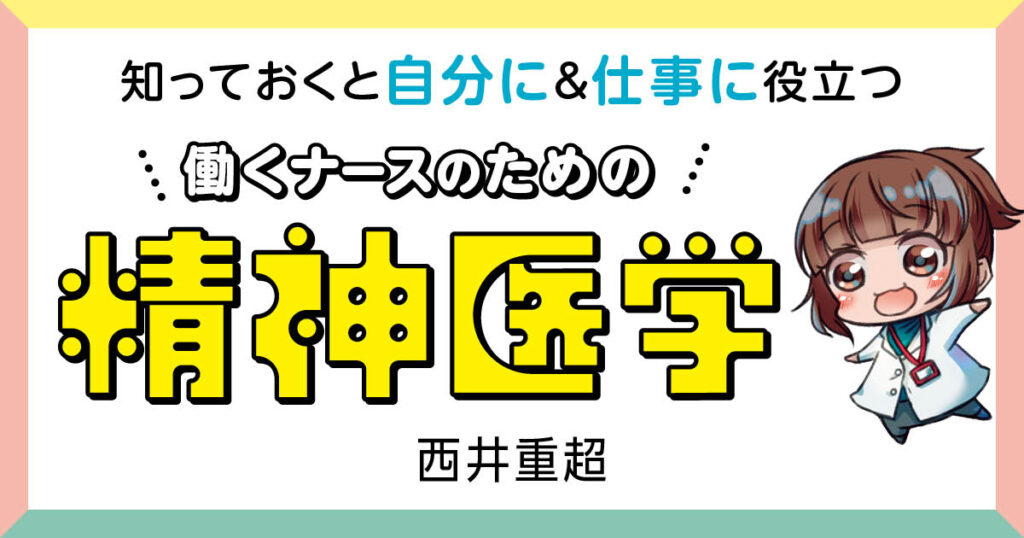
20231123.jpg)



