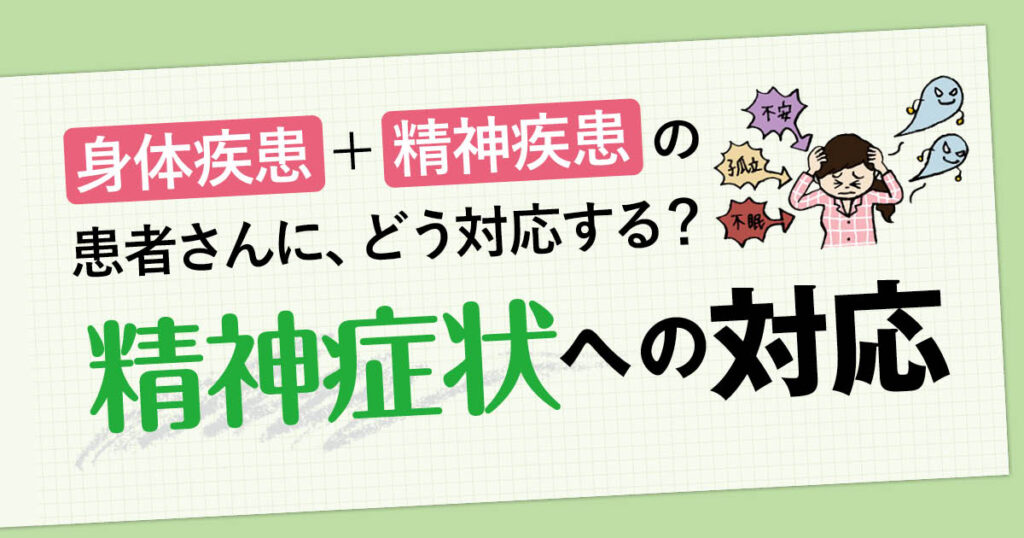精神疾患に処方される主な薬剤の1つが「抗精神病薬」。作用や気をつけたい副作用など、基礎知識を紹介します。
抗精神病薬は脳内のさわがしさを抑えてくれるイメージ
抗精神病薬はドパミンD2受容体をブロックする作用をもちます。イメージとしては、脳内のさわがしさを抑えてくれる感じです。
このブロックが幻覚や妄想を緩和する作用にもなりますが、副作用の一部にもなります。また、共通して血栓リスクを上げ、悪性症候群の原因にもなります。
気をつけたい副作用は錐体外路症状
多い副作用はやはり錐体外路症状で、種類は手の振るえ(振戦)、アカシジア(身体のそわそわ感)、ジスキネジア(口や身体の不随意運動)、ジストニア(不随意な筋緊張による不自然な姿勢)など。
抗精神病薬は「定型」と「非定型」に分けられます。非定型の薬剤にはセロトニン5-HT2A受容体のブロック作用があり、それが副作用の軽減に働いているのではと言われています(ただし、用量に配慮すると、そんなに大きな違いは出ません)。
一般病棟で使われるのは、定型だとせん妄治療のハロペリドール(セレネース®)でしょうか。非定型もわりと多く使われます。表1で主な副作用を薬剤別に示します。
この記事は会員限定記事です。