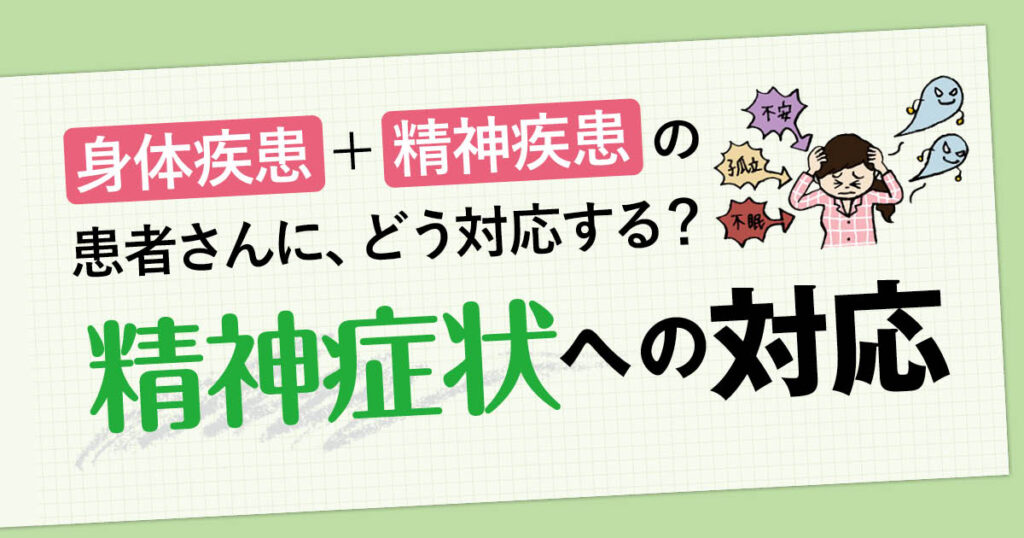一般病棟でもよく出合う精神疾患「身体症状症」について、薬剤治療の進み方、経過観察とアセスメント、対応のポイントをまとめました。器質的な原因がみつからない場合の、患者さんとの会話のコツも紹介します。
身体症状症の基礎知識
身体の症状はあれど、内科的外科的な検索をかけても原因が十分にわからないものを、身体表現性障害と言っていました。医学がさらに進歩したら原因がわかるかもしれませんが、現段階では精神科の範疇。「気のせい」と言われて患者さんが納得いかず、ドクターショッピングをするというのが典型でしょうか。
なお、身体表現性障害は、アメリカ精神医学会の診断基準のDSM-5では名称が“身体症状症”に変わり、身体疾患の有無にこだわらなくなって、身体症状とそれに伴う思考・感情・行動のズレに重きを置くようになりました。
薬剤治療の進み方
痛みに鎮痛薬や鎮痙薬、動悸にβ遮断薬など、対症療法的な薬剤も、使いすぎなければ悪くないかと思います。
ベンゾジアゼピン系は使わないのが理想的で、身体の症状は慢性化しやすく長期投与は好ましくありません。SSRIなどの抗うつ薬も治療に使われるものの、患者さんは副作用にとても敏感で注意が必要です。
経過観察とアセスメントのポイント
患者さんの訴える症状は軽視しないこと。症状に見合う身体的な原因があるかどうかというのは必ず確認しましょう。身体症状症の患者さんでは身体疾患の有無を問わないので、全部を「気のせい」にすると大変な目に遭うことがあります。
後述しますが、診察を行うことも重要です。“手当て”という行為は、まさに手を当てることから始まります。
対応のポイント
患者さんは抱えきれないつらさを、こころが破れないように身体の症状として表出せざるを得ない状況にいます。よって日常生活や人間関係を少しでもゆとりあるものにしていくのが目標ですが、なかなかその苦しさを語らないことも多く、かかわりは難渋します。
こちらも症状以外のみに重心を置きすぎることは避けること。理由はどうであれ患者さんは身体の苦痛があり、そこへの医学的な関心を示すことが重要です。
この記事は会員限定記事です。