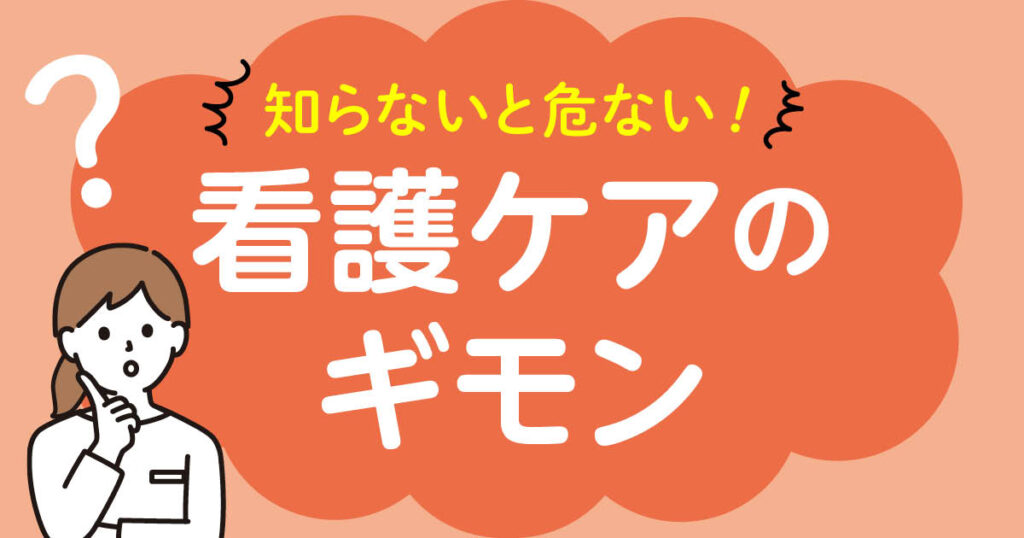ICG(インドシアニンググリーン)試験を行う際の注意点とは?静注と採血のタイミングなど、手技のポイントを紹介します。ICGの血漿中濃度の推移についても解説します。
Q. ICG(インドシアニンググリーン)試験のポイントは?
ひとこと回答
試薬を投与する際、静注の速度は 30 秒以内に“すみやかに”行うことが手技上の注意点です。
ICG(indocyanine green)試験とは、暗緑色の色素(インドシアニングリーン)を静注負荷し、一定時間後に採血してその残存度を測ることにより、肝疾患の診断や肝の予備能を定量的に評価する色素負荷試験です。
色素を静注すると、大半がリポ蛋白と結合して肝細胞に取り込まれ、そのままの形で胆汁中へ排泄されます。この色素は腸肝循環や腎排泄もなく、肝以外では代謝・排泄されない性質をもつために検査に用いられます。
ショック症状に注意しながら30秒以内に徐々に静注
通常、静注は体重1kgあたり0.5mgの負荷量(被験者の体重が約50kgの場合は5mL程度の溶液)で行われます。
このとき、色素は生物学的半減期がきわめて短い(ICGの血漿中濃度は、健常人で3~4分で半減。詳細はコラム参照)ことから、静注をすみやかに行う必要があります。
また、ICGはヨウ素を含むため、ショック症状の有無にも注意しましょう。よって、手技のポイントは「30秒以内に、徐々に静注」です。
採血は何分後に何回実施する?
「消失率」(K値)を測定する場合の採血は、負荷前と注入後5~15 分の間に2回以上(例:5分、10分、15分)実施します(図1-①)。
一方、簡易的に「血中停滞率」(ICG R15)を求める場合には、負荷前と15分時のみ採血を行います(図1-②)。
この記事は会員限定記事です。