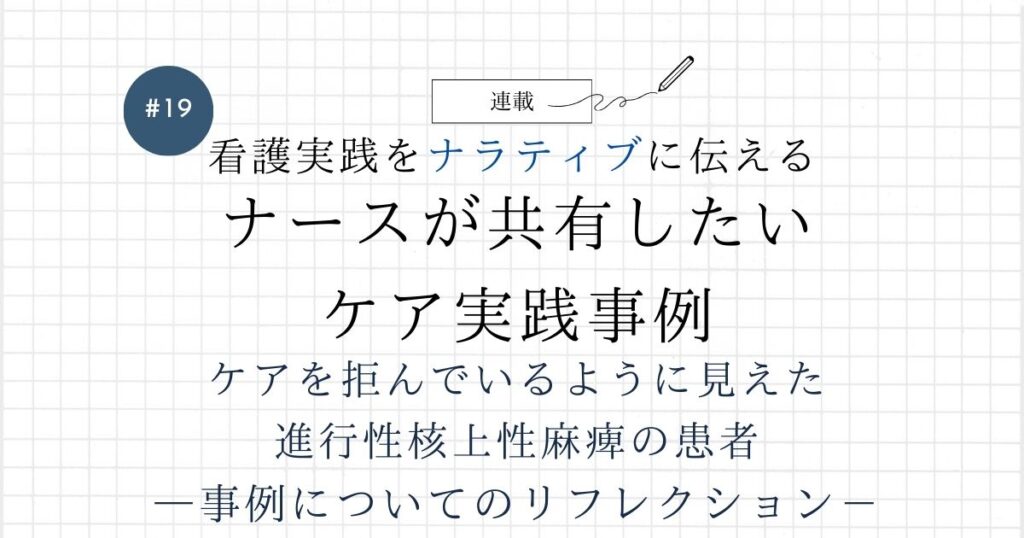事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回はケアを拒んでいるように見えた進行性核上性麻痺の患者さんの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第17回】ケア拒否に見えた進行性核上性麻痺患者の真意と看護介入
事例についてのリフレクション
その人の人生を支えるということ
急性期病院に入院する多くの患者さんにとっては、病院は治療を受けるための“一時的な生活の場”に過ぎず、家庭や職場・学校などで生活する時間のほうが圧倒的に長くなります。
つまり、私たちの知らない患者さんの生きている姿が、病院の外にはあるのです。しかし病棟で働いていると、入院中の患者さんの姿が、その人そのものであるように錯覚しやすくなります。
このケースでも、病棟看護師はAさんのことを「慢性疾患を抱えながら人生を歩んでいる人」ではなく、「転倒リスクが高いのに、それを理解できない危ない人」ととらえていました。通常、進行性核上性麻痺は転倒リスクが非常に高いため、病棟看護師がそう思うのも無理のないことだったのでしょう。
今回、宗像さんがAさんと病棟看護師の間に入ることで、徐々にAさんのこれまでの生き方や価値観、病気への思い、ふだんの暮らしぶりなどを、皆で共有できるようになりました。
そのことで、病棟看護師は“Aさんが自分らしく生きる中での困難さ”に着目するようになり、看護師の立場から必要と判断したケアを押しつけるのではなく、Aさんやその妻と「ともに考える」ケアの提供へと変わっていきました。
ここにきて、病棟看護師と宗像さんは、Aさんの人生のサポーターの1人になることができたのだと思います。
人生の終末に向けて
この記事は会員限定記事です。