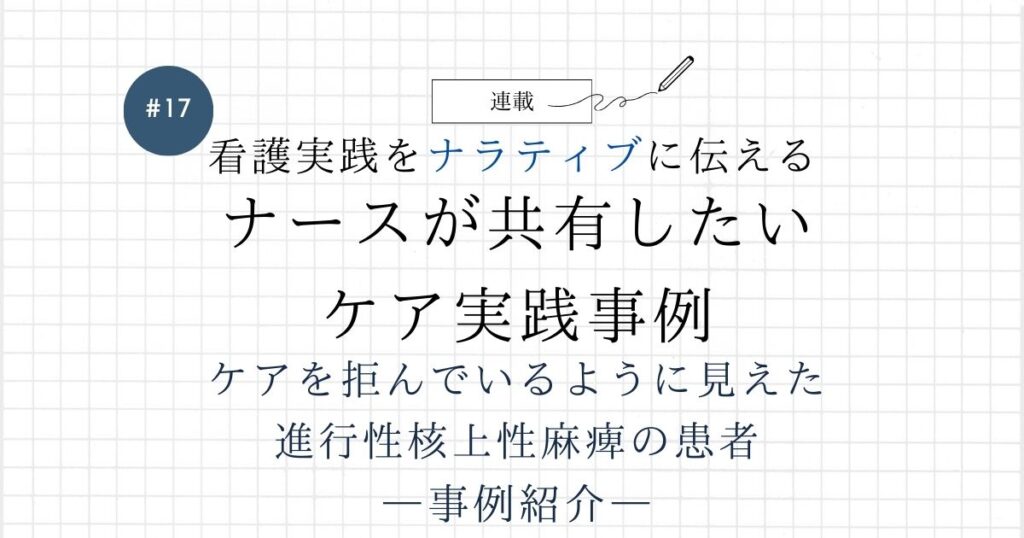事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回はケアを拒んでいるように見えた進行性核上性麻痺(PSP)の患者さんの事例を紹介します。患者さんの真意とは?
〈目次〉
ケアを拒んでいるように見えた進行性核上性麻痺の患者さんの“思い”
Aさんのご自宅での様子と、伝わってきた葛藤
生活環境の整備・摂食嚥下ケアを「ともに考える」
Aさんに現れた変化と、今後への視点
ケアを拒んでいるように見えた進行性核上性麻痺の患者さんの“思い”
Aさん、80代の男性。数年前より進行性核上性麻痺(進行性の難病。歩行障害、パーキンソニズム、認知症などを特徴とし、進行するにつれて構音障害や嚥下障害、認知症が出現し、徐々に歩行・立位不能となる)を発症しています。
Aさんは妻との2人暮らしで、要介護3(食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんど自分1人ではできない)です。パーキンソニズムにより“小刻み歩行”“すくみ足”が著明にありましたが、自宅では室内自立し、通所リハビリテーション施設などを活用し、自宅療養していました。
今回、誤嚥性肺炎のために入院し、病棟では肺炎治療と嚥下訓練を行っていました。
入院後、病棟看護師は、発熱もあり立位も不安定であったことから、転倒・転落などのリスクを考慮した安全へのケアのため差し込み式ベッド柵を使用し、Aさんに“移乗時は看護師を呼んでほしいこと”を説明しました。
しかし、Aさんが夜間に1人で車椅子に移乗していたため、再度、転倒の危険性などを話すと、「俺は俺のやりたいようにやらせてくれ」と介助を拒み、声を荒げました。
また、摂食指導では、「監視されている」などと話す場面が続き、病棟看護師より“対応に苦慮している”と相談がありました。この相談が、Aさんとの出会いでした。
Aさんのご自宅での様子と、伝わってきた葛藤
私はAさんに会いに訪室しました。そして、Aさんについてよいケアを考えていきたいことをお伝えし、入院中の困りごとはないかをうかがうと、「俺は危険人物だ」と言い、表情をこわばらせていました。
医療者に対して不信感を抱いている様子が感じられ、このままでは治療・ケアを受けられる環境ではなく、Aさんと医療者の関係に溝が深まってしまう恐れが考えられました。
私は、Aさんが自分を「危険人物」と感じていることを受け止め、なぜそのように思われるのかをうかがっていくと、「ベッド柵で囲われて自分が危険人物として扱われている不信感」「家では自立している動作に対しても介助を受けることへの抵抗感」「摂食指導や介助の場面で、“○○してはいけない”と自分より歳の若い看護師に指示を受ける状況に屈辱的な感情を抱いている」ことを語られました。
思いを聴かせていただいたことに感謝の気持ちと、このような思いを抱かせてしまっていたことに謝罪しつつ、Aさんと一緒にケアについて考えていきたいことをお伝えしました。
また、自宅での生活状況をうかがうと、6年間、徐々に身体機能が低下していく進行性核上性麻痺と向き合いながらも前向きに生きてきた自負があり、Aさんは「何ごとも前向きに」と語りました。自宅では、できる限り妻の手を借りなくても生活できるよう、手すりや衝立(ついたて)などさまざまな工夫をして生活してこられたそうです。
Aさんは大手の企業に勤め、工場長まで勤め上げたのち、ご自宅で自叙伝の作成、書道など趣味に力を入れてきたそうで、ご自宅の自室はご自身の作品でいっぱいになっているとのことでした。
「自叙伝を完成させたい」と笑顔で語られるAさんの姿は、とても生き生きとされていました。しかし最近は、パーキンソニズムの増強、構音障害、嚥下障害が目立ち始め、今後についての不安や、さらに介助を要し依存することへの葛藤を抱いていることが語られました。
妻は、「とてもがんこな人。自分のことは自分で決める。病気になってもそれは変わらない。大変だけど、できる限り支えたい」と、Aさんとともに歩んでこられた様子でした。
生活環境の整備・摂食嚥下ケアを「ともに考える」
Aさんについて病棟看護師に伝え、Aさんの「病気への向き合い方」「自宅での生活の工夫」について共有しました。
そこでは、病棟看護師は転倒を回避させたい思いから、Aさんに対して“説明してもわからない、病識がない、危険の認識が低い人”と決めつけた見方をしてしまうことで、Aさんの行動の真意をつかめず、どうしたらいいだろうと苦悩していることがわかりました。
また摂食指導では、指導マニュアルを中心とした指導となり、これまでの食事形態や工夫点などを取り入れていませんでした。病棟看護師は転倒や誤嚥などのリスクにとらわれ、患者との関係性を築くうえでの困難さを感じ、どうかかわっていったらよいか見失っていました。
そこで、家での生活環境の確認を行い、理学療法士と連携してAさんが“ 1人でできるADL”を、病棟看護師とともに確認しました。これにより、自室内自立とすることができました。
また、自宅と同じような環境で、かつAさんが安全に行動できるよう、ベッド柵は常に乗り降りできるようL字バーを設置し、尿器の保管位置や車椅子の位置などAさんと相談しながら行動範囲に合わせて設置して、生活環境を整えました。 摂食指導においては、妻のやり方を見守るとともに、これまでの不安な点を確認して改善策や注意点を考え、自宅でよく作るメニューに合わせた嚥下食の作り方を考えていきました。
Aさんに現れた変化と、今後への視点
出会った当初、Aさんは「入院しなければよかった」と後悔の念を抱き、訪室のたびに不満ばかり言葉にしていました。
しかし、1人でも安全に行動できる範囲を確保することができるようになると、自室や廊下で、穏やかな表情で車椅子で自走している姿を見かけるようになりました。
訪室すると、Aさんからは摂食角度の工夫や嚥下食についての質問がありました。
また、話をするなかで、今後の胃瘻造設についての質問なども聞かれるようになりました。進行性核上性麻痺の進行を自覚し、以前より胃瘻造設についての説明を医師より受けていたことから、「そんなときが近づいてきているとも思っている。先生に勧められれば作るべきなのか悩んでいる」と、経口摂取ができなくなった場合について、本人なりに考えていることを教えていただきました。
Aさんの肺炎は改善し、ADL、摂食条件も入院前とほとんど変わりない状況まで回復され、自宅退院となりました。 退院後2年の経過のなかでは、構音障害、嚥下障害の進行が認められており、発語が聞き取りにくくコミュニケーションが難しくなりつつありますが、思いを汲み取りながら、Aさんの価値観を尊重した支援を継続して行っています。
※この記事は『エキスパートナース』2016年6月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。