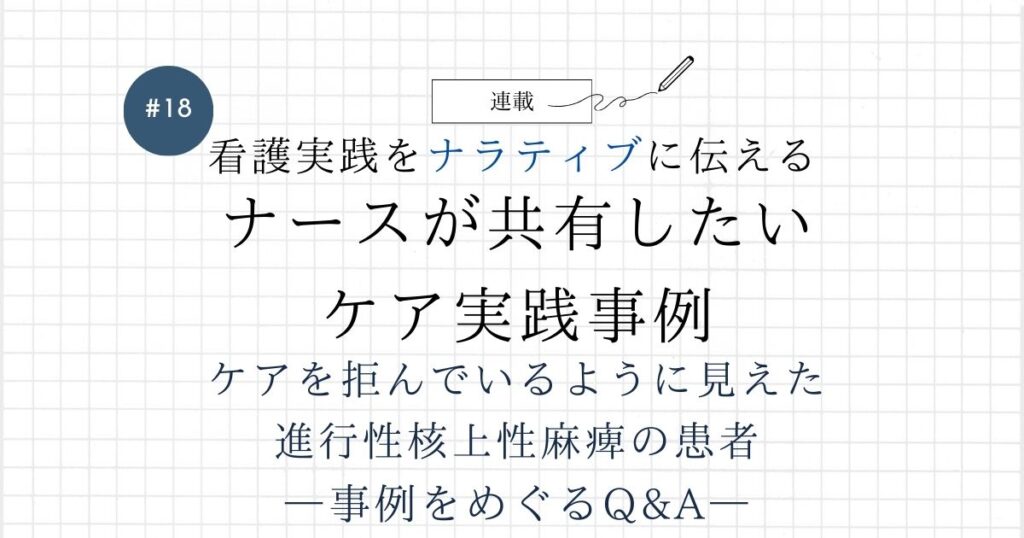事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回はケアを拒んでいるように見えた進行性核上性麻痺(PSP)の患者さんの事例をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第17回】ケア拒否に見えた進行性核上性麻痺患者の真意と看護介入
〈目次〉
この事例を紹介した理由は?
Aさんへの理解やかかわり方はどう変化した?
多職種連携にあたり留意した点は?
これからのAさんの気持ちの変化をどうサポートする?
事例をめぐるQ&A
この事例を紹介した理由は?
松本 宗像さんがこの事例を選んだ理由を教えてください。
宗像 看護師の提供しているケアが患者さんにとって苦痛となっていて、そのことに気づいていないスタッフにどのようにかかわっていけばよいか、私自身とても悩んだ事例でした。
悩みながらもAさんにかかわるなかで、Aさんの考えや価値観に触れ、Aさんの病気に向かう姿勢を知ることで、実践しているケアが“医療者のみの視点”であることに気づき、スタッフの視点の転換を図ることで、Aさんへの理解を深め、Aさんにとって最善なケアを考えた事例でした。
特に高齢者では急性疾患のみならず二次的合併症の併発などのリスクが高く、急性期病院においては安全面への配慮や対策を重視される傾向にあります。 高齢者の意思や意向を尊重し、病を抱えながら生活する高齢者をどのように支えていくのかを考え続けたいと思いました。
Aさんへの理解やかかわり方はどう変化した?
松本 慢性疾患を抱える人は、自分なりの病気や生活への対処方法を生み出すと言われていますが、医療者側がそれを理解しないために、患者さんとの関係がうまくいかないケースが少なくありません。Aさんと病棟看護師も、最初のうちはこのような状況になっていたように思います。
Aさんと妻の疾病や生活への向き合い方を知ることで、宗像さん自身とスタッフのAさんへの理解やかかわり方は、どのように変化しましたか?
宗像 私自身は、Aさんの考えや価値観を知れば知るほど、Aさんのことをもっと教えていただきたいと思うようになりました。そしてAさんについて、スタッフにも知ってもらいたいと思いました。
Aさんを知ることで、同じケアでも1つひとつのケアの方法や意味が違ってくると感じたからです。何度かお会いするうちにAさんのこわばっていた表情も徐々にほぐれ、笑顔がみられるようになりました。
スタッフとともにAさんの立位が安全にできるよう環境調整し、「こうすれば立ちやすいのですね」とAさんの動きを確認することができると、これまでは、まず“危ないと制止していたかかわり”であったのが、排泄時には“できるところまでAさんの行動を見守るかかわり”に変化していきました。
また、「転倒」という事象を避けたい思いを残しつつも、スタッフはかかわりから、Aさんのできた行動、夜間の様子について私に報告してくれるようになりました。
スタッフからは「はじめて笑顔を見ました」「Aさんと話ができました」と聞かれました。Aさんのもつ力を知ることで、この力を活かしたケアを考える方向に、視点が転換されたのだと感じています。
この記事は会員限定記事です。