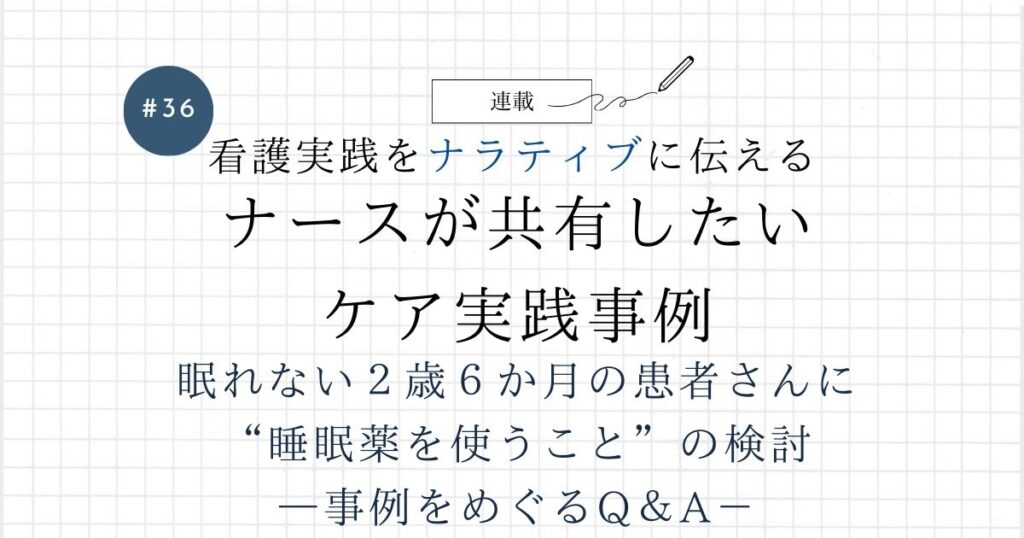事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は化学療法中の、眠れない2歳6か月の患者さんに“睡眠薬を使うこと”の検討をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第35回】化学療法中の2歳児の不眠に対する睡眠薬使用の検討
〈目次〉
この事例を選んだ理由は?
看護師の気づきを重視したのはなぜ?
ケースカンファレンスのねらいは?
事例をめぐるQ&A
この事例を選んだ理由は?
渡邊 この事例を選んだ理由を教えてください。
河俣 日常的な看護のなかにも、じつは見過ごされていることがあると気づかされた事例でした。
本事例は、“幼児期の子どもが示すストレスサインを捉える重要性”を示してくれました。これは、言語的に表現できない子どもをどのように捉えるか、その視点を大切にする小児看護には重要なことでした。
基盤となる理論として、リチャード.S.ラザルスの「ストレスとコーピング理論」があります。子どものストレス反応は、低年齢ほど認知発達が未熟でありストレス対処行動にも限界があります。また言語化できないためにストレスを生じやすく、ストレス反応としてさまざまな反応が現れます。
子どもがネガティブな反応を示した際に、ストレスとなる要因がありストレスに対処しているのではないかという視点が重要だと考えています。
看護師の気づきを重視したのはなぜ?
渡邊 なぜ河俣さんは、意図的に病棟看護師の気づきにはたらきかけたのでしょうか?河俣さんの看護師へのかかわりの意図とは何だったのでしょうか?
河俣 看護師には、「子どもが出すサインには何らかの意図があることに気づける力」が必要だと考えています。看護師の気づきにはたらきかけることで、問題を焦点化し、解決するため具体的な介入につながります。
また、スタッフが気づいていることを共有し、評価されることも重要です。 子どものストレスサインをスタッフ自身が捉えていたことが問題解決につながり、結果的に子どもが身体的にも心理的にも苦痛が軽減されたことを実感することで、さらにスタッフの看護力が高められることにつなげたかったのです。
この記事は会員限定記事です。