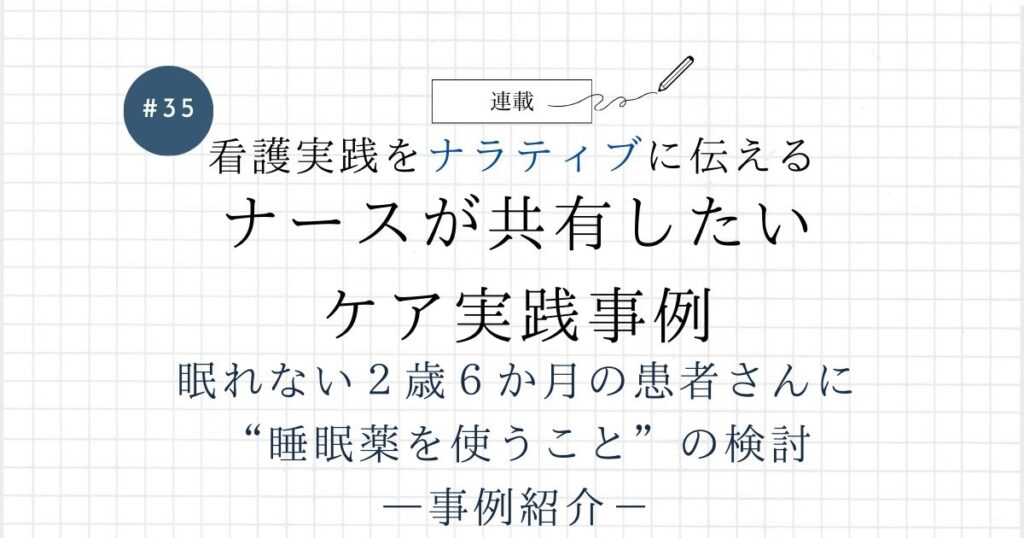事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は化学療法中の、眠れない2歳6か月の患者さんに“睡眠薬を使うこと”の検討についての事例を紹介します。
〈目次〉
眠れない2歳6か月の患者さんに“睡眠薬を使うこと”の検討
眠れない要因を挙げていく
ストレス要因を紐解き、あわせて対応を考える
睡眠薬を使うことについての母親との打ち合わせ
ケースカンファレンスでの振り返り
眠れない2歳6か月の患者さんに“睡眠薬を使うこと”の検討
Aくんは2歳6か月の男児で、急性骨髄性白血病のため臍帯血移植に向けて化学療法中でした。
骨髄抑制のため1か月前から準クリーンルームでの個室管理となっており、移植後にもさらに個室管理が長期化することが予想されました。入院中は母が24時間付き添いをされ、毎日、日中には父の面会がありました。
夜勤の担当看護師として訪室した私に、母から、「最近、ぐずつくことが多くてずっと抱っこしないといけない。遊ぶことも少なくなって、夜もおむつを替えるだけで起きて泣き、自分も睡眠不足で疲れてきました。どうしたら夜も寝てくれるのでしょうか」という発言がありました。
私は病棟で実践を通じて、子どもと家族とを主体にした看護について病棟看護師とともに考えたり、看護師からの相談を受けスタッフ自身が解決できる力を引き出せるようにかかわっていました。
母の発言を受け持ち看護師に伝えると、受け持ち看護師は、Aくんの不眠と、Aくんが眠れないことによる母の身体的負担の軽減に対するケアが必要と考え、入眠を図るケアとして“Aくんへの睡眠薬の使用”について、看護師のデイカンファレンスに提案しました。
眠れない要因を挙げていく
受け持ち看護師は、児と母親が十分に睡眠をとれていない状況に気づいていました。デイカンファレンスでは、他の看護師が捉えているAくんと母親の様子、および看護師のアセスメントを出し合い、共有しました。
見えている現象は“子どもの不眠と母の身体的負担がある”ということでしたが、デイカンファレンスに参加していた私は、以下の観点で意図的な質問を投げかけながら、看護師の気づきにはたらきかけました。
●問題の焦点が「不眠」かどうかを見きわめる
●Aくんにとって不眠となる「原因」を導き出す
●幼児期の非言語的な「ストレスサイン」を理解し、スタッフと共有する
●具体的な「介入の方法」を導き出すことができる
例えば、「遊びが少ない」という母親の発言から、日中のAくんの様子や、看護師がかかわる際の様子、看護師が気づいているAくんのサインについて問いかけました。
その結果、Aくんについて以下のような多くの気づきが出されました。
①夜間だけでなく日中も昼寝をしない
②1日中ぐずつき、抱っこを要求する
③笑うことが少なくなり、眉間に皺を寄せている表情が多い
④母親以外の人に触れられることを嫌がる
⑤寝言で「いや、終わり」という否定的な言葉がある
⑥食事に集中できずおやつも欲しがらない
ストレス要因を紐解き、あわせて対応を考える
そこで私は、まずはスタッフがAくんの表出しているサインに気づいていることを言語的に評価して、Aくんのストレスサインを共有しました。
次に問題を焦点化するために、さらに「不眠は確かに問題ですが、不眠の原因は何でしょうか。たくさん表出しているAくんのストレスサインは、どこからくるのでしょうか?」と問いかけると、原因としては、以下が挙げられました。
●化学療法による倦怠感
●個室管理による限られた空間により、行動や遊びが制限されてしまうこと
●移植をひかえ、医療者による処置の回数が増えたこと
受け持ち看護師は、問題の焦点は不眠ではなく“子どもの身体的苦痛”“子どもの高いストレス”であること、また、幼児期の子どもが示す非言語的なストレスサインとコーピングに気づくことができました。
ここで気をつけたいことは、スタッフ自身が気づくように導くことです。最初は“不眠”という問題でしたが、じつはその根底に身体的苦痛と心理的苦痛があることに気づくことが重要です。
問題が焦点化された結果、身体的苦痛緩和とストレス軽減への具体的介入について検討しました。具体的介入としては以下が挙げられました。
①薬剤使用による睡眠の確保
②医療者による血圧測定を最小限に控えること
③安心できる個室の空間づくりのためにベッド上以外に畳敷きの場所を設置する
④短い時間でプレイルームでの遊びを取り入れる
⑤医師にも協力を得て、遊びの際は診察や処置を行わないこと
私たちはこれらを母親と医師とも共有し、実施しました。
睡眠薬を使うことについての母親との打ち合わせ
当初、母親は睡眠薬に関して、「薬を使うことで悪影響はないか、癖にならないか」と心配していましたが、癖性はないこと、2~3日使用して睡眠が得られたらAくんのストレスが軽減する可能性があり、その際には使用を中止してもよいことを説明し、投与に同意されました。
睡眠薬は、母親と使用時間を決めて、同日の夜から開始しました。翌朝、Aくんは早くから目覚めたため、15分ほどプレイルームで遊びました。
2日目には母親からAくんについて、「長時間寝ることはなかったけれど、短い時間でも、おむつ交換でも起きずに寝ていました」と話がありました。
昼もよく遊ぶようになったこと、ベッド以外の畳の空間がお気に入りであること、1人遊びもできて抱っこの時間が少なくなったことが告げられ、また、「今日は笑ってくれて、元に戻ってうれしいです。私も眠れてぐっと楽になりました」と言われました。
3日目には薬剤を使用しなくても、夜間の入眠が図れました。
ケースカンファレンスでの振り返り
この事例を、看護師や医師と共有するために私たちはケースカンファレンスを実施しました。
目的は、看護師や医師と、長期間に個室管理が必要な幼児に対するケアについて検討することと、本事例のように非言語的な幼児期のストレスと対応について、スタッフの気づきがあったから解決できたことを評価し、フィードバックすることです。
医師からは、「ベッド以外に個室に畳敷きの空間をつくることに最初は反対だったけど、一緒に少し遊ぶことで診察にも協力的になった。空間づくりの大切さを感じました」という意見がありました。
また看護師からは、「子どもが寝ないことでお母さんの不眠の訴えに捉われてしまったけど、本当の問題が隠されていることに気がつきました」「言葉で発せないからこそ、体全体で表現している子どもたちのサインをしっかりみていきたい」と言い、この事例をもとに、“子どものストレスとストレスコーピング”について学習会を開催することになりました。
看護師は日常的に、子どものケアや遊びを通して、さまざまな子どものサインを観察しています。それらが重要な子どものサインであることを結びつけられれば、問題が焦点化され具体的なケアにつながることを実感した事例でした。
※この記事は『エキスパートナース』2016年12月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。