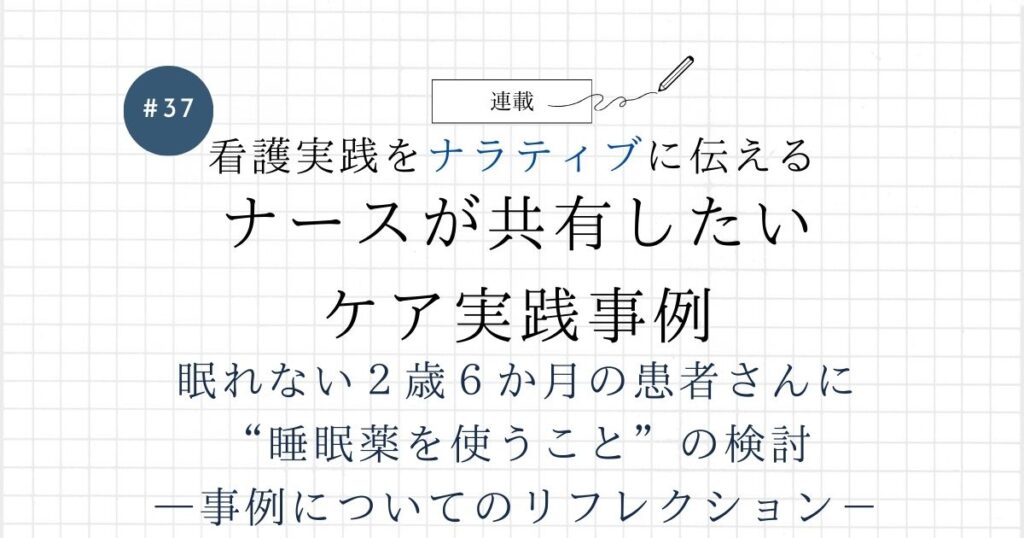事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は化学療法中の、眠れない2歳6か月の患者さんに“睡眠薬を使うこと”の検討を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第35回】化学療法中の2歳児の不眠に対する睡眠薬使用の検討
〈目次〉
カンファレンスの主眼は“母親”?“Aくん”?
サインを受け取ることで広がる看護介入
学びを引き出し、次のステップへ
事例についてのリフレクション
カンファレンスの主眼は“母親”?“Aくん”?
医療チームで行われるカンファレンスは、そこに参加する医療者が注目している関心事を中心に話題が展開されていきます。
この事例の最初のカンファレンスの焦点は、「眠れない2歳6か月のAくんへの“睡眠薬の使用”」についてでした。これは、Aくんが眠れば付き添いの母親の身体的負担が軽減できるという、“母親”に主眼が置かれたものです。
この議題をそのまま展開すると、眠れていないAくんに睡眠薬を使うことを前提として、いつ・どのように睡眠薬を使うかなど、“睡眠薬の使い方”を中心にカンファレンスが進んでいくことが予想されます。これは看護介入の“方法”に着目した話し合いの展開となります。
このとき河俣さんは、最初からAくんに睡眠薬を使うという看護介入に着目するのではなく、“2歳6か月のAくん”に着目しました。
そもそもなぜAくんが眠れていないのだろうか。その原因は何か。この事例の看護問題がAくんに生じていることだと捉えた河俣さんは、カンファレンスが“Aくん”中心の話題になるように、意図的に看護師にかかわっていきました。
そこには、「言語的に表現できない子どもにおいても、彼らの表情や態度には何らかのサインとして意味がある」という“子どもを主体”として捉える河俣さんの考えがありました。
付き添っている母親から言葉で訴えられると、その言葉の訴えを問題として捉えがちになってしまいます。 しかし、医療者からみれば、“日常”である、病児や付き添う大人(健康な成人)が過ごしている病室の環境について、子どもを主体として改めて考えてみるという作業は、チームにとっては新鮮な視点だったのだと思います。
サインを受け取ることで広がる看護介入
この記事は会員限定記事です。