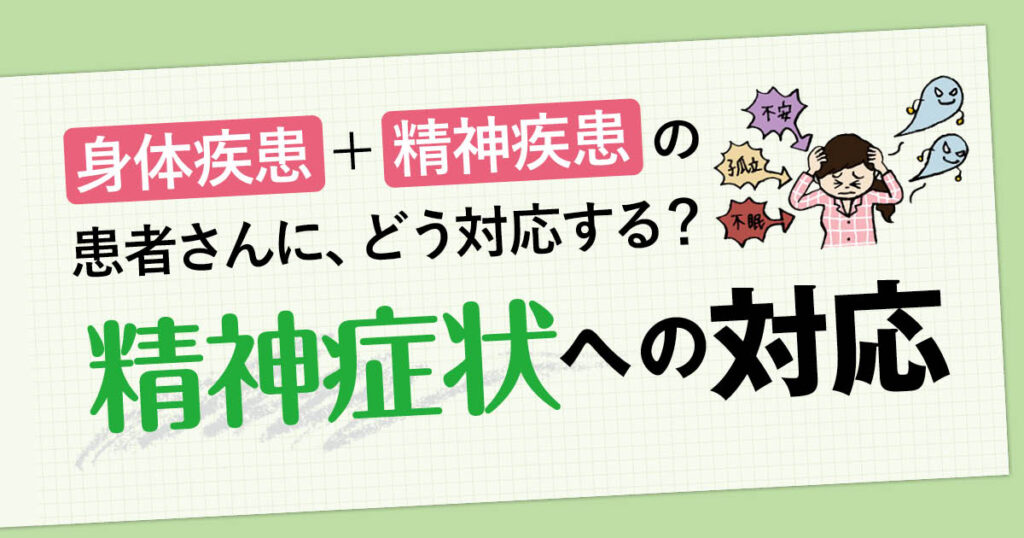精神症状が現れている患者さんへ、看護師ができることとは?「安易な共感はせず、“認証する”」「“侵襲的でない空気”をつくる」「患者さんを“あせらせず”、“ゆとり”をもてるようにする」という3つの対応を紹介します。
対応1 安易な共感はせず、“認証する”
基本は患者さんの言葉を“なぞって繰り返す”
精神的な対応において、よく出てくるのは“共感”という言葉。患者さんを癒すには共感をもってこちらで抱えればよいのだ、という指摘も確かにありますが、いたずらに共感してしまうのはちょっと恐い部分もあります。
特に身体疾患の患者さんは「健康なあなたに、わたしのこの痛みやつらさをわかられてたまるか!」という思いを抱くことがあります。
医療者が支持していると思っていても、患者さんは侵襲と感じることもあるため、精神症状に安易な共感はしない。これが重要です。患者さんの気持ちをなぞるように聞き、わからない部分があれば詰問調にならないように繰り返し聞いてみて理解を深めていく(“なぞって繰り返す”がポイント)。
気持ちのすれ違いにならないように、「こちらの思い描いているイメージ」と「患者さんのもつイメージ」ができるだけ一致するように心がけます。
“認証”とは、論理的に患者さんの苦しみを理解すること
イメージの一致というのは、患者さんの背景を読みとって察した内容が患者さんの思いと重なり、それが両者で共有されることを意味します。患者さんが「つらい」と言ったとき、すぐに「そうだよね、つらいよね」と返した場合、こちらの「そうだよね」ははたして患者さんの背景と合致しているでしょうか?
例えば「この人はがんで入院しているからつらいんだ」と早合点していないでしょうか? ひょっとしたら違う内容でつらく思っているかもしれませんし、たとえそうであっても、それを患者さんの口から言ってもらって、それをこちらがなぞって繰り返すという行為が、イメージが一致したという思
いを両者に生みだします。
そして「あぁそうだったの。そんな状況ならこういう気持ちになるのも無理はないですね」という“認証(validation)”を行います。この“認証”は、こちらは患者さんの苦しみを完全に追体験はできないけれども、背景を知ることで論理的に理解できるということを指します。それが“抱えること”でもあり、その繰り返しの果てに真の共感が見えてくるのでしょう。
早々に助言を行うと“意見の押しつけ”になってしまうため、まずは患者さんの話をなぞって繰り返して“抱える”状態にするのが大事です。
対応2 “侵襲的でない空気”をつくる
言葉のみならず医療者と患者さんとの間の空気というのも重要で、そこにはこちらの声の音色や高さ、表情、しぐさ、視線などが含まれます。言葉というのはノンバーバル(非言語的)な要素によって意味が異なってきて、それはプラスにもマイナスにもなります。その力を知って、できるだけ患者さんに侵襲的でない空気をつくっていきましょう。
同じ言葉でも、目線が上からであったり、患者さんのほうを向いていなかったり、語気が強かったり。それだけで言葉の意味はきついものになってしまいます。こういった細かいところに配慮することが、空気の色合いをよくしてくれます。
ケアの場というものを患者さんにとって安心できるものに整えていく。そうすることが患者さんのしなやかな回復力(レジリエンス)を助け、“こころのスペース”を広げることにつながります。症状を叩くのみならず、患者さんの置かれている生活を感じてよりよくしていくことが、ケアに求められてくるのです。
この記事は会員限定記事です。