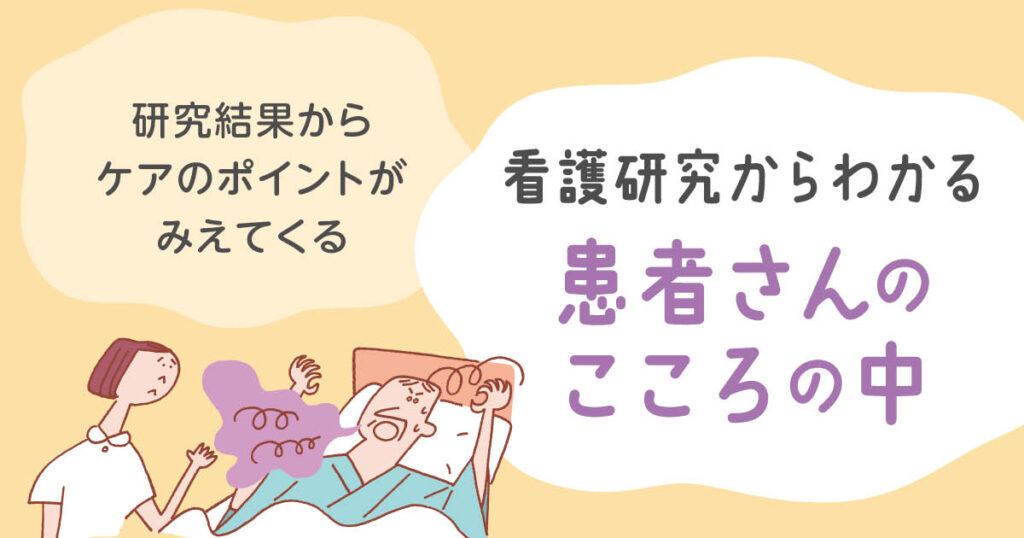降圧安静治療を受ける急性大動脈解離患者さんの心理に関する研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。疾患・治療についての情報提供、心理面や環境の整備などが大切です。
前回の記事:降圧安静治療を受ける急性大動脈解離患者の心理とは?【看護研究#35】
安静の必要性を理解し、安静を保持できるようにする
●患者さんが情報を欲している状態もしくは聞く余裕があるかを、患者さんの状態を見ながら判断する
●疾患・治療、そして先の見通しというように順序立てたうえで、患者さんの知りたい内容に合わせ適切なタイミングで説明する
●安静が保持できるよう、マッサージを行ったり、動いてよい範囲を実際に示す
疾患・治療の認知には、説明する内容の順序性や時期ごとに段階を踏んだ説明が鍵を握っており、患者さんが疾患・治療を認知し、自己効力感を高められるような支援が必要であると考えられました。
大動脈解離患者さんに対して行いたいケア
①情報提供
1)順序立てて段階を踏んで、病状などの説明を行う
●安静の必要性を認識してもらう
2)患者さんの心理状態や病態に合わせて、タイミングを見きわめ情報を提供する
●発症直後や CCU 入室時などの状態に合わせる
●検査データなどももとに、情報を欲する余裕があるかどうかを判断する
1)順序立てて段階を踏んで、病状などの説明を行う
“痛みは継続せず意識もしっかりしている”“自分でも体を動かそうと思えば動かせる”という状況のなかで、患者さんが安静を維持できるようにするためには、患者さんが安静の必要性を認識することが重要です。
患者さんは予想外の突然の入院やCCUという特殊な環境下に置かれ、「ただ自分の置かれている状況に、“ 何で何で???”って頭の中でグルグル回っているだけで……」と困惑・混乱した状況にあります。
CCU入室後しばらくして、やっと患者さんは医療者の話を聞く余裕が少しずつ出てきます。しかし、医療者は入院時に病状を説明したことで、“一度説明したから患者さんはわかっているだろう”と思い込んでしまっている部分があります。
そして、一度病気について説明はしたのだから、あとは治療のために「絶対安静」と安静指示が主体の説明になってしまいがちです。このようななか、患者さんは“なぜ安静が必要なのか”“どういう病気なのか”理解できず困惑するという状況が見られました。 このことから、患者さんが疾患・治療を理解し安静を保つためには、以下のように順序立てて段階を踏んだ説明が必要です。
①まず病気を知る
②次にどのような治療をするのか治療内容を知る
③そのうえで入院・治療の期間や退院後の生活など先の見通しについて知る
そして患者さんの置かれている心理状態を考慮し、患者さんが他者からの話を聞く余裕があるのかを見きわめつつ、一度説明したからと終わりにするのではなく、患者さんの状態に合わせて繰り返し説明を行うことも大切です。
2)患者さんの心理状態や病態に合わせて、タイミングを見きわめ情報を提供する
説明の適切なタイミングを見きわめることは、なかなか難しいことでもあります。以下に置かれている状況ごとの患者さんの心理状態を示します。状況によって心理状態も異なり、患者さんが求める情報も変わってきます。
①痛みがあるとき
突然発症し、痛みがあるときは、くわしい説明よりも「とにかくこの痛みを何とかしてほしい」という思いが強いです。
一方、痛みが治まり落ち着くと、「痛みもとれたし、すぐに自宅に帰れるだろう。たいしたことはないだろう」と会社のことや家のことなどほかに気になることに意識が向き、「いつ帰れるのか」と先の見通しを求めています。
この記事は会員限定記事です。