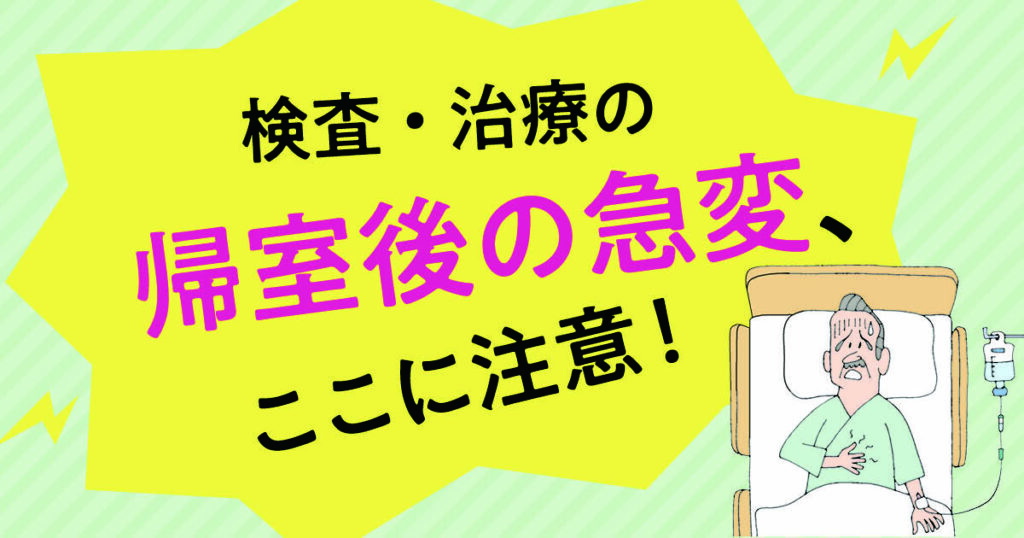検査・治療の帰室後の急変に注意!放射線治療後に注意したい、放射線宿酔や放射線粘膜炎、放射線皮膚炎のケア方法について解説します。
放射線宿酔のケア

放射線宿酔(しゅくすい)は、放射線治療を開始した初日の数時間~数日後に発症し、それ以降は改善します。症状には、倦怠感や悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛などがあり、船酔いや二日酔いのような症状ともいえます。上腹部への照射、全脳照射、全身照射は注意が必要です。
治療開始前に、放射線宿酔は必ず起こるものではないこと、症状が出現しても一時的であることを患者に伝え、緊張や不安を取り除くことが必要です。
治療前後で食事の工夫も大切です。上腹部へ照射する場合は、照射前の食事(特に胃に長く停滞する高脂肪食や固形食品)を少なくしたり控えたりすることがあります。放射線宿酔発症時は、3回の食事にこだわらず、食べられるときに、無理のない量を、少しずつ摂取するように指導します。
また、悪心・嘔吐があるときは、グラニセトロンを点滴、あるいは内服することがあります。全身照射では事前に投与することもあります。
放射線宿酔のケアでは、心身の安寧、食事の工夫、必要に応じた薬剤の使用が大切です。
放射線粘膜炎のケア

放射線粘膜炎は、口腔や食道、膀胱、腸管などの粘膜に放射線が照射されることで発症します。症状には、口腔内・咽頭痛、嚥下時痛、頻尿・排尿時痛、下痢などがあります。
口腔へのケアでは、治療前より歯科受診し口腔衛生を改善することや患者へ日ごろのケアの方法を指導することが重要になります。有害事象共通用語規準(CTCAE、表1)1「グレード1」で、紅斑が軽度の場合は、アズノール®含嗽液を使用します。
「グレード2」では、疼痛を伴うため、アズノール®含嗽液に加えキシロカイン®を配合した含嗽液や内服薬の処方とスポンジブラシ・柔らかい歯ブラシの使用、食事形態を変更することが必要です。香辛料や酸味などの刺激が強い食品は避けましょう。また、口腔内が乾燥する場合は、こまめな水分摂取や含嗽、ジェル型の口腔保湿スプレーなどの使用を心がけましょう。
「グレード3」では、高度の疼痛により食事摂取が困難であるため、オピオイドの処方と高カロリー輸液や胃瘻での栄養管理が必要になります。
腸炎(下痢)へのケアでは、肛門周囲の衛生が必要になります。温水洗浄便座の使用をすすめ、水圧は弱く、温度はぬるくすることを説明します。それでも疼痛で使用できないときは、サニーナ®などのケア用品で無理なく拭きとることができます。洗浄は、弱酸性のボディーソープなどで1日1~2回程度、ぬるま湯で洗いましょう。洗いすぎはバリア機能が低下しますので注意します。
この記事は会員限定記事です。