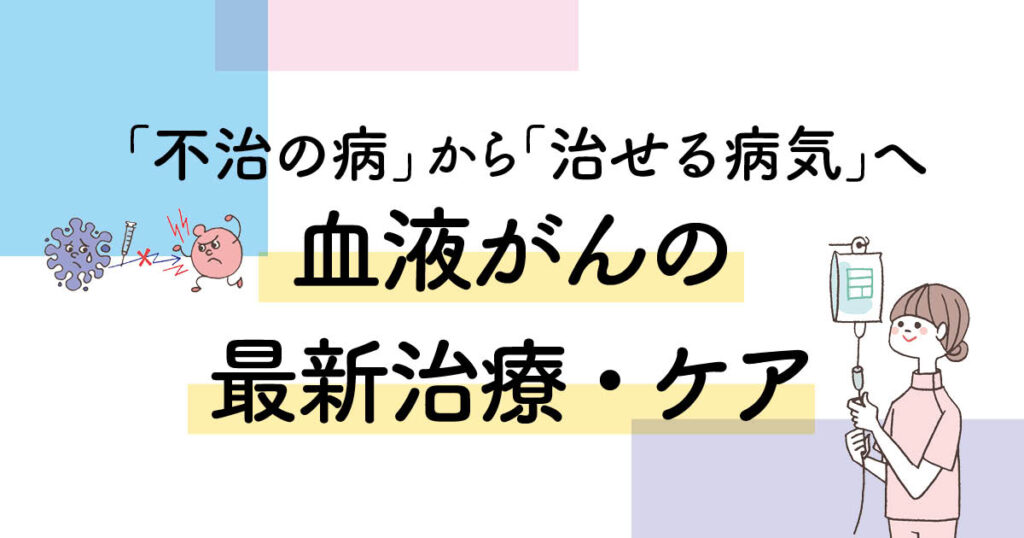白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液がん。現在では不治の病ではなく、治せる病気になってきています。この連載では、血液がんの最新の治療・ケアについて解説する全20回の連載です。
【第1回】血液がんは治せる時代へ:最新治療と生存率
〈目次〉
●代表的な血液がん
・白血病
・多発性骨髄腫
・悪性リンパ腫
●造血幹細胞移植や分子標的治療薬などにより「治せる病気」に
【第2回】血液がん患者の増加と新規薬剤による最新治療
〈目次〉
●高齢化に伴い、血液がんの患者さんは増加
●治療薬、支持療法薬の進歩で楽に安全に効果的な抗がん剤治療が可能に
【第3回】血液がんの免疫療法:免疫チェックポイント阻害剤、CAR-T療法とは?
〈目次〉
●免疫チェックポイント阻害剤のしくみ
●実臨床に導入されつつあるCAR-T療法
・免疫療法薬の代表的な副作用
・全身的な副作用
【第4回】がんサバイバーシップとは?血液がん患者の社会生活サポート
〈目次〉
●「治せる病気」となった現在におけるがん治療の“成功”の変化
●社会全体でがんサバイバーを支えるがんサバイバーシップという考え方
●治療の進歩に伴い、増してきている多職種ケアの重要性
【第5回】血液がんの化学療法中の発熱性好中球減少症、骨髄抑制に注意
〈目次〉
●発熱性好中球減少症とは?
●分裂速度の速い正常な細胞にも作用してしまう
●骨髄抑制が副作用として現れる
【第6回】発熱性好中球減少症が疑われるときは?血液がんの化学療法中の注意点
〈目次〉
●発熱性好中球減少症の特徴は?
●発熱性好中球減少症が疑われるとき気をつけることは?
●発熱性好中球減少症が疑われるときの検査や治療の進め方
・発熱性好中球減少症に対して保険適用のある抗菌薬
【第7回】発熱性好中球減少症の血液培養・胸部X線撮影のポイント
〈目次〉
●血液培養のポイント:2セット以上採取しよう
●胸部X線撮影のポイント:以前に撮影した画像と比較しよう
【第8回】血液がん患者の感染予防のためのセルフケアと看護師の役割
〈目次〉
●患者さん自身にセルフケアを習得してもらうことが大切
●患者さんのセルフケア獲得に向けて看護師ができること
・退院後のLTFU受診のタイミングと留意事項
●LTFU外来ではどんなことをする?
●病棟内の無菌環境はどうなっている?
【第9回】血液がん患者の感染対策とは?看護師が気をつけたいポイント
〈目次〉
①身体の清潔・スキンケア
②口腔ケア
③服薬管理
④食事
⑤環境整備
●看護師の清潔行動はどうする?
【第10回】血液がん患者の食事とは?管理栄養士が解説
〈目次〉
●ひとくちに「病院食」といっても施設によって内容はさまざま
●食思不振時にも摂取できる「食思不振対応食」が整備されつつある
【第11回】管理栄養士が解説!血液がん患者の食事の工夫と注意点
〈目次〉
●差し入れや自分で購入した食品も含めて食事摂取量が維持できるように考える
・管理栄養士・栄養士ができる食事の対応
・食べ方のパターンでわかる食事の注意点
【第12回】造血幹細胞移植治療時の血液がん患者の食事管理
〈目次〉
●「大量調理施設衛生管理マニュアル」に則った食事に
●移植治療時の食品の選択のポイント
【第13回】血液がんの化学療法中のリハビリの基礎知識
〈目次〉
●化学療法中のリハビリテーションはなぜ必要?
●予防的なリハビリテーションとは?
・予防的なリハビリテーションの内容(大阪国際がんセンターの例)
・看護師や医師からの声かけが効果的
【第14回】骨髄抑制中のリハビリで気をつけること
〈目次〉
●化学療法中のリハビリ介入のポイント
●易感染性への対策
●易出血性への対策
●貧血への対策
【第15回】血液がんの化学療法による妊孕性低下の原因
〈目次〉
●がんサバイバーの増加で注目される妊孕性の低下という副作用
●がん患者における妊孕性低下の原因
①年齢的に妊娠が困難な状況である可能性がある
②卵巣は化学療法に対して非常に敏感な臓器である
【第16回】妊孕性温存治療の種類と看護介入のポイント
〈目次〉
●妊孕性温存治療にはどんなものがある?
●適切な時期での情報提供と意思決定を支えるのが看護師の役割
【第17回】血液がんの化学療法における抗がん剤曝露予防
〈目次〉
●抗がん剤曝露による健康への影響とは?
●抗がん剤曝露の経路は?
●抗がん剤曝露の場面にはどんなものがある?
●閉鎖式薬物移送システム(CSTD)
【第18回】抗がん剤曝露予防:個人防護具の使用法と投与管理時のポイント
〈目次〉
●個人防護具の適切な使用法
●投与管理の手順と注意点
【第19回】抗がん剤曝露予防:病棟内での注意とこぼれたときの対処
〈目次〉
●病棟内で汚染に気をつけたい場所
●抗がん剤がこぼれたときの対処法
【最終回】造血細胞移植コーディネーターとは?
〈目次〉
●レシピエント、ドナー、医療従事者の調整を担う新たな専門職
●移植全体のプロセスに継続・中立的にかかわることが大切
・HCTC の役割とドナー・レシピエントの思い