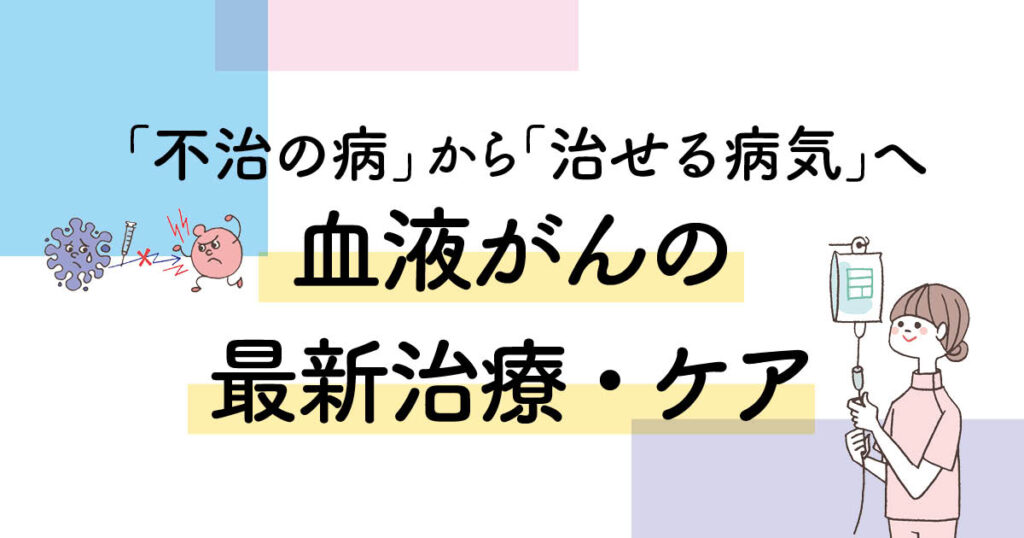白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は、血液癌の化学療法中に骨髄抑制をきたした際、リハビリを行ううえでの注意点を紹介します。易感染性、易出血性、貧血への対策とは?
化学療法中のリハビリ介入のポイント
化学療法中は、強い骨髄抑制をきたすことがしばしばあります。しかし骨髄抑制中であっても、患者さんの状態をきちんと把握し、適宜医師へ指示を仰ぐことでリハビリの実施が可能な場合もあります。
そもそも血液がんの患者さんにおいては、骨髄抑制中でなくとも血液データに変調をきたすため、日々の変化を常に把握してリスク管理に努める必要があります。
骨髄抑制中のリハビリ実施にあたり特に気をつけることとしては、
①易感染性、②易出血性、③貧血
が挙げられます。
がん患者におけるリハビリ中止基準では、血液データに関してはヘモグロビン7.5g/dL以下、血小板50,000/μL以下、白血球3,000/μL以下1となっています。
当院でもこれを参考に中止検討基準を設けており、該当する場合は主治医と協議したのち実施の可否を決定するとしていますが、みなさんお気づきのとおり、この基準では血液がんの患者さんへのリハビリの提供は困難です。
そのため、適宜医師へ相談しながら実施の可否だけでなく、内容や場所についても決めています。
リハビリを行ううえで注意すべき点は、ほかにもたくさんあります。例えば、末梢神経障害で足底感覚が鈍麻していたり、下肢に浮腫があると転倒リスクは高くなりますし、粘膜障害で食べられなかったり、下痢がひどいと栄養状態が不良となりやすいので、運動時の過負荷に注意しなければなりません。
化学療法中の血液疾患の患者さんにリハビリを行うにあたり、難しいと感じることも多々ありますが、医師や看護師、管理栄養士、臨床心理士、薬剤師などの多職種と協働して取り組むことで、よりよいリハビリが提供できると考えます。 また、その多職種連携の輪の中心には常に患者さん、ならびに患者さんを支える家族がいることを忘れずに取り組むことが大切です。
易感染性への対策
免疫力が低下している患者さんは、基本的に無菌病棟内でリハビリを実施します。無菌病棟以外で治療を行っている患者さんに関しては、部屋から出てもよいのかなど、安静度について適宜、確認が必要です。
この記事は会員限定記事です。