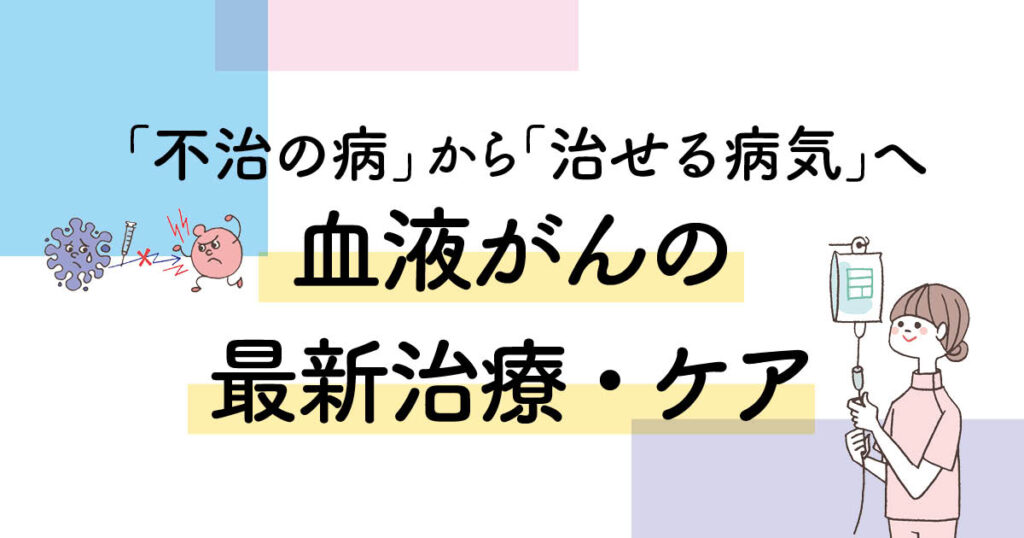白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は、化学療法の副作用である妊孕性の低下を取り上げます。その原因、治療前に説明すべきリスクとは?
がんサバイバーの増加で注目される妊孕性の低下という副作用
妊孕性(にんようせい、fertility)とは、妊娠する能力といわれています。
化学療法を行うと、吐き気や倦怠感などの急性期の副作用とは別に、卵巣機能障害、精巣機能障害といった不妊につながる妊孕性低下という晩期的な副作用が出現することがあります。
近年、がんサバイバー(がん治療後の生存者)の増加により、がんサバイバーのQOLに対する関心が高まってきています。QOLにかかわる問題の1つとして、治療によって生じる妊孕性低下・消失があります。がん患者は疾患が完解しても、これらの問題を抱えることになるためです。
がん患者における妊孕性低下の原因
がん患者の化学療法における妊孕性の低下は、おもに2つの原因があります。
①年齢的に妊娠が困難な状況である可能性がある
卵巣における卵子数は加齢とともに徐々に減少します。さらに加齢に伴い、卵子の質は低下し、受精能が低下(一般的に35歳を境に妊孕性低下は加速)。
よって、がん治療後数年が経過し、主治医が妊娠可能と判断したときには、すでに年齢的に妊娠が困難な状況になっている可能性があります。
②卵巣は化学療法に対して非常に敏感な臓器である
化学療法の結果生じた卵巣機能不全は化学療法誘発性無月経といわれ、「化学療法開始後1年以内に生じる3 か月以上の無月経」と定義されます。発症頻度は年齢や化学療法のレジメン、抗がん剤の投与量によって0~100%と異なります。
特にアルキル化剤(ブスルファン、メルファラン、シクロホスファミド水和物、イホスファミドなど)は、卵子および顆粒膜細胞への毒性が強く、卵巣機能不全になるリスクが高いです。
治療前にリスクの説明を
2006年に米国臨床腫瘍学会(American Society of Clinical Oncology:ASCO)はがん患者における妊孕性温存に関するガイドラインを示しました。また、化学療法・放射線療法における性腺毒性によるリスクについては、ASCO2013から報告されています(表1)。
表1 ASCO2013 における化学療法および放射線療法の性腺毒性によるリスク分類(女性)
この記事は会員限定記事です。