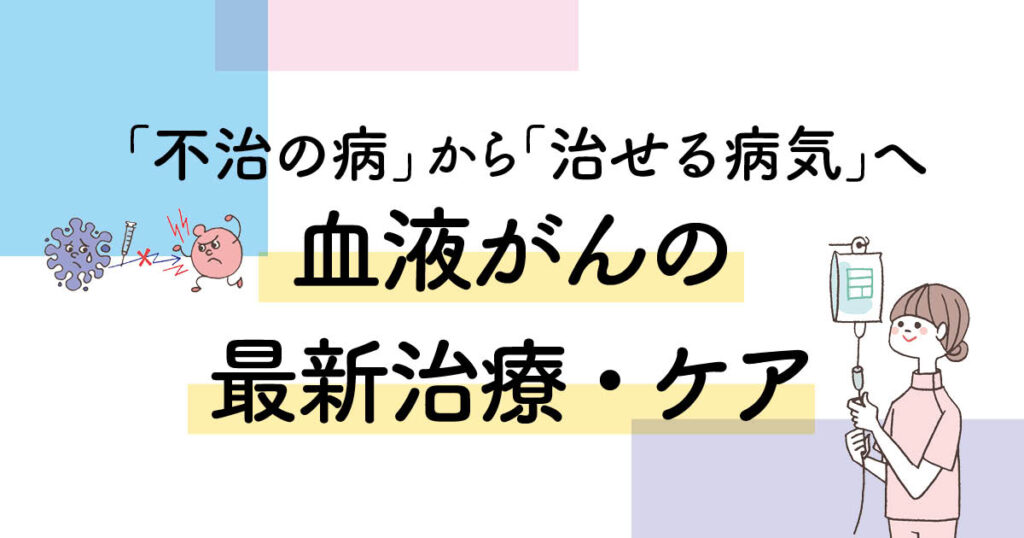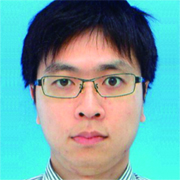白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は血液がんの化学療法中に注意が必要な発熱性好中球減少症の対応を紹介。血液培養や胸部X線撮影のポイントをお伝えします。
血液培養のポイント:2セット以上採取しよう
血液培養採取のタイミングとしては、発熱後すぐが一番菌量が多いといわれており、発熱後すみやかに採取することがすすめられます。
血液培養ボトルは好気ボトル1本、嫌気ボトル1本を合わせて1セットとし、2セット以上採取することがすすめられます。
2セット以上採取する理由としては、血液量が増えるため菌の検出率を高めることができることや、検出された菌が真の原因菌なのか、混入した菌(コンタミネーション)なのかの鑑別に用いることができます。
中心静脈カテーテル挿入中の患者さんが発熱性好中球減少症を発症した場合、末梢静脈穿刺のほかに、中心静脈カテーテルから採取した血液培養を1セットずつ採取することが推奨されます。
中心静脈カテーテルから採血する際は清潔操作で行います。合併症が増加するため、血栓塞栓症にも注意が必要です。予防にはカテーテル内に血液が残存して凝固することを防ぐため、採血後の十分なフラッシュが大切です。
胸部X線撮影のポイント:以前に撮影した画像と比較しよう
入院患者において発熱性好中球減少症を発症した場合に、胸部X線写真を撮影することはよくあります。胸部X線は通常立位で撮影しますが、血液疾患の患者さんで、クリーンルームで治療を受けているなどの理由でX線撮影室まで移動できない場合は、ポータブルX線撮影装置での撮影を行うこととなります。
この記事は会員限定記事です。