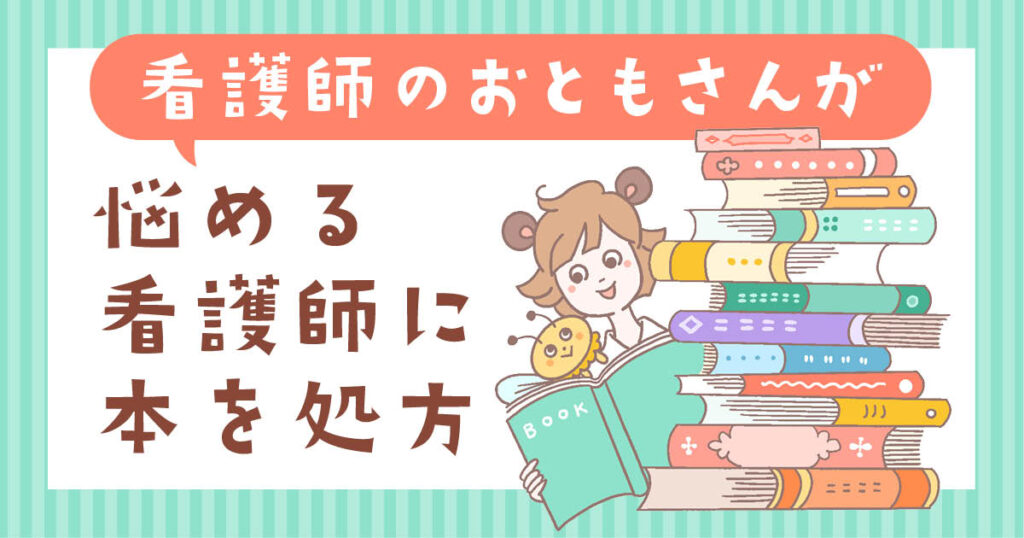本が大好きな看護師のおともさんが、“あなた”に寄り添った本を紹介するブックセラピー企画。看護師さんのさまざまなお悩みに合わせて、相談者にぴったりな書籍を教えてくれます。「勉強会担当になった」というナースにおすすめの本とは?
看護師のおともかんごしのおとも
救急外来部門・シミュレーションセンターで主任を務める看護師。実家も今の家も、本だけで丸々1部屋を使ってしまっているほどの本好き。@99emergencycall
看護師4年目のDさん
今年度の勉強会担当になりました。テーマは自分たちで考えてOK、必要があれば医師や先輩看護師、他職種などを巻き込んで開催してもよいという自由さがあるがゆえに、どうしたらいいかわかりません。勉強会を進めるうえで、大事なことを学べる本を知りたいです。また、資料づくりやプレゼンの基礎も知りたいです。
勉強会の第一歩、効果的なスライド作成のコツ
白石 勉強会担当ですか~。私もなかなか苦手なところですが、そういった看護師さんへのおすすめ本を教えてくださいとのことです。
看護師のおとも
このあたりの本もいろいろ読みましたよ~。最近、対面での勉強会も再開され始めていますからね。ちょっと待っていてください……(本棚をガサゴソ)。
勉強会を開くとなると、いろんな準備が必要になってくると思うんですけど、まずおすすめするのがこれ。『医療者のスライドデザイン プレゼンテーションを進化させる、デザインの教科書』です。
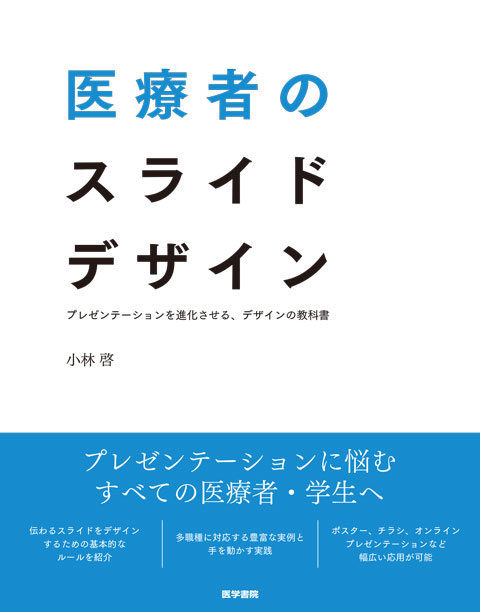
医療者のスライドデザイン プレゼンテーションを進化させる、デザインの教科書
小林啓 著
医学書院
B5変形判
3,740円(税込)
看護師のおとも
以前、後輩が勉強会用の資料を作るとなったときに、「今まで避けてきたから、スライドの作り方がわからない」と言われたことがあるんですよ。
白石 そうなんですか。たしかに学生のときはあんまり作らないかもしれないですね。
看護師のおとも
僕はそういう機会に恵まれていたのか、当たり前のようにスライドを作っていましたが、たしかにやらない人はやらないなと思って。後輩にとってはすごくハードルが高かったらしいです。それでフォローしながら進めていったんですけど、やっぱり作りが粗いんですよ。1枚のスライドにぎっちり文字が詰め込まれてポイントがわかりにくい、色使いが気になって読みにくい、アニメーション作成にすごく時間がかかる……などということがありまして。
白石 本編の内容じゃないところで気が散っちゃう、時間がかかりすぎてしまうというのはもったいないですね。
看護師のおとも
人前で話すのが得意じゃない人ももちろんいますけど、それ以前にスライドを作ることをハードルに感じる人がいるんです。こちらの本では医療者がよく使うスライドの実例を紹介し、色使いやグラフ、アニメーションのほか、デザインをシンプルにするためのポイントなど基礎的なところを教えてくれています。
一歩先へ、勉強会の設計から評価まで
看護師のおとも
もう少しレベルアップ版となると、『研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン』という本もあります。インストラクショナルデザインは、授業設計などに言い換えられますね。大学院でも使われている本で、まあまあ分厚くてかなり細かいんですけど、シミュレーションセンターを兼務している僕がめちゃくちゃ読み込んでいる本です。
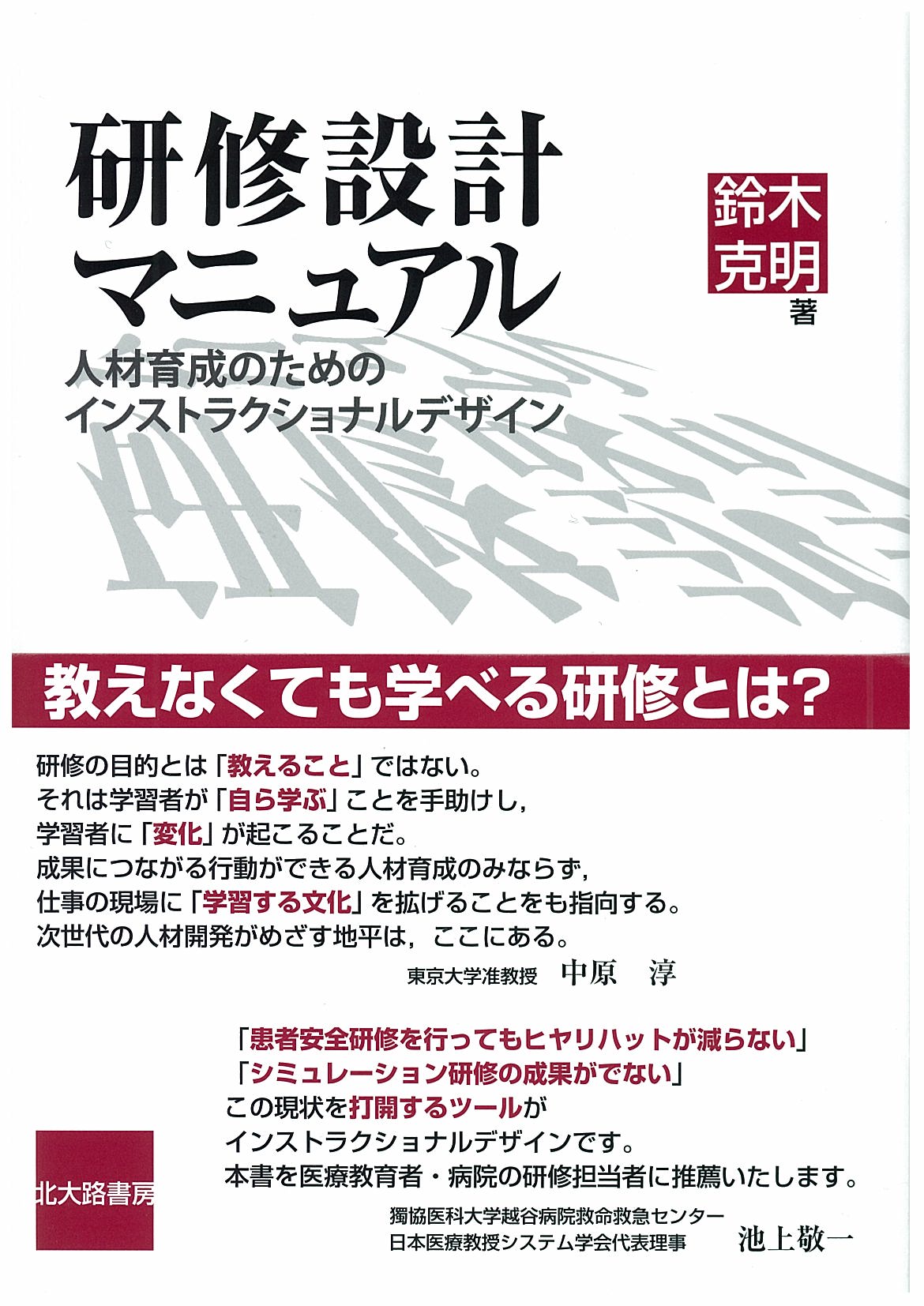
研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明 著
北大路書房
A5判
2,970円(税込)
白石 おお、なるほど。しかし、北大路書房さんっぽい表紙ですねぇ。
看護師のおとも
ザ!教科書という感じですよね。「勉強会をやります」「こういう研修をやりたいです」といったときに、テーマをどうやって決めるのか、勉強会が終わった後にどう評価するのかまで、すべてにフォーカスしています。基礎となる研修の考え方の部分、ニーズの把握の仕方、シミュレーションの考え方、評価方法、勉強した後の行動変容をどうモニタリングして支援するのか、その変化をどう継続させるかも含めて書いてあって、読み応えがあります。
これを突き詰めると、「そもそも勉強会をやる必要があるのか」という話になるんです。病棟の勉強会も慣習的に担当を振られがちですが、別の方法で置き換えられるなら手間のかかる勉強会をしなくてもいいかもしれない。もしダメだったら勉強会をする、というところから始まっています。
白石 面白いですね。もしかしたら勉強会の担当をしなくてよくなっちゃうかもしれないんだ(笑)。
看護師のおとも
本当にそうなんですよ。研修ですべてを解決しようとするんじゃないってことなんです。あと面白いのが、「教えないで学べる研修を作ろう」とも書かれていることです。
白石 教えないで学べる……なぞなぞかな(笑)。
看護師のおとも
何を言っているんだと思うかもしれないですけど(笑)。この本でいう真意としては、教えなくても自分で学ぶ人に育てる。自分でこういうことをしたい、学びたいと気づいて、自分でこの学習のサイクルを回せるようになっていく――ということなんでしょうね。そういうやってみたい、学んでみたい、もっと知りたいというトリガーを起こす仕掛けをどうやって考えるか、そのヒントが書いてあります。なかなか面白いでしょう。
白石 すごいです!ちょっと上級者向けの話ですけど、ワクワクしてきますね。
看護師のおとも
ちなみにこの本、3,000円しないんです。かなりリーズナブルな価格だと思います。
また、『講師・インストラクターハンドブック』という本もあります。これは看護に限らず、勉強会を開くとか院外講師を依頼されたときに困る人向けです。教える側に立ったときに何をすべきか、何に気をつけるべきかというところで、退屈だと思わせないためにどうするかが書いてあります。
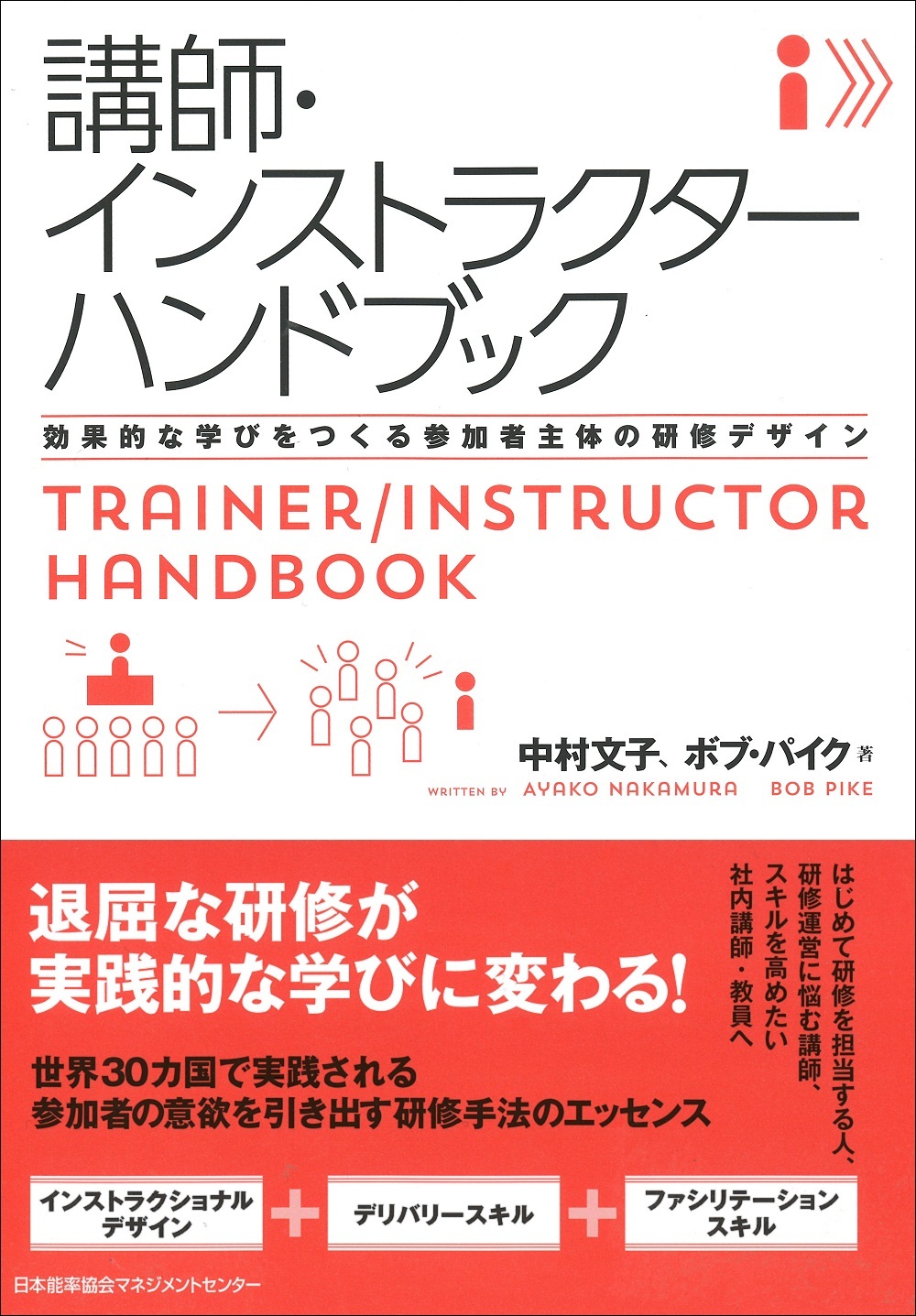
講師・インストラクターハンドブック
中村文子、ボブ・パイク 著
日本能率協会マネジメントセンター
A5判
3,080円(税込)
看護師のおとも
参加者に主体的に参加してもらうための研修方法や、歩き方、立ち振る舞い、ジェスチャーなどのノンバーバルコミュニケーション、間のつくり方、スピードのコントロールなどの話し方、教材の準備の仕方といった、インストラクターとしての基本的なスキルが載っています。それだけでなく、安心して学べる環境のつくり方、研修運営や設営の方法なども書かれています。個人的に経験則でやっていたことが補完されて、好きになった本ですね。
白石 かなり広範囲にわたって、かつ細かな内容のスキルについて触れられているんですね。医師や他職種とのディスカッションにも活きそうな感じがしますね。
看護師のおとも
とても役立つと思います。ちなみに、このシリーズは『研修アクティビティハンドブック』『研修ファシリテーションハンドブック』『オンライン研修アクティビティ』など6冊が出ていて、僕は全部持っているんです。
白石 おともさんのように沼った人はこちらへどうぞ、という感じですね(笑)。
看護師のおとも
はい、こちらへどうぞです(笑)。同シリーズの『研修デザインハンドブック』は先ほどのインストラクショナルデザインの話も入っていて、こちらも読みやすいと思います。結局、勉強会の話も行き着くところは対人コミュニケーションの話になってくるんですよね。なので、プリセプターなど教える立場になったときにコミュニケーションの基礎ができていると、勉強会にも応用が効くと思います。大勢の前で話すのは、また違ったスキルにはなってきますけど。
余談ですが、このシリーズが網羅されているような『クリエイティブ・トレーニング・テクニック・ハンドブック』という本もあります。ちょっと高価ですが、興味がある方はぜひ!
白石 それはチャレンジャーな人に、ぜひ……!!!
今回、看護師のおともさんが紹介してくれた本
『医療者のスライドデザイン プレゼンテーションを進化させる、デザインの教科書』
『研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン』
『講師・インストラクターハンドブック』
『研修デザインハンドブック』
『クリエイティブ・トレーニング・テクニック・ハンドブック 第3版』
日々、患者さんに寄り添うあなたにも、やさしく寄り添うものがあってほしい。今回紹介した本たちが、そんなあなたの心の“おとも”になれることを願っています。
看護師のおともさんに、「悩みに合う本を教えてほしい」という方を募集中。
下記URLよりご応募ください。
※掲載の有無はエキスパートナース編集部で判断し、掲載有無の結果は事前にご連絡はいたしません。
https://questant.jp/q/book_therapy_otomo
「悩める看護師に本を処方」の記事一覧
そのほかの連載はこちら
〈おすすめ記事〉
新人ナース、先輩ナースへのおすすめ本7選
プリセプターとして教えることに悩む看護師への本【悩める看護師に本を処方⑦】
エキナス編集部がレポート!「看護師さんと本屋に行こう」トークイベント~ 自分に合った看護書の探し方~
※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。