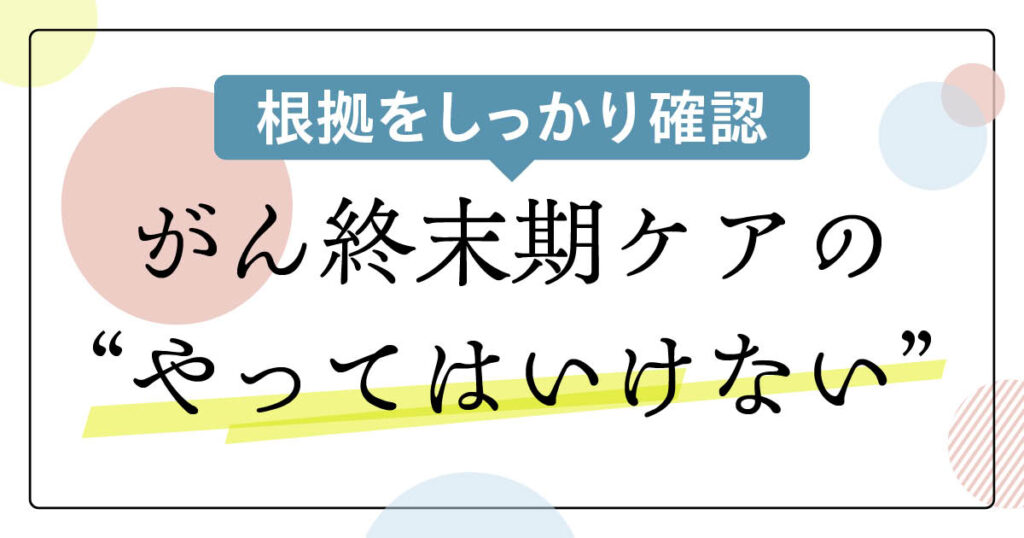がん終末期の栄養管理のポイントを解説。食欲低下やQOLへの影響をふまえ、患者や家族の“食べられない不安”に寄り添う食事ケアについて紹介します。
「がん終末期ケアの“やってはいけない”」の連載まとめはこちら
積極的な経口摂取が、必ずしも勧められるとは限らない
〈理由〉無理に食べることや食べるように勧められることが苦痛になる場合があるから
「食べられない」ことが不安の増大につながる
患者さんやご家族にとって、食べることは生きていくために重要な行為であり、「生きていること」の象徴的な意味合いをもつことがあります。
しかし、終末期には食べたくても食べることができなくなり、患者さんにとって食べることが苦痛になってくることがあります。食事が摂れない患者さんを目の当たりにし、ご家族は不安になり、食べることを勧める場面に遭遇することがあるのではないでしょうか。
終末期には「食べられなくなったらもう終わり」「少しでも食べないと体力が落ちていってしまう」という患者さんやご家族の訴えをよく耳にします。このように、「食べられない」ことは患者さん、ご家族にとって病状の悪化を自覚させ、不安の増大に結びついてしまいます。
しかし、このような食欲不振は終末期がん患者さんにおいて高頻度に出現します。ホスピス・緩和ケア病棟に入院する患者さんの約半数は空腹感を感じないという報告1もあり、食べることをご家族から強く勧められることが患者さんの苦痛となる場合があるということを知っておきましょう。
食欲不振について患者・家族に説明するポイント
そして、食事が摂取できないことは、栄養面だけでなく、食べる喜びや楽しみを奪い、生きる意欲を失うことにもつながってしまいます2。そのため、この時期には、患者さん、ご家族の食べられないことによる不安や恐怖に耳を傾ける姿勢を示し、きちんとした説明をして、納得を得ていく(表1)ことが重要となります。
表1 患者・家族への食欲不振に関する説明(例)
●患者の予後や病状によって、ケアのゴールは変化すること
●予後が週単位の場合、食欲不振は一般的な症状であること
●今まで好んでいたものと嗜好が変化すること
●運動量の減少や代謝の低下によって、必要エネルギー量が減り、今までより少ないエネルギー量で十分となること
●予後が日単位の場合、食欲不振は必発の症状であり、自然な経過であること
さらに、患者さん自身が何を望んでいるのかを知り、つらさが緩和される方法をご家族とともに考えていきましょう。そのような医療者の姿勢を目にすることが、家族にとっての安心につながります。
QOLを高めるための食事の工夫とは?
この記事は会員限定記事です。