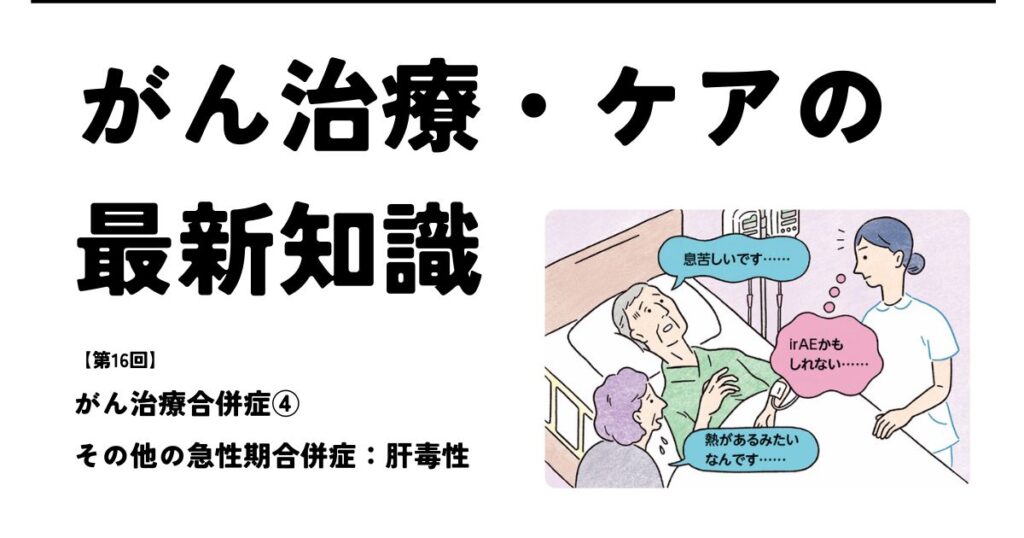がん治療・ケアの最新知識を紹介。今回は、急性期合併症「肝毒性」を取り上げます。概要や薬剤性肝障害の機序と対策、化学療法によるB型肝炎の対策の動向、肝中心静脈閉塞症(VOD)について解説します。
●近年は、免疫チェックポイント阻害薬による肝機能障害が増えている。
●化学療法によって発症するB型肝炎も重要であり、HBV陽性患者では、「B型肝炎ウイルスの再活性化」に注意が必要である。
肝毒性の概要
主な肝毒性はALT・AST上昇などの肝機能障害で、がん治療中にしばしば経験されます。原因として、薬剤・肝腫瘍や肝転移・感染症などのさまざまな要因が関与します。
抗がん薬も含めてどんな薬剤でも起こし得ますが、最近は免疫チェックポイント阻害薬による肝機能障害も増えています。また、化学療法により発症するB型肝炎が重要です。
肝障害に注意が必要な主な抗がん薬
ゲムツズマブオゾガマイシン
●販売名:マイロターグ®
●発症率:約30%
●ポイント:劇症肝炎やVOD(次ページ参照)などの重篤な肝障害も報告されている。
イノツズマブ
●販売名:オゾガマイシンベスポンサ®
●発症率:約30%
●ポイント:劇症肝炎やVOD(次ページ参照)などの重篤な肝障害も報告されている。
白金製剤(例:シスプラチン〈ランダ®など〉、カルボプラチン〈パラプラチン®〉、オキサリプラチン〈エルプラット®〉、ネダプラチン〈アクプラ®〉)
●発症率:10〜15%
●ポイント:多くは可逆性だが、肝不全の報告もある。
メトトレキサート
●販売名:メソトレキセート®
●発症率:約10%
●ポイント:肝臓の線維化が原因となるが、肝障害は一時的かつ可逆的なことが多い。治療期間や用量に依存して肝障害の頻度は増加する。
免疫チェックポイント阻害薬
【第3回】参照
●発症率:1〜5%
●ポイント:イピリムマブとニボルマブとの併用で、肝障害の頻度が約25%に増加する。
この記事は会員限定記事です。