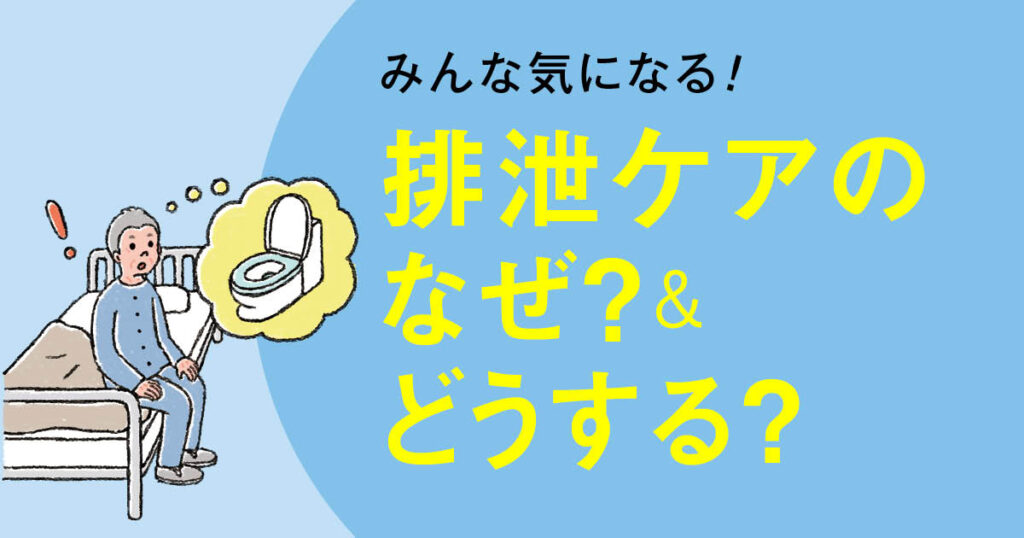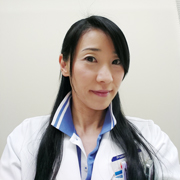尿道留置カテーテルは長期になると合併症を引き起こすリスクがあることに注意。尿路感染症、出血、結石の形成、膀胱機能の低下、膀胱の萎縮といった合併症の例を紹介します。
●尿道留置カテーテルの留置は尿路感染症をはじめ、出血などの合併症のリスクを高める。
● 本当に尿道留置カテーテルが必要か、現在留置を行っている場合はどのような理由で留置がされているのか、考えよう。
尿道留置カテーテルが必要な場面とは?
尿道留置カテーテルは膀胱の尿を排出するための処置ですが、長期になるほど合併症が増えるため、できるだけ早期に外したい治療です。ですから、今から留置を行おうとする患者さん、現在留置が行われている患者さんには、本当に膀胱留置カテーテルが必要であるのか、どういう理由で留置がされているのかを考える必要があります。
尿道留置カテーテルがどうしても必要な例としては、以下のようなものがあります。
①急性尿閉での応急処置(すぐに自排尿が改善する理由であれば、できるだけ間欠導尿で対応する)
②神経因性膀胱での慢性尿閉や多量の残尿があり、腎機能低下や水腎症を起こしている場合
③過度の膀胱容量の低下やコンプライアンス(膀胱の伸展性)の低下により、膀胱が高圧になる可能性がある場合
④自排尿が難しい下部尿路の疾患(尿道狭窄や前立腺肥大症など)があるが、他の合併症のためその治療ができない場合
⑤安静が必要な病態(術後や脳血管疾患、整形外科的疾患発症後など)である場合
⑥患者さんの病態から、正確な尿量の把握が必要な場合
相対的に必要な場合は、以下の通りです。
①尿失禁のコントロールが困難で、皮膚炎や褥瘡の悪化が考えられる場合
②高齢や寝たきりなどで移動が難しく、かつ、おむつ管理では何らかの弊害が生じる場合
尿道留置カテーテルの合併症とは?
尿道留置カテーテルによって起こる合併症には、さまざまなものがあります。以下に例を挙げます。
①尿路感染症
尿路感染症は医療関連感染の約40%を占め、そのうち66~86% が尿道留置カテーテルなどの器具が原因といわれています。
カテーテル留置期間が長いほど感染リスクが増加し、留置期間7~10日では患者さんの50%が細菌尿、30日以上になると、ほぼ100%に細菌尿が検出されるといわれます1。
細菌尿が検出されても無症候性の場合は、抗菌薬の投与や感染予防を目的とした日常的な膀胱洗浄は不要ですが、有熱性や症候性の尿路感染を発症した場合には、抗菌薬の投与やカテーテルの交換が必要となります。
②出血
カテーテルの挿入(交換)時や膀胱粘膜へのカテーテルの接触により、出血をきたすことがあります。
出血を防止するためには、挿入時に潤滑液を十分に使用し、必要な場合は潤滑液を10cc程度事前に尿道内にゆっくり注入してからカテーテル挿入を行います(男性の場合)。
留置後に膀胱内からの出血が疑われる場合には、バルーンからの先端までの距離が短いカテーテル(腎盂:じんう/バルーンカテーテルなど)を使用することで防ぎます。 カテーテルが閉塞するほどの血尿がある場合には、洗浄にて血塊を除去し、生理食塩水での還流が必要となる場合があります
③結石の形成
カテーテル内腔の結石結晶沈着の主因は、proteus mirabilis(プロテウスミラビリス)を代表とするウレアーゼ(尿素分解酵素)産生菌の感染とされています。この感染により、尿のアルカリ化、結晶析出とバイオフィルムの形成、さらに膀胱結石形成へと進展すると考えられています2。
洗浄にて除去不可能なサイズの結石は、経尿道的な手術によって除去する必要があります。
④膀胱機能の低下、膀胱の萎縮
尿道留置カテーテルを留置した状態では常に尿が排出されるため、膀胱が空の状態が持続することになります。通常、膀胱は尿貯留による膀胱の拡張と、排尿・導尿による膀胱の収縮が繰り返されていますが、留置により拡張が起きないため、廃用性萎縮を生じます3。
短期間であれば機能は回復しますが、長期間になると拡張・収縮ともに機能の改善が難しくなります。同じ尿道留置カテーテルでも、膀胱拡張による尿意の確認や保持のため、キャップ排尿を行うことがあります(図1)。
図1 キャップ排尿の例

⑤QOLの低下
尿道留置カテーテル治療では、連結のチューブや蓄尿バッグの存在のため、患者さんの行動に制限が生じ、QOLが著しく低下します。
このような場合は、レッグバッグ(図2)の使用や、キャップ排尿による工夫によって改善が可能です。間欠自己導尿(図3)が可能であればカテーテルフリーにすることができ、QOLは格段に改善します。
この記事は会員限定記事です。