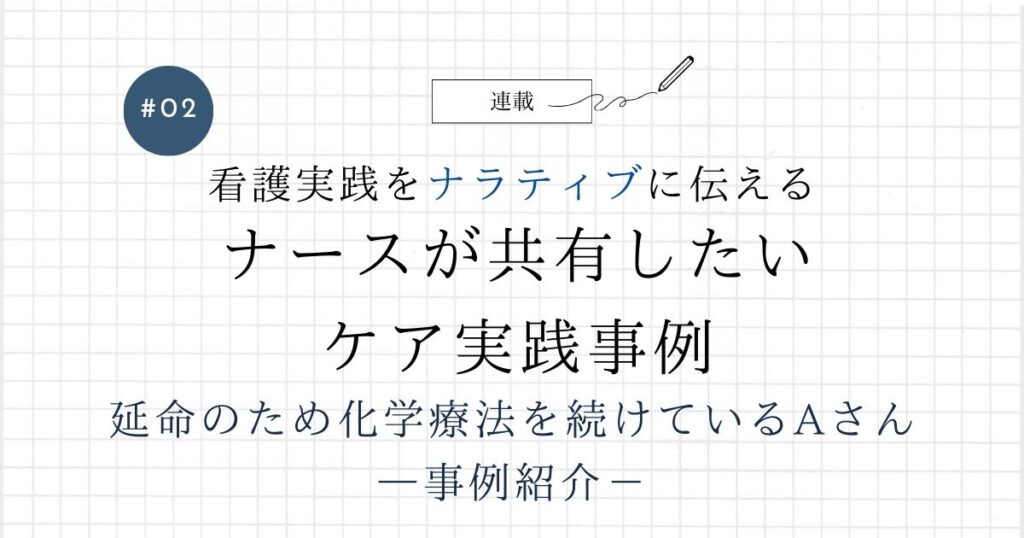事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は延命のための化学療法を続けている患者さんの事例を紹介します。
〈目次〉
延命のための化学療法を続けているAさんとの出会い
経過は順調ながらも冴えない表情
Aさんの表出する今の気がかり
診察同席により感じた“Aさんに必要な支え”
Aさんと共有した“最期”のイメージ
延命のための化学療法を続けているAさんとの出会い
60代の女性Aさんはある地方に住んでおり、S状結腸がんとイレウスと診断されて切除術を受けたのち、化学療法(mFOLFOX6+Bevacizumab〈ベバシズマブ〉)を7コース受けていました。
その後、関東に住む子どもたちの近くで過ごしながら治療することを望み、夫を残して単身、上京しました。
多発肝転移していたため、Panitumumab(パニツムマブ)単剤療法2コース施行後に、肝部分切除術を二度に分けて受けましたが、病勢は治まらずに多発肺転移がわかりました。
CVポートを造設し、化学療法(FOLFIRI+Panitumumab)2コース目のときに、私は外来の化学療法室でスタッフナースとしてAさんに出会いました。
経過は順調ながらも冴えない表情
お会いしたときのAさんには多発肝転移はありましたが、肝機能に問題はなく、ADLは自立しており、PS(パフォーマンスステイタス)はスコア0(まったく問題なく活動できる)でした。
治療室に入り、笑顔であいさつをした足取りの軽いAさんを見たときに、遠方から引っ越してきて治療を続けられているが、症状もない様子で、順調な経過だと思いました。
しかし、治療準備を整えて椅子に座ったAさんは、“手術や治療で少し痩せた”と穏やかな笑顔で静かに話しながら、やや肩を落とし、表情が冴えない様子でした。私は、Aさんの雰囲気が暗いことに気づきました。Aさんの病状が深刻なことから、死を強く意識するできごとがあったのではないかと思いました。
そしてAさんが病気や死とどのように向き合っているのか、また、どのような方なのかを理解してからかかわる必要性を感じ、Aさんの様子を観察しながら、前回の治療後の自宅での様子や生活についてうかがうようにして、Aさんへの理解を深めるとともに、話しやすい雰囲気作りと関係作りに配慮しました。
Aさんの表情の変化を感じながら、場の雰囲気が少し和んだところで、少し間を置いて、「今日は何か気になることでも?(あるのですか?)」とAさんの様子に合わせ、同調するよう配慮しながら問いかけました。 私は、治療のための点滴準備をしていましたが、視線と気持ちをAさんに向けて、Aさんが話し出すタイミングを待ちました。
Aさんの表出する今の気がかり
すると、Aさんは大きくうなずき、「あとどれくらい元気でいられるのか……って。あの、今日はいつもの先生と違っていて、その先生が“手術は意味がなかった”って。悪い状態は手術の前と一緒だって言われたんです……」「そうか、と思って……。今後のこともあるので、子どものこともあるし、あとどれくらい元気なのかなって思って」と静かに、暗い表情で語りました。
Aさんは、代診の医師に“肝臓を切除した手術に効果がなかった”という思いがけない悪い知らせを受けて落胆し、死を意識し、動揺していました。
その一方で、残される家族に想いを馳せて、予後について理解したうえで今後の生き方を考えていこうとしておられ、問題に焦点を当てたコーピング(対処方法)だと思いました。
私は、Aさんが代診の医師から受けた説明で落胆しているつらい気持ちに共感しながら、点滴準備の作業を一時止めて、「お子さんもいらっしゃるし、いろいろ考えますよね……」と応じました。
そして、「今の病状と今後の見通しについて、主治医の先生からお話を聞いてみたい、というお気持ちでしょうか?」と、予後告知の部分を含めた病状説明の希望についてうかがうと、Aさんはうなずき、「でもね、先生、いつも忙しそうだから……」と寂しそうな表情になりました。
私は、Aさんの希望があれば、診察の際に私が同席してAさんを支援できることを説明しました。すると、Aさんは驚きの表情を見せて「そういうこと、できるんですか? お願いしたいです」とうれしそうな表情になりました。
「それじゃ先生に聞いてみようかしら。私、じつは家族で大きな旅行を計画しているんですけど、どうでしょうか。家族が計画してくれたんです。最後になるかもしれないからって……」と話していました。私は、「素敵ですね。ぜひ先生に相談してみましょう」と応じ、旅行の計画を支持しました。
Aさんが旅行を「最後の旅行」と表現したことから、残された時間を考えて、死に向き合い、受け止めようとしていることを感じました。また、Aさんが家族に大切にされており、現状を共有できていると思いました。
診察同席により感じた“Aさんに必要な支え”
翌々週、事前に主治医に同席する了承を得ておき、私はAさんの診察に同席しました。
Aさんはためらいながらも、予後について主治医に質問することができ、医師から予後について「治療に効果があれば約1年半、治療が難しくなれば半年」という説明を受けました。Aさんは「そうですか……」と医師をしっかりと見つめながら納得したように返答したあと、家族旅行について相談し、許可を得ると、安堵していました。
診察を終えて外来治療室に移動すると、Aさんは家族旅行についてうれしそうに話したあと、表情を曇らせて沈黙し、「─ 最期ってどうなるのかなって思うんです。やっぱり苦しいんでしょうか。きっと動けなくなってくるだろうって思っているんですけど」「うちは90歳になる父も母も元気で、全然わからないんです。(死の)イメージがわかなくて」と話しました。
私は、死に関連した話をしてもよいタイミングだと感じ、「そうですよね。どうなるのかって思いますよね」と応じながら、人それぞれ最期の迎え方は異なるけれど、倦怠感が増したり、食欲が落ちてきたり、今までできていたことが少しずつできなくなって最期を迎えることを説明しました。
そして病状が進んでくると痛みが出てくることもあるけれど、今はとてもよい薬が出ており、痛みはコントロールできること。痛みだけでなく、体の不快なつらさや気持ちのつらさに対しては「サポートチーム」があり、専門的な支援を受けることで、楽になることを話しました。
また、最期のころは、Aさんが考えているように、思うように動けなくなり寝ている時間が長くなってくること、眠るように最期を迎える方が多いことなどを話しました。
Aさんと共有した“最期”のイメージ
Aさんは興味深い面持ちでうなずきながら、「そうなんですね。でもまだまだそんな時期が来るなんて思えなくて。こんなに元気なのにって思ってしまって」と話していました。
私は、死を受け入れることへの抵抗はプロセスとして自然であると考えながら、最期を迎える時期について、「電車に乗っていて、トンネルに入ったときに、出口の光が遠くに見えますよね。そして光が遠いので“まだまだ”と思っていたら、意外と早くて、すっと出口を出てしまう。 ─ 最期を迎えるまでのときって、そんなふうに、思ったよりも早いということがあるかもしません」と話すと、Aさんは「そうなんですね。あ~、そんなふうにね……」とうなずきながら納得する表情をしていました。
私は、Aさんが「死」を「最期」という言葉で表現していたことから、そのほうが話しやすいのではないかと考え、私もAさんに合わせて、「最期」という言葉を用いて話すように配慮しました。
Aさんは、その後も通院しながら、希望の家族旅行を叶えて治療を継続されています。
※この記事は『エキスパートナース』2016年1月号連載を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。