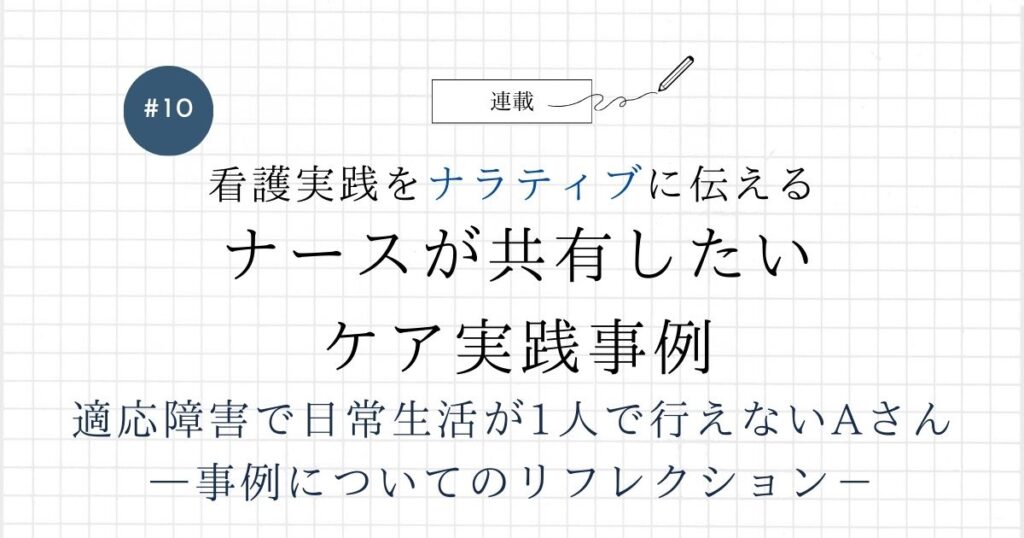事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は適応障害により、日常生活が1人で行えなかった患者さんの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第8回】適応障害でADLが低下した患者への看護介入
〈目次〉
患者さんの過去を振り返り、現状を正しく理解
これまでのアセスメントと異なる視点をもつリフレーミングの効果
事例についてのリフレクション
患者さんの過去を振り返り、現状を正しく理解
こころの病は、検査値などで明らかになるものではなく、生活する中にみることができます。
Aさんの抱えた適応障害*は、「ストレス因により引き起こされる情緒面や行動面の症状で、社会的機能が著しく障害されている状態」です。Aさんは、妹と母が亡くなり、1人で生活するようになったころから徐々に“不眠”“抑うつ気分”などの症状がみられていることから、原因となるストレスは、「身近な家族を失い、孤独な生活になったこと」だと考えられます。
それを契機に生じた不眠や抑うつ気分、活動性の低下は、適応障害の情動・行動面の症状です。アルバイトや家事をこなし、地域の人ともかかわることができていたAさんですが、そのような社会参加をして活動する機能もみられなくなっています。
これまでの経過を振り返ってみると、なぜこのような状態になったのかの見当はつきますが、この経過に気がつかなければ、現在の状態を正しく理解することが難しくなります。 正しく理解するためには、過去の情報を活用し、そのうえで今後の経過を予測立てることがポイントになります。
*執筆当時、『ICD-10(国際疾病分類第10版)』により、「適応障害」と診断された
これまでのアセスメントと異なる視点をもつリフレーミングの効果
この記事は会員限定記事です。