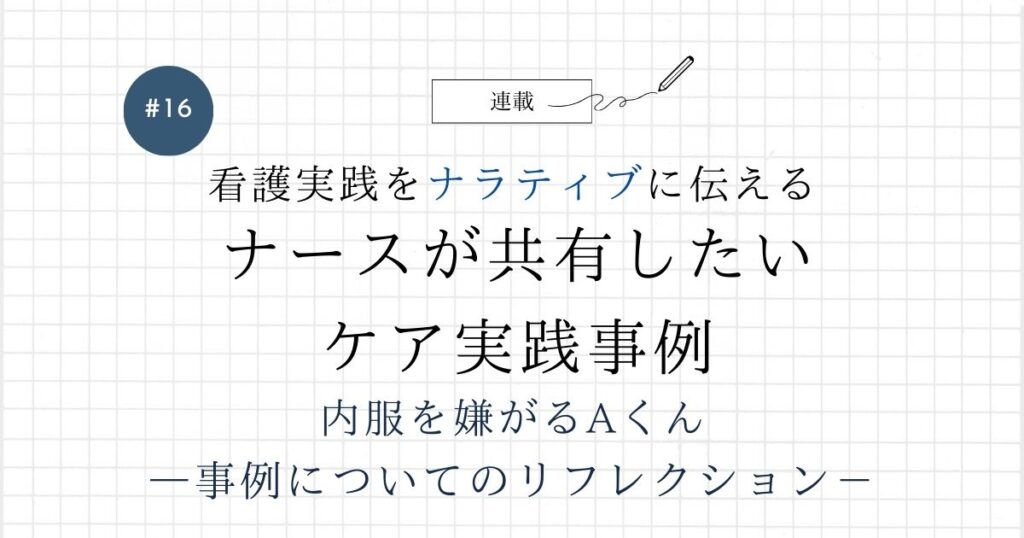事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は内服を嫌がる6歳の患者さんの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第14回】小児の服薬拒否への対応は?6歳児への看護介入
〈目次〉
Aくんを主人公にしたストーリーを立てて支援
治療する場を“成長できる場”に変えるための安全基地に
事例についてのリフレクション
Aくんを主人公にしたストーリーを立てて支援
神経芽細胞腫は、発症年齢や病期によりリスクが分かれます。低~中間リスクにおいては、7割以上が治るようになってきました。
しかし、その治療は年単位の長い期間を必要とし、苦痛を伴う処置が多いです。そのようなことを経験し大人になっていく子どもにとっては、治療中においても病気にならなかった子どもと同じように成長・発達していくことができるような支援が必要となります。
薬も飲まず、暴れるAくんは、大人からすると“困った”子どもです。ともすれば、大人の強い力で押さえて無理にでも内服させられたかもしれません。
杉澤さんは、大人が押さえる方法を考えるのではなく、「Aくんが内服する」という、Aくんを主人公としたストーリーを考え、展開していきました。Aくんを主体として考えると、6歳のAくんが彼なりに考えていることを理解する必要があります。
6歳児は、「過去の認識」「未来の感覚」という“時間の概念”の発達途上にあり、現在起こっていることを体験して理解していきます。
また、言語の理解はできても、自分が感じたことを正確な言葉で表すのが難しい段階にあり、言葉より実体験が中心です。
Aくんにとって“入院”という非日常的な環境は、まわりの大人が決めたことであり、彼には突然の変化です。付き添いをしていない環境であれば、両親とは面会時間だけしか会えなくなり、親から見放された感覚をもちやすくなります。
この記事は会員限定記事です。