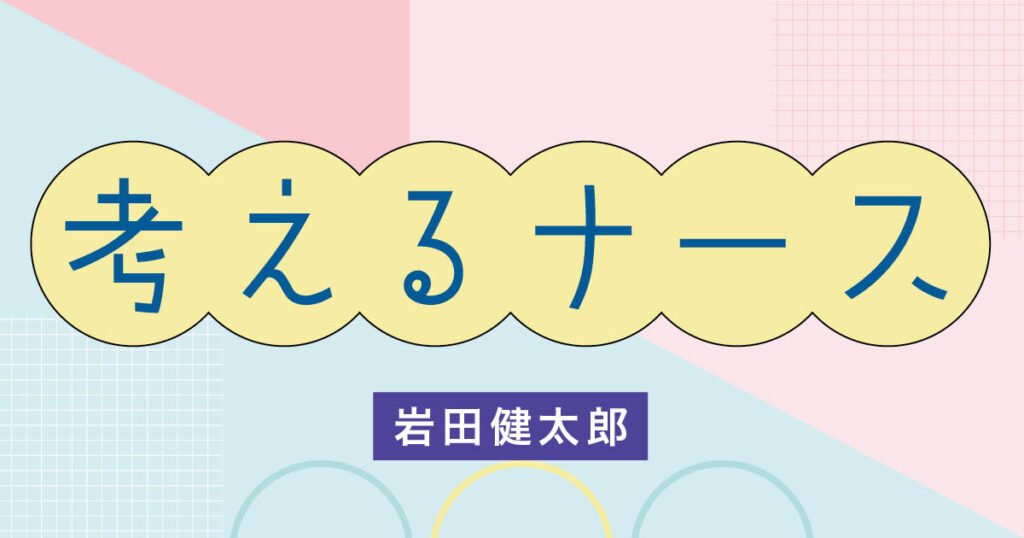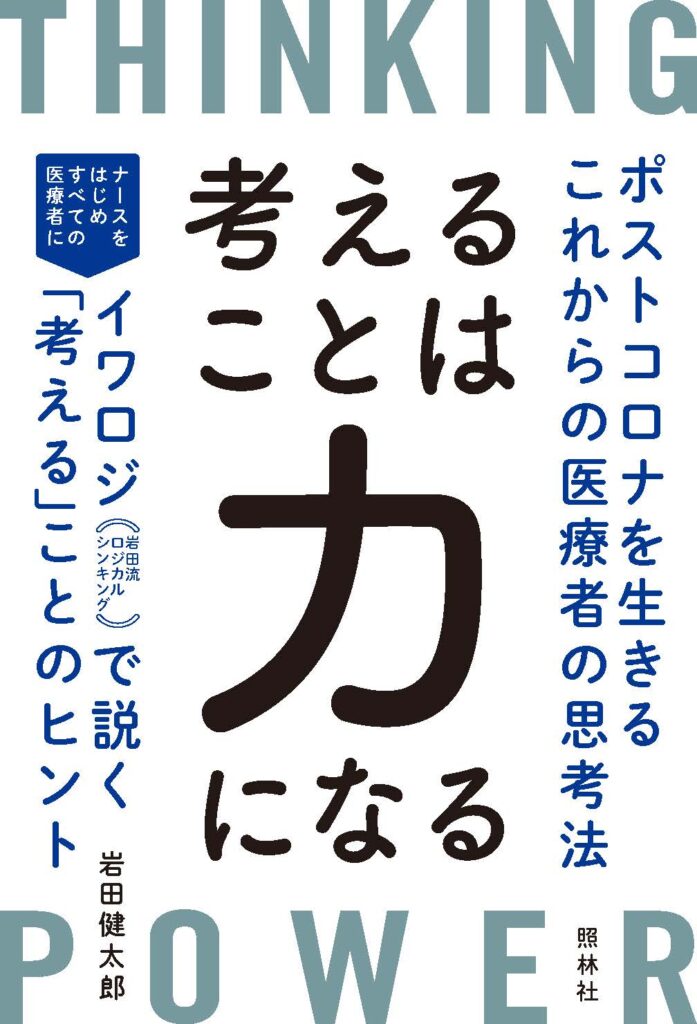岩田健太郎先生が「イワロジ(岩田流ロジカルシンキング)」で説く、「考える」ことのヒントとは。今回は、ロジカルな思考と、感情との関連性についてです。
*
一般に「ロジカル」という言葉には緻密さや論理的といったポジティブなイメージがついて回るとともに、「冷たい」「非人間的」といったネガティブなイメージもやはりついて回ります。でも、それはじつは間違いなんです。真にロジカルに考えるということは、とても感情に富み、感性豊かな行いなんですよ。
意識の4つの分類
ぼくは「意識」というものをよく4種類に分類してます。まあ、これも便宜的なというか、“便利的”な分類にすぎず、必ずしも学問的なものではないのかもしれませんが(役に立てば、それでいいんだ!)
1つ目は「起きてるか、寝てるか」の意識。難しくいうと「覚醒の度合い」です。あの、JCS(Japan Coma Scale)とかGCS(Glasgow Coma Scale)とかいうのは、この覚醒の度合いを「目が開くか」とか「痛み刺激に反応するか」みたいな方法で調べているんですね。“頭シャキーン”の度合いですね。
2つ目は「話が通じるか」。難しくいうと「見当識」です。こっちの言ってることをちゃんと理解できるか、の度合いを指します。ボオっとしていて寝起きの状態でもちゃんと話を理解できている人もいます。朝イチの看護学生とかはこんな感じかな?“頭シャキーン”だけど質問には見当違いな答えしか返ってこない人もいます。うちの研修医はこんな感じ?覚醒の度合いと見当識は一緒に上がったり下がったりもしますが、それぞれ独立していることもありますね~。
3つ目は情動(感情)の種類。「喜怒哀楽」ってやつです。ハッピー?アングリー?ハングリー?最後は関係ないか。
4つ目は情動(感情)の量。感情量というか、生きるエネルギーというか。感情量がやたら大きい、ちょっとうるさい人っていますよね。逆に、感情が表に出ない、感情量が少ない人もいます。この感情量や生きるエネルギーが極端に少なくなった状態が、いわゆる「うつ状態」です。
このように、意識は「覚醒度」「見当識」「感情の種類」「感情の量」の4つに分類すると、わりとスッキリします。今度、患者さんをみるときはこういう観点から観察してみると、いろいろと発見がありますよ。
ロジカルであるためには感情の量が必要
さて、ロジカルであるためには、当然覚醒している必要があります。もちろん、まっとうな見当識も必要です。感情の種類は……まあ、ケースバイケースかな。
しかし、感情の量、生きるエネルギーが小さいと、ロジカルでいることはとても難しいんです。
ロジカルでいるということは「上手に質問を重ねること」といいました。さて、質問をするのと、しないのとではどっちが楽かといいますと、これは「質問をしない」ほうが楽に決まっています。それ以上の努力、エネルギーは必要ありませんから。
しかし、質問し、さらに質問を重ね、納得いくまで突き詰めていくような探索的なものの考え方を続けるためには、かなりの精神的なエネルギー量を必要とします。いくら頭の回転の速い人でも、エネルギー量が十分になければ「もういいや」と投げてしまうんです。頭はいいのにロジカルでない人はとても多いですが、そういう人の多くがこういう「投げやりな」人たちです。
エネルギーは、別の言葉で言い換えるならば「意志の力」と呼んでもよいと思います。本当に問題の根っこはそこにあるのか、最後の最後まで吟味したい、という強い欲求の度合いです。誤解のないように申し上げておきますが、必ずしも大はしゃぎしなさい、と申しているわけではありません。静かに燃えるタイプのエネルギー量の大きさだってあるんです。
医療・医学・看護の世界に「100点満点」はありません。どんなにベストを尽くしたつもりでも、やはりまだ改善点は残ります。これ以上改善の余地のない医療・医学・看護などは存在せず、われわれは今もこれからも改善を重ねていくのです。「これで100点満点」と満足している人がいるとすれば、それは幻想的な自己満足にすぎません。
なので、「これでいいのか、本当にこれでいいのか?」と問い続ける(質問を重ねる)ことは、現状に満足せず、さらに改善を重ねていくために必要なエネルギーなのですね。それは「ロジカルにあり続けるために必要な燃料」と捉えてくださってもよいと思います。
※この記事は『考えることは力になる』(岩田健太郎著、照林社、2021年)を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。