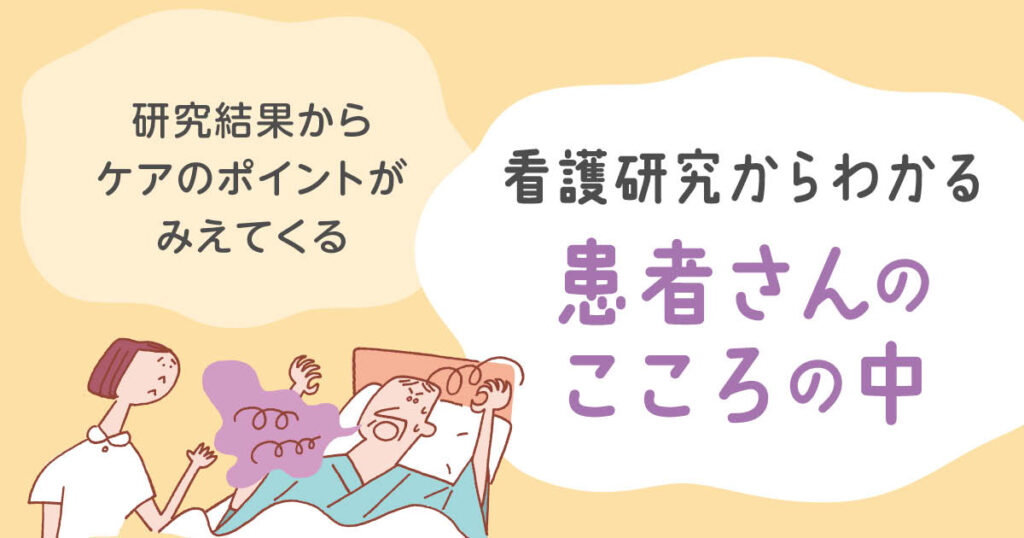回復過程における脳卒中患者さんは、落胆などの心理が回復に影響を与えていることが研究からわかりました。研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。
前回の記事:脳卒中患者の回復過程における落胆の原因は?【看護研究#5】
回復に影響を及ぼす要因を知り、患者さんを支える
●患者さんの落ち込みに対処するため、十分な見守りを行う
●患者さんの落ち込みの原因を鑑別するために、他職種との連携を行う
●身体的回復が停滞しても患者さんの心理面では変化があることを理解し、患者さんにもそれを伝える
「落胆」から回復を促すよう心理面の変化を伝えたり、患者さんどうしの交流を支える
脳卒中患者さんの回復過程に影響を及ぼす要因とそのケアを下記に示します。
脳卒中患者さんの回復過程に影響を及ぼす要因への対応1
「①了解不能」から「②障害の実感」移行の要因
●病状説明
●症状の悪化
●リハビリテーション開始
●ADL の失敗
【実践したいケア】
●「障害直面による落胆」(特に「ADL の失敗」による)に注意する
●フォローアップを十分に行う
●身体回復にあわせて心理面も変化していくことを伝える
「②障害の実感」から「③回復の喜び」移行の要因
●身体機能の改善感
●ADLの再獲得
●努力の報い
【実践したいケア】
●やればやるだけ身体面が回復するため、ベッドサイドでも可能なリハビリテーションをケアに取り入れる
●今後、身体面の回復が停滞することもあり得ることを、この時期にある程度予期的に伝えておく
「③回復の喜び」から「④プラスの感情とマイナスの感情の交錯」移行の要因
●回復の減速感
●回復の停滞感
【実践したいケア】
●身体面の回復が減速・停滞していても、少しでもよい変化を見つけ伝える
●「回復停滞による落胆」やうつ状態に陥りやすいため、心理面について十分にアセスメントする
「④プラスの感情とマイナスの感情の交錯」から「⑤人生の方向転換」移行の要因
●他の患者さんとの比較
●家族や医療者のサポート
●努力に対する満足感
【実践したいケア】
●周りと比較して自身の回復の遅れを悟り「落胆」に陥ることがあるため、患者さんが他の患者さんをどのように考えているかを見きわめる
●それに応じて患者さんどうしの交流を支える
(文献1を参考に作成)
1)脳卒中患者さんの「落胆」体験を回復の契機として支える
一時的に落ち込む局面である「落胆」は、従来、うつ状態に関する研究で多く取り上げられ、そこでは、主にリハビリテーションを妨げる大きなマイナス要因になるため、避けるべきものであるとされてきました。
しかしながら、本研究においては「障害直面による落胆」と「回復減速による落胆」から立ち直ったあとにもとの局面に戻るのでなく、「④プラスの感情とマイナスの感情の交錯」や「⑤人生の方向転換」という 新たな局面に移行することが認められました(【第5回】・図1)。
この記事は会員限定記事です。