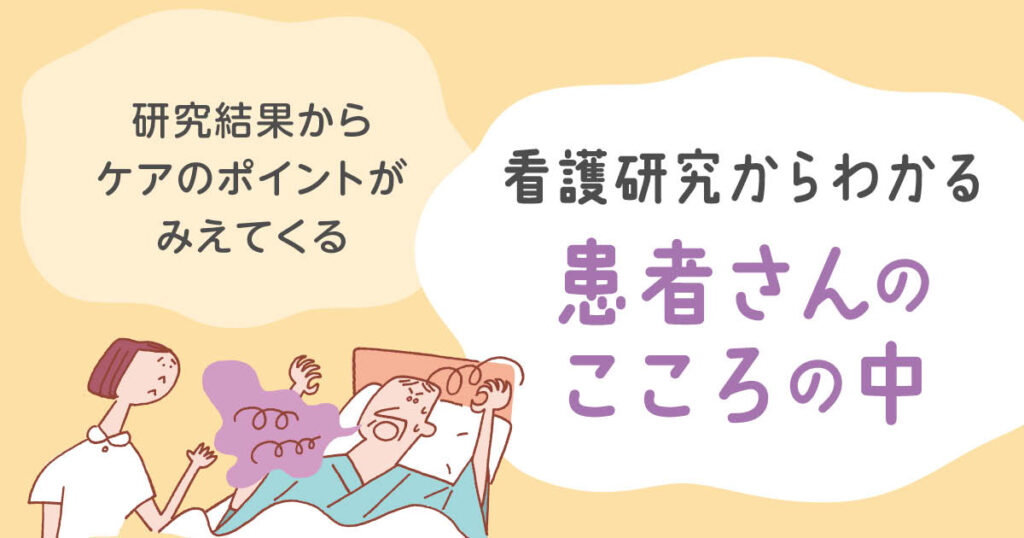咽頭全摘出の患者さんの心理についての研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。障害の早期受容と、新たなコミュニケーション習得に向けた看護支援が重要です。
前回の記事:喉頭全摘出による機能障害に伴う患者心理とは?【看護研究#13】
患者さんがボディイメージの変化や障害を早期に受容し、自信をもてるようにかかわる
●喉頭全摘出術に対する心の準備状態や、失声により十分な自己表現ができないことに対する精神的苦痛を理解する
●代用発声(電動式人工喉頭・食道発声)を含めたコミュニケーション方法に対するニーズを把握し情報提供する
●日常生活におけるセルフケア行動の促進を図る
障害の早期受容と、新たなコミュニケーション習得に向けた看護支援を行う
喉頭がんの患者さんが危機的状況に陥りやすい時期は、「Ⓐ喉頭全摘出術前」「Ⓑ喉頭全摘出術後」「Ⓒ退院後」いずれにも存在します。手術による危機的状況を克服し、早期に社会復帰するためには、術前から退院後までを通し、心理状態に応じた継続的な看護支援が必要です。
また、患者さんが早期に障害を受容し、生活を再構築するためには、家族の理解・協力を得て、患者・家族への段階的な看護支援を行うことが必要です。
喉頭全摘出術による危機的状況に陥りやすい時期と看護支援
喉頭全摘出術前:喉頭全摘出術を告知されたとき
患者さんの体験
●病名告知と声を失うことに対する二重のショックを受ける
●声を残したい気持ちと生への願いとの狭間で葛藤する
看護支援
●告知時から手術を意思決定するまでの患者さんの思い・気持ちを理解し寄り添う
●インフォームドコンセント後、術後の身体的変化、機能障害に対する患者さんの理解度を把握し、必要時わかりやすく説明する
●患者さんのニーズに応じて、術前あるいは術後に患者会に関する情報提供や参加を促す
喉頭全摘出術後:術後自分に何が起きているか認識したとき
患者さんの体験
●麻酔から覚醒し初めて声が出ない現実に直面し、失声を実感する
●永久気管孔造設による外見の変化や嗅覚等の機能障害を認識する
看護支援
●失声や永久気管孔造設の現実に直面した思い・気持ちを把握する
●筆談等によって十分に自己表現ができずに、意思伝達できないもどかしさに理解を示す
●患者さんの表情や反応、筆談の内容から訴える内容が伝達されたのか、ニーズや不都合の程度を把握する
退院後:入院という保護的環境から退院したとき
患者さんの体験
●退院後の生活における周囲の人々とのコミュニケーションに対する不安を抱く
●退院後、気管孔のトラブル発生時への対応が困難であることに不安を抱く
看護支援
●患者さんの代用発声(電動式人工喉頭・食道発声)に対する意欲や関心の程度を把握し、患者会への参加を促す
●入院中早期から患者さん・家族への日常生活行動に対する教育的かかわりをもつ
●日常生活におけるセルフケアに対する経験の強みから、日常生活行動に対する不安の軽減を図る
●病棟・外来間の連携を図る
1)喉頭全摘出術前・術後:喉頭全摘出術におけるボディイメージ変化の早期受容に向けた看護支援
①喉頭全摘出術による失声や機能障害における心の準備状態を把握する
患者さんは、「喉頭がんの告知」と「喉頭全摘出術に伴う失声などの障害」を余儀なくされるという二重のショックに苦悩し、「生きるためには仕方がないこと」と手術を受けることを意思決定しています。
この意思決定は、患者さん自身が術後の障害や身体的変化を価値づけし肯定的に受け止めることができるかを左右する、重要な過程です。 喉頭全摘出術の意思決定過程を含め、術後の失声や永久気管孔造設に伴う機能障害、また身体的変化をどのように受け止めているのか、心の準備状態の程度を詳細に把握することが必要です。
この記事は会員限定記事です。