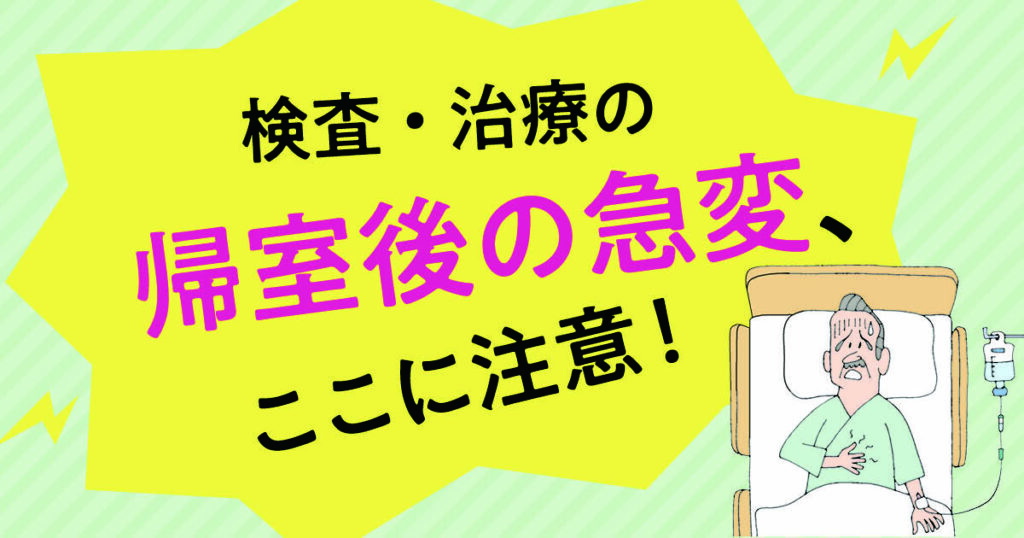検査・治療の帰室後の急変に注意!今回は、気管支鏡検査の目的、検査の流れ、検査の種類、帰室時の状態について解説します。
気管支鏡検査とは?肺がん、間質性肺炎といった病気を疑う場合に実施
気管支鏡検査とは、肺や気管支の病気を診断するための内視鏡検査、いわゆる肺カメラの検査です。気管支鏡の太さは約3~6mmくらいの細くてやわらかい管で、一般的な胃カメラより細くできています。 また、一番先端には小型のCCDカメラが搭載され、外部のモニタで口の中から気管支の中を見ることができる機器です。
気管支鏡検査は、消化管内視鏡検査に比べると侵襲性の高い検査といわれています。肺が呼吸を行うための器官であり、生命維持のための重要な器官だからです。
この検査が行われるのは、以下の場合があります。
- 肺がんや間質性肺炎、気管支炎、気管支拡張症、肺線維症、感染症などの病気を疑う場合
- 痰に血が混じる、痰がつまって息ができない場合
- 入れ歯などの異物を誤嚥した場合
- 食道がんや甲状腺がんの進行で気管浸潤が疑われる場合
ただし、60歳以上の患者では気管支鏡検査により心筋虚血が発生するリスクが高いとされており、心筋梗塞後6週間は検査を避けるほうが賢明です1。
位置や疾患によって検査の種類を選択
気管支鏡検査を行う患者は、胸部レントゲンにおいて異常陰影を指摘され、その後CTやMRI等にて何らかの呼吸器疾患が疑われる方や、他の疾患の治療・経過観察中に肺に何らかの異常がみられた方が多いです。胸部レントゲンの異常には、「腫瘤影」「結節影」「線状影」「網状影」があります(図1)。
この記事は会員限定記事です。