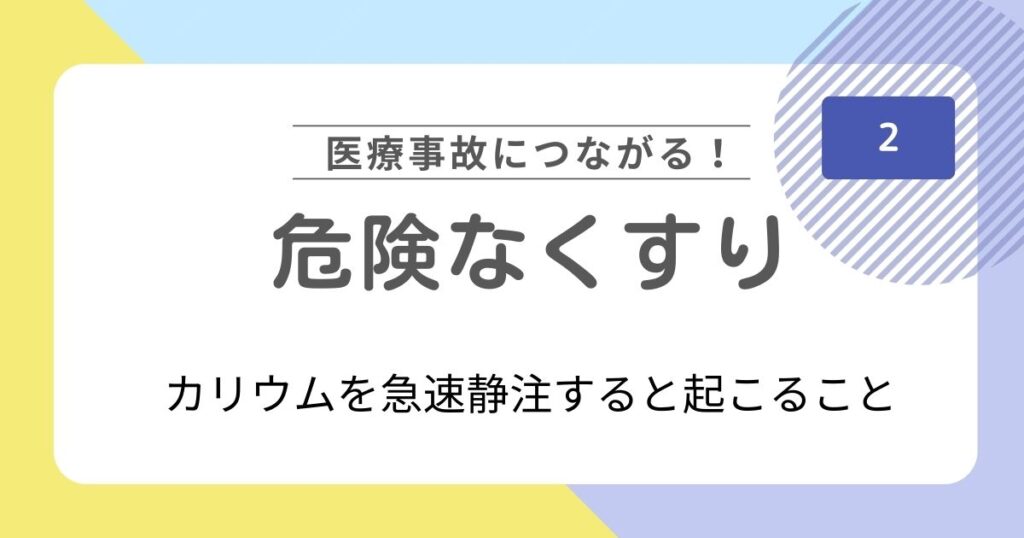医療事故につながる可能性のある危険な薬に注意!今回は、カリウム製剤を急速静注すると何が起こるのかを解説。不整脈や心停止につながる危険性を確認しましょう。
普段の経口摂取でのカリウムの量ならば危険でない
カリウムは野菜や果物などに多く含まれていて、健康のために十分量を摂取することが推奨されています。厚生労働省による『日本人の食事摂取基準(2020年版)』では、1日に摂取するべきカリウムの目安量として、18歳以上の女性で2,000mg、男性で2,500mg、目標量としては18歳以上の女性で2,600mg以上、男性で3,000mg以上とされています。
経口摂取されたカリウムは、主に小腸で吸収され細胞外液に入ります。腎機能が正常であれば、普段の食事からのカリウム摂取によって高カリウム血症をきたすことはなく、耐容上限量は設定されていません。
カリウムが多すぎると膜電位が不安定になり、不整脈や心停止につながる
添付文書に記載されている20mEq/時を超えて急速にカリウムが静注されると、たとえ腎機能が正常であったとしても高カリウム血症をきたします。
細胞外液でのカリウムイオン濃度が増加すると、細胞内外のイオンの濃度差が小さくなる結果、静止膜電位は浅くなります(図1)。静止膜電位が先に述べた閾膜電位(約-60mV)に近づくと、わずかな刺激で心筋の脱分極が始まる、すなわち興奮しやすく不安定な状態になります。
結果、無秩序な心筋収縮、不整脈が引き起こされます。さらにカリウムの濃度が高くなって、再分極で閾膜電位まで戻らなくなると、もはや活動電位は発生しなくなり、心停止に至ります。
この記事は会員限定記事です。