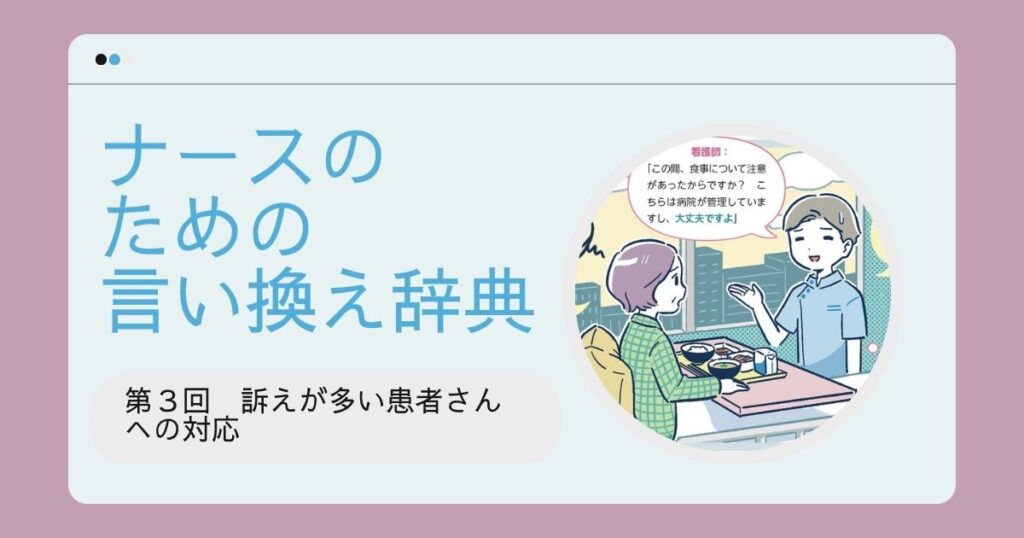さまざまな人と接する機会の多いナースが、円滑な関係構築のためにできる“ちょっとした言葉選びの工夫”を紹介します。今回は、訴えが多い患者さんへの対応です。
訴えが多い患者さんへの対応、どうする?

患者さんには「万が一〇〇になったら…」という不安がある
看護師のもつ情報に比べて、患者さんのもつ情報は圧倒的に少ないことが普通です。看護師が、症状などの経過を丁寧に観察・対応していても、患者さんは自分の経過が通常の範囲なのかがわかりません。不安が強い方ほど、事前に受けた説明との小さな違いに気づきやすくなります。
このようなときに一般的な説明を繰り返されたり、単に「大丈夫ですよ」と言われたりすると、「自分の個別の状況が正確に理解されてない」とむしろ不安が増してしまいます。
自分の気がかりを聴いてもらえなかった患者さんは、「理解不足が原因で、○○になったら大変だ」「自分がしっかりしなければ」と看護師へ不信感さえもつようになり、どんな小さな気がかりもすべて看護師に確認・訴えてくるかもしれません。
患者さん
「看護師さん!私、こういった料理は食べちゃいけないと思うんだけど」
看護師
「この間、食事について注意があったからですか?こちらは病院が管理しているので大丈夫ですよ」
患者さん
「……今後、こういったものは出してほしくないわ」
患者さんの思う“当たり前”と、病院の“当たり前”のズレが不満を招く
患者さんのこれまでの生活と病院生活との違いは、「治療上の制限」「ケアを行う人数」「病棟アメニティの質」などにもよりますが、通常、病院生活のほうが生活の質が低下して、不快さや不満をもちがちです。
看護師は、生活の質を「患者さんのこれまで」に合わせることはできません。このような“しかたがない”ことに不満を訴える患者さんにいらだち、“わがままな患者”として、患者さんの訴えを受け流してしまうことがあるかもしれません。
すると、訴えを受け流された患者さんは、「理解しようとしない」「自分がおかしいと気づきもしない」「社会の常識を知らない」などと、看護師への不満が増幅し、怒りにさえ発展してしまうこともあります。
患者さんの考えや気持ちを正確に知ろうとする言葉を選択する

不安のある患者さんに対しては、「痛みがいつまで続くのかご心配なんですね」など、相手の気持ちとその根拠となった考えを、言葉として相手に返して確認していきます。
考えと気持ちを共有できたら、「○○については、私たちもより注意して観察をしていきます」など、確認できた患者さんの考えに対してのみ、情報提供や対応を提案していきます。こうした対応をする看護師に、患者さんは「自分の状態を知ったうえで対応してくれているのだから、安心だ」と感じやすくなり、訴えが減ります。
患者さん
「看護師さん!私、こういった料理は食べちゃいけないと思うんだけど」
看護師
「この間、食事について注意がありましたので、ご心配ですよね。こちらは○○さん用に調整されているので召し上がれますよ」
不満のある患者さんにも同じように考えや気持ちを確認していきます。ただし、不満をもった患者さんの特別扱いや、問題行動への同意や許可は避けることが必要です。
例えば、他の患者さんに不満をもつ患者さんの「あのじいさん汚いから、洗面所使うなって言っておいた」などの発言へは、“考えや気持ちを言葉で伝える”ことのみを許容しますが、行動への同意や許可は避けます。
「嫌ですよね」という返事は意見への同意ともとられますが、「嫌だと思われたんですね」は同意にはなりません。そのうえで、「なぜ自分ががまん(他人と洗面所を共有すること)をしいられるんだ、と腹が立つ」「入院になって悔しい」などの不満の背景を具体化して共有します。こうすることで、不満による訴えは減るかもしれません。
※この記事は『エキスパートナース』2022年6月号連載を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。