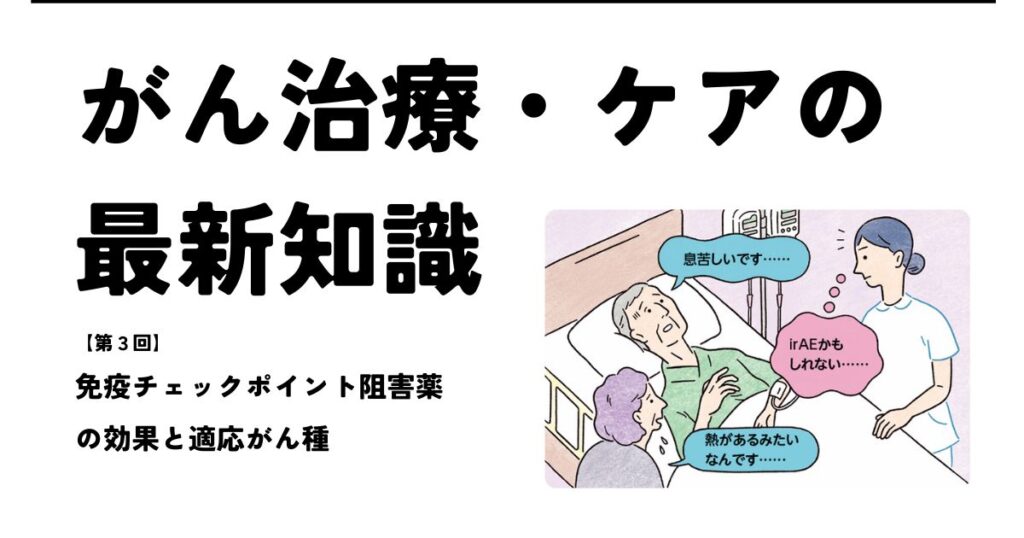がん治療・ケアの最新知識を紹介。今回は免疫チェックポイント阻害薬の効果や、保険適用となっている免疫チェックポイント阻害薬について解説します。
● 免疫チェックポイント阻害薬は、複数のがん種に効果が期待される(一方で、自然耐性を獲得
している腫瘍も多い)。
● 原発巣によらない、臓器横断的治療が注目を集めている。
がん種ごとにドライバー遺伝子(がんの発生・進行に直接のかかわりをもつ遺伝子)の変異は異なります。
そのため、これまではそれぞれ特異的ながん遺伝子タンパク阻害薬を用意する必要がありました。
対照的に、T-リンパ球は基本的に非自己であるすべての細胞を攻撃できるので、免疫チェックポイント阻害薬は原理的に複数のがん種にわたって効果を期待できます。
他方で、がん細胞が免疫反応を惹起する性質(免疫原性)や免疫回避の手段は、個々のがんによって大きく異なり、免疫チェックポイント阻害薬に対する自然耐性を獲得している腫瘍も多いです。
効果の指標となるバイオマーカーは、免疫チェックポイント阻害薬の開発当初から研究されてきました。現在臨床で使われているのは、次のようなものです。
臨床で使われているバイオマーカーの種類
全腫瘍細胞に対する、PD-L1陽性腫瘍細胞の割合
TPS(tumor proportion score)
または
TC(tumor cells scored as percentage of PD-L1-expressing tumor cells)
腫瘍領域に対する、PD-L1陽性腫瘍浸潤免疫細胞の割合
IC(tumor-infiltrating immune cells scored as percentage of tumor area)
全腫瘍細胞に対する、PD-L1陽性細胞(腫瘍細胞+リンパ球+マクロファージ)の割合
CPS(combined positive score)
腫瘍遺伝子変異量
TMB(tumor mutation burden)
この記事は会員限定記事です。