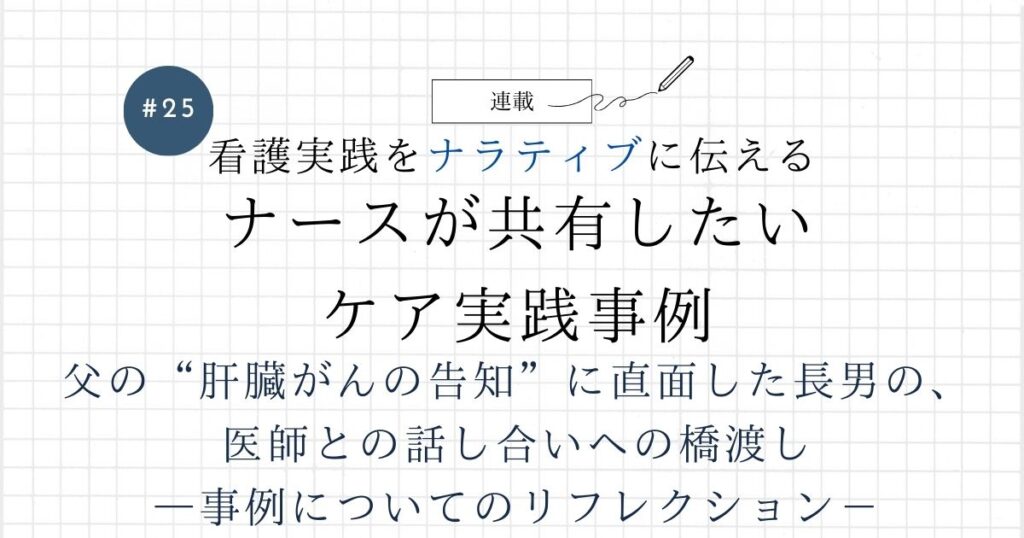事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は父の“肝臓がんの告知”に直面した長男の、医師との話し合いへの橋渡しの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第23回】肝臓がんの告知に直面した家族への意思決定支援
〈目次〉
反応・感情を“適切に”受け止めたい
看護者としての倫理に配慮しながら実践することの重要性
事例についてのリフレクション
反応・感情を“適切に”受け止めたい
患者や家族のさまざまな反応や感情を受け止めることは、私たち看護師の日常の重要な業務の一部です。
しかし、その反応や感情の意味の解釈は容易ではなく、看護師としてどのように受け止めることができるのか、受け止めることに意味があるのかと、忙しい業務の中でとまどうことがあるのではないでしょうか。
患者や家族の反応や感情の意味について、看護師として、また看護チームとしてわかっていなければ、看護師が責められるような理不尽さや、理解力のない人だとか、変わった性格の人だと、対象へのレッテル貼りにつながってします。
そのことで看護ケアが滞り、患者や家族の気持ちのねじれは複雑になり、医療者との関係性もこじれ、患者や家族にとっての困難さの増強につながりかねません。
看護者としての倫理に配慮しながら実践することの重要性
日本看護協会の『看護職の倫理綱領』の〈条文6〉に「看護者は、対象となる人々に不利益や危害が生じているときは、人々を保護し安全を確保する」1とあります。今回提示いただいたAさんは、悲しみや怒りを表現されていました。
致命的な診断を受けることによる父親へのダメージを緩衝し守ろうとする家族としての役割や、体力の衰えはあるものの継続している父親との生活のイメージが途絶え先行きの見通しが立たなくなったことなど、当然の気持ちの反応であったと思います。
この記事は会員限定記事です。