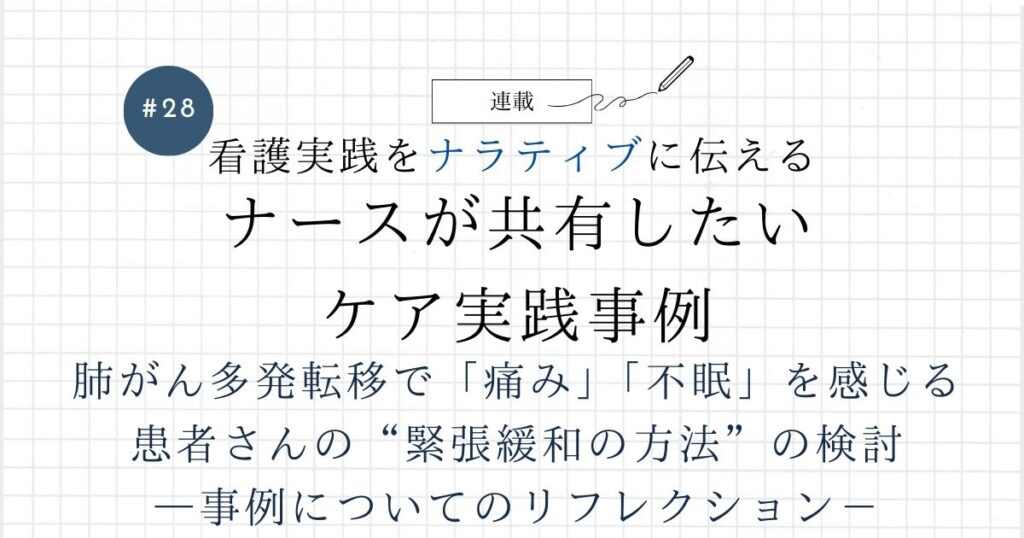事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は肺がん多発転移で「痛み」「不眠」を感じる患者さんの“緊張緩和の方法”の検討を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第26回】肺がん多発転移による痛みと不眠に苦しむ患者への緊張緩和ケア
〈目次〉
因果関係は円環的。1つに理由を求めない
要因を「なぜ?」「どうして?」と考えケアに活かす
事例についてのリフレクション
因果関係は円環的。1つに理由を求めない
私たちの今ある“心の在(あ)りよう”は、ある1つの原因や理由で成り立っているわけではありません。「不安だな」と感じるときも、目の前にはっきりとわかるストレス源のみを理由にしがちですが、理由は本当にそれだけなのでしょうか?
瀬尾さんが取り組んでいるリエゾン精神看護では、原因→結果と考えていくのではなく、原因が結果を生み、生じた結果が原因となってまた別の結果を生み出すという“円環的な因果関係”を見きわめ、アセスメントしています。
今回の事例のAさんは、左肺腫瘍と診断され、多発性骨転移もある状態で、疼痛があり、また同時に気分の落ち込みが見られた方でした。ここだけで考えれば、「継続した疼痛による抑うつ」と考えると思います。
しかしここで瀬尾さんは、原因→結果だけでなく、円環的な因果関係を見きわめるために、Aさんに会い、くわしく話を聞いています。
そして瀬尾さんは、単に「疼痛による抑うつ」ではなく、疼痛コントロールが不十分で不眠が続いた、それによる心身のエネルギーの低下と自己コントロール感の低下によって、生活する意欲・能動性の低下や抑うつ気分を呈した状態と判断しています。
また、この痛みや不眠の苦悩が意欲低下や抑うつに影響されて医療者と共有されなかったために、孤独感が生まれ、またその孤独感が不安を強め、さらなる不眠や疼痛につながっていると見きわめています。
要因を「なぜ?」「どうして?」と考えケアに活かす
さらに瀬尾さんは、このようにAさんが置かれている状況にある円環的な因果関係を考えながら、その中で看護がかかわれる部分を見つけだしました。
この記事は会員限定記事です。