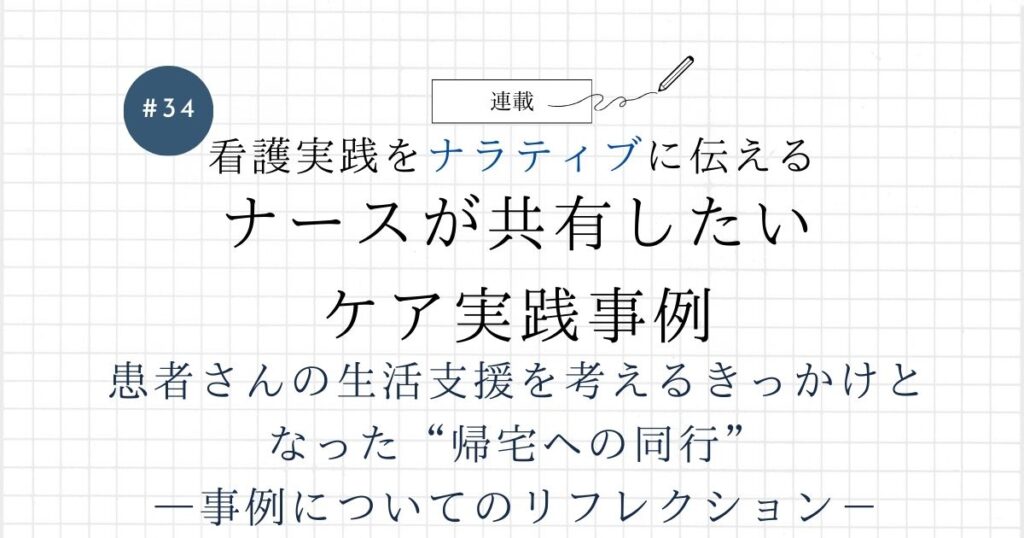事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は患者さんの生活支援を考えるきっかけとなった“帰宅への同行”の事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第32回】外来患者の帰宅同行を通じて見えた在宅支援の課題
〈目次〉
患者さんの“地域で生活すること”に興味を向ける重要性
個々人のもつ、生活する力を信じてみよう
事例についてのリフレクション
患者さんの“地域で生活すること”に興味を向ける重要性
今回、山元さんは1人暮らしの認知症のAさんへの、アウトリーチ(訪問活動)による支援を行いました。高齢化の進展により、病棟や外来では日常的に認知症高齢者に対応するようになりました。
「認知症で1人暮らし」と聞けば、「介護保険サービスは受けているのか?」「早くケアマネジャーと連携しなくちゃ」と思う読者の方も多いでしょう。
ここで気を付けたいのは、単にサービスをあてがうだけになっていないか、ということです。当事者がどのように暮らしたいと思っているのか、どんな強みをもっているのかという視点を忘れないでいたいものです。山元さんのケアは、改めてその大切さを教えてくれているように思います。
山元さんが行ったような病院や施設からのアウトリーチも増えてきました。また、地域で認知症の人を支える仕組みも整いつつあり、住民の意識も認知症の人と共生する方向に少しずつ変化してきています。 自分が働いている地域や住んでいる地域で行われている認知症の人を支えるさまざまな活動にも、目を向けてみませんか。
個々人のもつ、生活する力を信じてみよう
この事例では、山元さんがAさんの帰宅に同行したことで、さまざまなことがわかり、解決に向かいました。持ちものや家の様子から認知症の診断・治療に結びついたこと、訪問看護や配食サービスの導入やかかりつけ医の変更によって健康管理体制が整ったことなど、フォーマルな支援が受けられるようになりました。
一方で、山元さんが【第33回】で説明している“つなぎの役割”ですが、これはフォーマルな支援に連携すればよいということでも、ただ院外に足を運べばよいサービスにつながるということでもありません。
この記事は会員限定記事です。