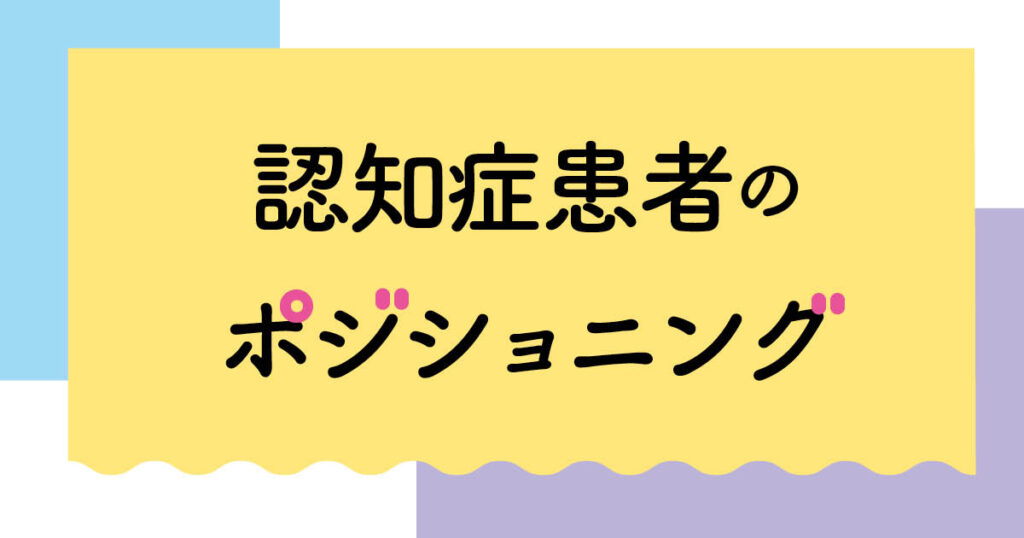「おむつ交換のときに抵抗する」「移乗のときにスムーズにいかない」など、認知症の患者さんへのケアに関して悩んでいませんか。適切なポジショニングを紹介する、全9回の連載です。
【第1回】ベッド上姿勢
円背や下肢屈曲の姿勢をとりやすい高齢患者が臥位となると、殿部・踵部周囲に重さが集中。体圧分散のために気をつけたいポイントを解説します。
●「ベッド上~車いすへの乗車」までの一連のケア場面について解説
●ベッド上姿勢のポジショニング
●高齢患者は殿部・踵部に重さが集中してしまう
●広い面積で重さを受けられるようにクッションを活用
【第2回】寝返りの介助
側臥位への寝返りの際、肩甲帯と骨盤帯をゴロンと回転させる方法では患者さんが怖がってしまいます。適切な寝返り介助の方法だと、高頻度で質の高いリハビリテーションにもなりえます。
●左右へ転がされると患者さんは怖がってしまう
●体幹のひねりをアシストして介助
【第3回】起き上がりの介助
V字で抱え上げると、患者さんのすべての重さが介助者にかかって負担に。この方法を続けると、患者さんの反り返った不良な座位姿勢が強まり、移乗がしにくく、生活全般に制限が生じます。
●V字で抱え上げると、介助者に腰痛や腱鞘炎の危険も
●側臥位にしてから下肢をおろす
【第4回】立ち上がり・車いすへの移乗の介助
人はおじき動作により、立ち上がることができます。しかし、患者さんの両膝の間に割り入ってから立ち上がりを介助すると、おじぎ動作をじゃましてしまいます。適切な介助法とは?
●おじぎ動作をじゃまするのはNG
●患者さんに合わせて重心移動を行う
【第5回】ポジショニング・移乗のギモン①
ポジショニング・移乗に関するギモンを取り上げています。患者さんが怖がったり、緊張したりしていないか、患者さんにとって安楽かどうか、気をつけるようにしましょう。
Q.移動の際に、 柵をつかんだままなかなか手を離してくれない場合のコツは?
Q.ポジショニングしてもすぐに体をずらしてしまうなど、良肢位を保持できない場合に、車いすの選択以外にできることは?
【第6回】車いすでの姿勢の調整
殿部が前方へずれると、体幹や頸部が後方へ反り返った不良姿勢(すべり座り)になりやすいため注意。褥瘡発生リスクが高まり、拘縮の原因にもなります。
●拘縮の原因にもなるすべり座りに注意
●左右交互に重心移動させて深く座ってもらう
【第7回】リクライニング型車いすとティルト・リクライニング型車いす
リクライニング型車いすでは、身体が下方・前方へすべり落ちやすい場合があります。アームサポートをつかんで離さない患者さんは、安定の状態を求めているのかもしれません。
●リクライニング型車いすでのずり落ちに注意
●ティルト・リクライニング型車いすは座面の後方へ傾斜可能
【第8回】ポジショニング・移乗のギモン②
正しい移乗のやり方を広めるには?とのギモンに答えています。有効なのは体験型学習の場を設けること。チーム全体のケア能力を高めるために、できることから始めてみては。
Q.正しい移乗のやり方を職場の人にも伝えたいのですが、どうしたら理解してもらいやすい?
【最終回】不適切なケアがもたらす影響
ケア従事者が困り果てるほどの抵抗や緊張を示す患者さんには、二次的障害が起こっているかもしれません。患者さんに安心を与えられるケアのありかたを考えてみませんか。
●「認知症が進行している」と感じるとき、問題がケアにあるのではないかと考えてみる
●「業務」に、患者さんが安心できるサポートは含まれている?