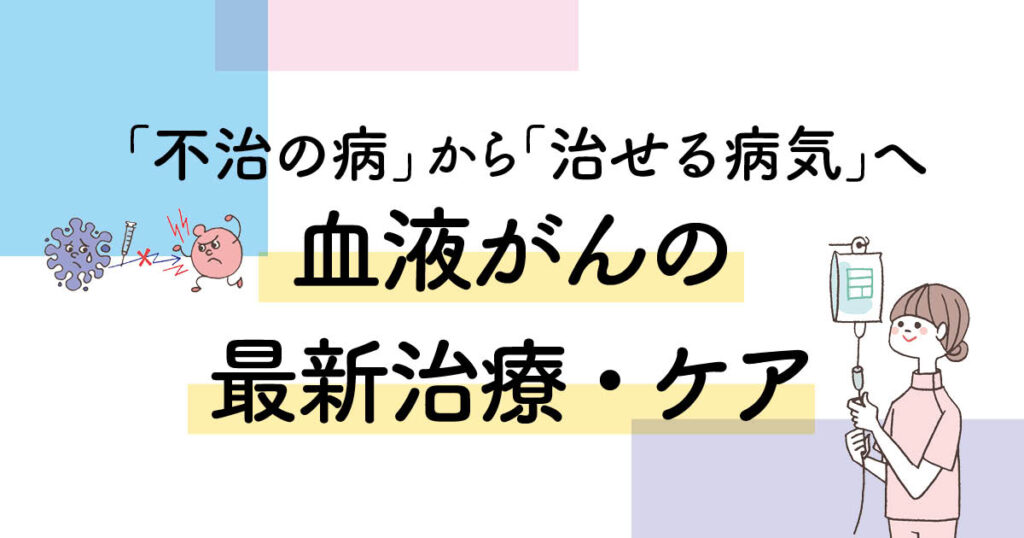白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、血液がんの最新の治療・ケアについて解説。今回は造血幹細胞移植治療中の食事を取り上げます。「大量調理施設衛生管理マニュアル」や食品選択のポイントを紹介します。
「大量調理施設衛生管理マニュアル」に則った食事に
移植治療の食事は、
①食品・食事由来の感染を防ぐこと
②医薬品との交互作用
を念頭に置いた食事が提供されます。従来から「煮沸食」や「無菌食」と呼ばれていた移植治療の食事は、すべての調理済食品を袋に詰めて食器ごと再加熱するなど、徹底的な無菌化を行っていたため、見た目、味、内容ともに嗜好性が低く、有害事象や治療環境下で食事摂取量が低下しがちな移植患者の栄養状態の維持には問題となっていました。
日本造血細胞移植学会のガイドライン1では、病院食等の1日750食以上提供する施設では、HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)という考えに基づいた「大量調理施設衛生管理マニュアル」2に従った食事が提供されていれば、移植治療の患者さんにも安全であると記載されています。
HACPPとは、食品製造工程上の食中毒菌汚染や異物混入などの危険要因を分析・把握し、それらの危険要因を除去または低減させるために、最も重要な工程を管理することで、食品の安全性を確保する管理手法です。
国内の病院などの施設では、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿った衛生管理が基本となっているため、医薬品との相互作用や細菌汚染の問題が残る食材を除けば、基本的には通常の病院給食と変わりのない食事を提供してよいといえます。
実際には、ガイドラインそのままではなく、施設ごとの運営上のルールが加わりますが、それでもすべての食事を再加熱して提供していた従来の食事に比べて改善されてきているといえるでしょう。
移植治療時の食品の選択のポイント
それでは、具体的に移植治療時の食品の選択のポイントを紹介します。
●賞味期限・消費期限内のものでも、冷凍・冷蔵等表示された適正な保管方法のものを選択する。
●外食の際や調理済み食品を選択する際は、調理製造過程と保管状態の安全性が確認できるものを選択する。
●食肉類・魚介類・卵の生食は禁止する。
●生野菜は、生産・収穫・搬送・保管・調理などの途上で、動物の糞尿による汚染・土壌中の真菌付着・腸管出血性大腸菌等で汚染された水、ノロウイルス・サルモネラなどによる食品汚染の可能性があるため、次亜塩素酸ナトリウム(100ppm)に10分浸漬後に飲料に適した水での流水洗浄後、皮をむくか加熱調理を行う。
この記事は会員限定記事です。