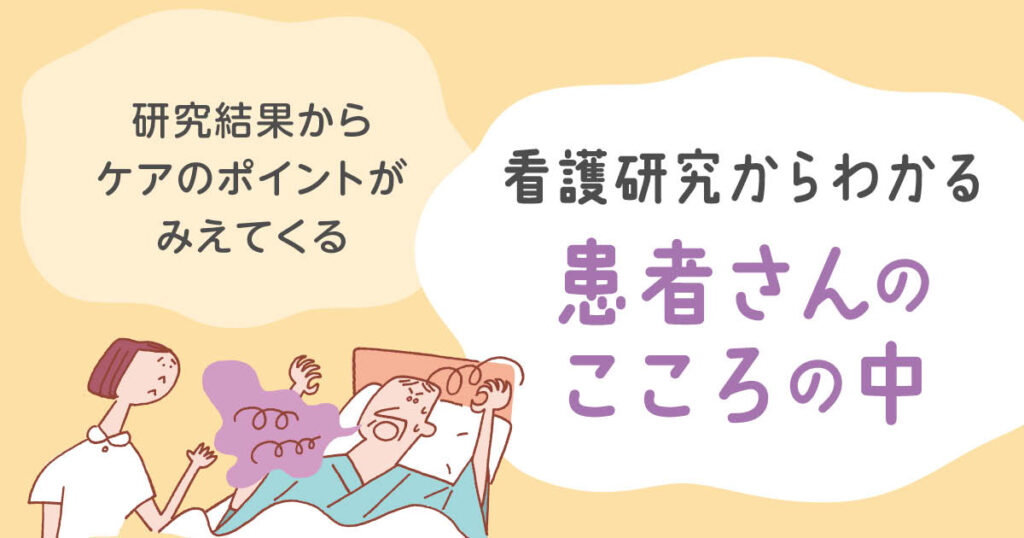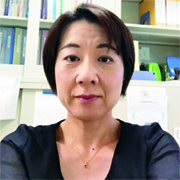重症外傷患者さんは、衝撃や苦痛を思うように制御できているという「コントロール感」をもっています。前回の研究結果をもとに、コントロール感を支えるために実践したいケアを紹介します。
前回の記事:重症外傷患者の回復過程における心理的変化とは?【看護研究#17】
回復過程に応じて、コントロール感を維持したり高めたりできるようにかかわる
●事故直後は、患者さんが自分の思いを伝えられないことを理解する
●患者さんが自分でできることは、可能な限り自分で行えるよう、忍耐強く見守る
●患者さんが傷つきやすいことを気に留めながら、回復を見守る
患者さんが自分の思いを伝えられないことを理解し、コントロール感を支える
患者さんの社会復帰を妨げているのは、事故の衝撃や、身体の一部または機能の喪失、さらには救命のために行われる侵襲的な治療の体験が引き金となって、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを生じた結果、コントロール感が低下し、病的な恐怖や不安、抑うつが発生するためです。
患者さんが自身のコントロール感を維持したり高めたりするために、看護師ができるケアとして以下が挙げられます。
表1 重症外傷患者さんのコントロール感とそれを支える看護支援のポイント2
①苦痛や恐怖から逃れる
●声に出せない思いや欲求の表出を助ける
・表情や呼吸様式などから苦痛を読み取り、「○○が痛くはありませんか?」「息苦しいですか?」などの質問をして、思いを確認する
●脅威となっている痛みや息苦しさが緩和されるようにする
・苦痛を代弁して、医師に伝える
・深呼吸を促すなど、そばについて不安を和らげる
②大切な人との絆を支えに現実に向き合う
●緊急事態について、すみやかに大切な人に伝達する
・この状況を伝えたい相手がいるかを尋ねたり、家族が病院に向かっている等の情報を伝えたりする
●自分の居場所や日時がわかるような工夫をする
・カレンダーや時計を患者さんから見える場所に置き、昼夜の区別がつくよう病室の照明やレイアウトを検討する
・新聞やテレビ、ラジオなど世の中の情報に触れられるようにする
③援助者に体を委ねて現実を傍観する
●責任をもってケアを提供しているという姿勢を示す
・その日の受け持ち看護師やケアに入る看護師は、必ず名前を名乗り、自分が行うことを伝えてから実施する
●体の変調に備えながら、細心の注意を払ってケアする
・ケア中に、循環変動を生じることや、体位を変えることで痛みを生じることを想定し、表情やバ
イタルサインの変化をモニタリングしながらケアを行う
④腰を据えてできごとを振り返り整理する
●そこがその人の居場所であることに配慮する
・カーテンレールで区切られた範囲はその人のパーソナルスペースであることを認識し、声をかけてからカーテンを開け、そこに入るようにする
●脅威となりうるものを患者さんから遠ざける
・痛みや恐怖を連想するような治療機器が、むやみに患者さんの視野に入らないよう配置を考慮する
・脅威となる物言いをする可能性のある家族、面会者、医療者の入室制限や、入室時の立ち会いをする
●欲している情報を繰り返していねいに伝える
・事故に遭った患者さんなどには、傷がいまどんな状況なのか、昨日医師から説明された内容はどんなことだったかなど、ニーズに応じて何度でも説明する
●聞くことの心の準備ができるまで情報を留め置きする
・衝撃的な事実(例えば、救命のために身体の一部を喪失していることなど)は、患者さんが聞くことのできる心理準備状態になってから段階的に伝える
⑤自らに課された仕事をこなす
●意思表示のサインにすみやかに反応する
・遠慮して口に出せない欲求を、表情やしぐさから先読みし、確認する
●安易に手を貸さないで根気強く見守る
・車椅子への移乗などは、できるだけ自力で行ってもらう
●1人の人間として関心をもち、よき話し相手になる
・趣味や関心事など、その人個人が関心をもっていることから共通の話題を見つけて対話する
●課題をこなすことで、期待できる成果を示す
・傷の治療やリハビリなど、それらが完了したときの成果を説明し、イメージがもてるようにする
●心地よさをもたらすケアを提供する
・清潔ケアやマッサージなどを、“癒し”となるよう意識して実施する
●納得できるまで医師とやりとりできる機会や場を調整する
・治療方法の選択や、現在の状況説明など、医師との対話ができるように場所と時間の設定をしたり、患者さんの聞きたいことを代弁したりする
この記事は会員限定記事です。