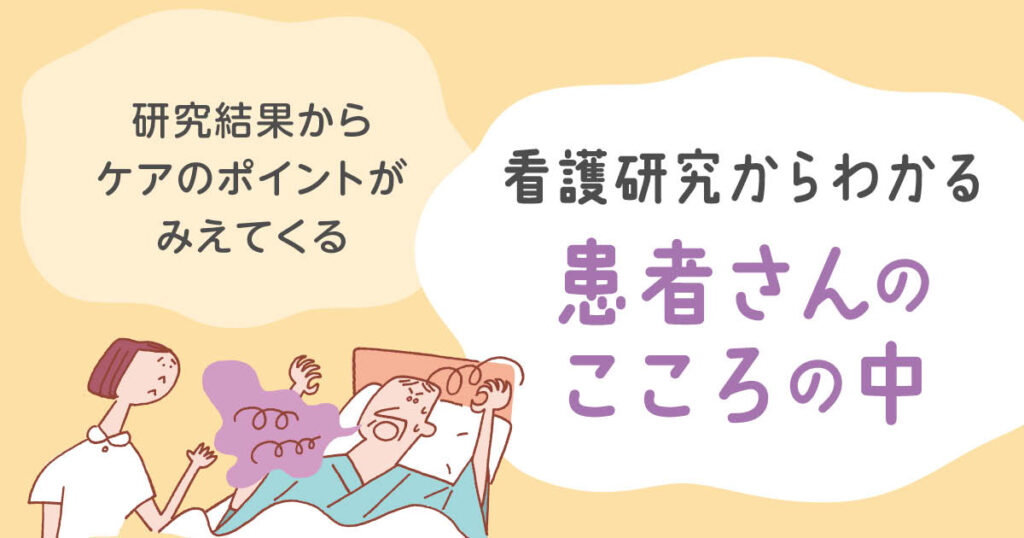患者さんの体験・心理についての「研究」を原著者に紹介してもらい、臨床で活用したいこころのケアを探っていくシリーズ企画。今回は、レビー小体型認知症の患者さんの心理についての研究結果をもとに、実践したいケアを紹介します。
前回の記事:レビー小体型認知症の症状と病気受容のプロセス【看護研究#25】
患者さん自身に疾患による変化を尋ね、思いを知る
●ふだんの患者さんの状態をよく観察し、変化の状態に合わせてかかわる
●幻視に対する思いや、周りの家族・医療者がどうすべきかを患者さんに直接尋ねる
●患者さんへの確認は、患者さんの状態がよいときに行う
レビー小体型認知症とは?突然の会話・歩行の症状と幻視に対して、患者さん自身の思いを理解する
レビー小体型認知症は、日本人の小阪憲司医師が発見し、2014年に世界で初の治療薬(アリセプト®)が日本で認可された疾患です。進行性の認知機能障害を必須症状とし、認知機能変動、幻視、パーキンソニズム、REM(レム)睡眠行動障害など、他の認知症にはあまり見られない症状が出現する特徴があります。
つまり、認知症=もの忘れという先入観ではレビー小体型患者さんの苦痛や困りごとを見逃す可能性があります。
【第25回】・表1の内容は、レビー小体型認知症患者さんが抱えておられる困難や思いのごく一部ではありますが、まずはこれらの困難や思いに対してのケアを考えます。
レビー小体型認知症患者さんへのケア
①今の意識・身体状態をつねに把握しながら必要な援助を行い、事故を防ぐ
<具体的な支援>
● 患者さんのふだんを知る
・コミュニケーション能力
・日常生活動作能力
・手段的日常生活動作能力
・出現している症状
●ふだんとの違いを把握する
●状態の変化に合わせて、援助方法を変える
●突然起こる転倒を予測してかかわる
・血圧測定
・意識レベル
・移動前後(離床、排泄、入浴など)に状態を確認
●状態の変化についての自覚や思いを把握し、できることを引き出す
②幻視の影響を把握し、幻視が見えたとしても落ち着いて過ごせるよう、薬の効果のアセスメントや環境調整を行う
<具体的な支援>
●幻視による影響をアセスメントする
●幻視が消える工夫をする
・一緒に触ってみる
・ケアする人が触ってみる
・部屋を明るくする、幻視を引き起こしているものがあれば、それを除去するなどの環境整備
●薬物治療
・専門医の診察を受け、正しい処方を受ける
・薬の副作用の出現状況を把握する
●精神状態が落ち着いている・認知機能がよい状態のときに、幻視について聴いてみる
・どのように見えているのか
・そのときどのような気持ちになっているのか
・周りの者はどのように支援すればよいか
この記事は会員限定記事です。