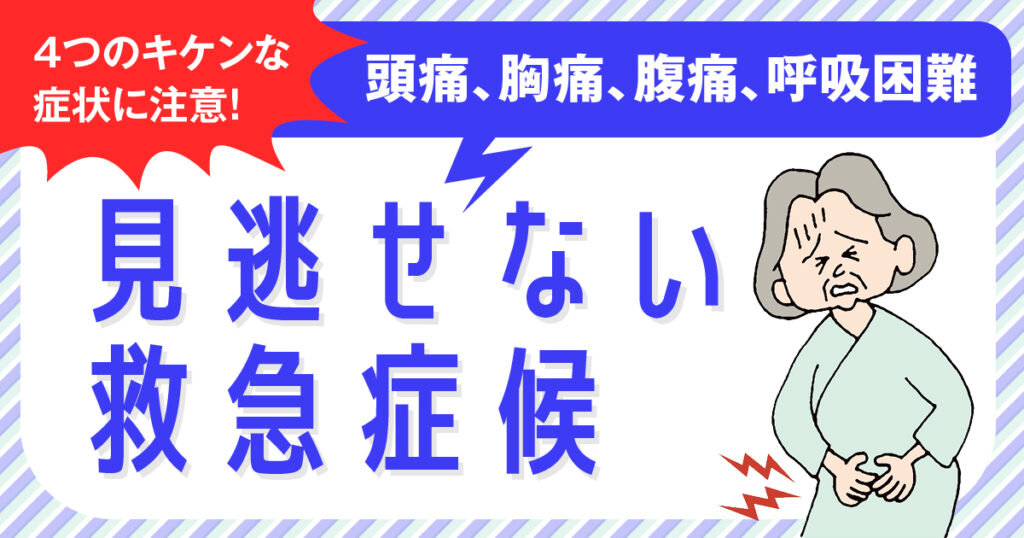患者さんの訴えから重大な疾患を見きわめて、すぐに対応するには?今回は頭痛の訴えがあったときの対応や、髄膜刺激症状のスクリーニング検査について解説します。また、頭蓋内圧亢進症状にも注意が必要です。
●くも膜下出血
●脳出血
●髄膜炎
●脳梗塞
頭痛の訴えがあれば、まずはバイタルサインとABCD の評価
【第1回】の通り、どのような症状であっても、まず①第一印象の把握、②ABCD 評価(A:気道、B:呼吸、C:循環、D:意識・中枢神経)から「緊急度判断」を行います。
ABCDの異常があれば、すぐに「バイタルサイン」を測定し、「ABC の確保」をする必要があります。そして、医師が来院した際に、迅速に二次救命処置が実施できるよう準備を進めます。
頭蓋内病変、頭蓋外病変に注意
同時に、患者さんの訴えから考えられる疾患を想定しながら原因検索を行います。
頭痛を訴える患者さんで見逃してはならないのは、頭蓋内病変(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞、髄膜炎)、頭蓋外病変(側頭動脈炎、緑内障)です。基本的なアセスメントの流れと使用する評価法を示します1-2。
頭痛の訴えがあったときのアセスメントの流れ
1 問診で病状や病歴等を確認する
●SAMPLE(表1)、OPQRSTT(表2)に沿って漏れなく情報を集めましょう。
表1 SAMPLE
S:Symptoms(症状〈主訴〉)
A:Allergy(アレルギー歴)
M:Medication(内服薬)
P:Past history&Pregnancy(既往歴と妊娠)
L:Last meal(最終の食事)
E:Event(現病歴)
表2 OPQRSTT
O:Onset(発症時間/様式)
P:Palliative/Provocative(誘発因子)
Q:Quality/Quantity of pain(痛みの性質・程度)
R:Region/Radiation(部位/放散)
S:Symptom(随伴症状)
T:Time(時間経過)
T:Treatment(治療)
2 致命的な二次性頭痛でないかを明らかにする
●SNOOP(表3)1に沿ってアセスメントしながら、表42に該当する頭痛でないかを確認します。
●特に、「突然」「最悪」「増悪傾向」の3つのサインは見逃せません。1 つでもあれば精査しましょう。
●SNOOPにひっかかる症例では、緊急度、重症度が高い可能性があります。
表3 SNOOP
S:Systemic symptoms/全身症状(発熱、倦怠感、体重減少など)
S:Systemic disease/全身性疾患(悪性腫瘍、AIDSなど)
N:Neurological/神経欠落症状
O:Onset abrupt/突然の発症、雷鳴頭痛、急速に悪化
O:Older/40歳以上の新規発症(5歳未満と50歳以上とするものもある)
P:Pattern change/以前と異なる頭痛(頻度、持続時間、性状、重症度)
(文献1より引用、一部改変)
表4 致命的な二次性頭痛を疑うポイント
1:突然発症、短時間で症状が完成した頭痛
2:今までの人生で最悪の頭痛
3:いつもとは違う頭痛
4:程度と頻度が増悪傾向の頭痛
5:発熱や髄膜刺激徴候(項部硬直、ジョルトアクセンチュエイション、ネックフレクションテスト)
6:50歳以降に初めて発症した頭痛
7:神経症状(麻痺など)を伴う頭痛
8:精神症状を伴う頭痛
9:がんや免疫不全を伴う頭痛
(文献2より引用)
3 頭部単純CTなどの画像検査の準備をする
●頭部単純 CT では、くも膜下出血や脳出血の所見が確認できます。
●しかし、逆にいえば頭部単純 CTでは、冒頭で取り上げた致命的な疾患のうち、くも膜下出血と脳出血しかわかりません。
●また、くも膜下出血は、CTが正常でも完全には否定できません。
●下記1に挙げた項目にも注意を払い、当てはまるものがみられた場合は医師に報告しましょう。
この記事は会員限定記事です。