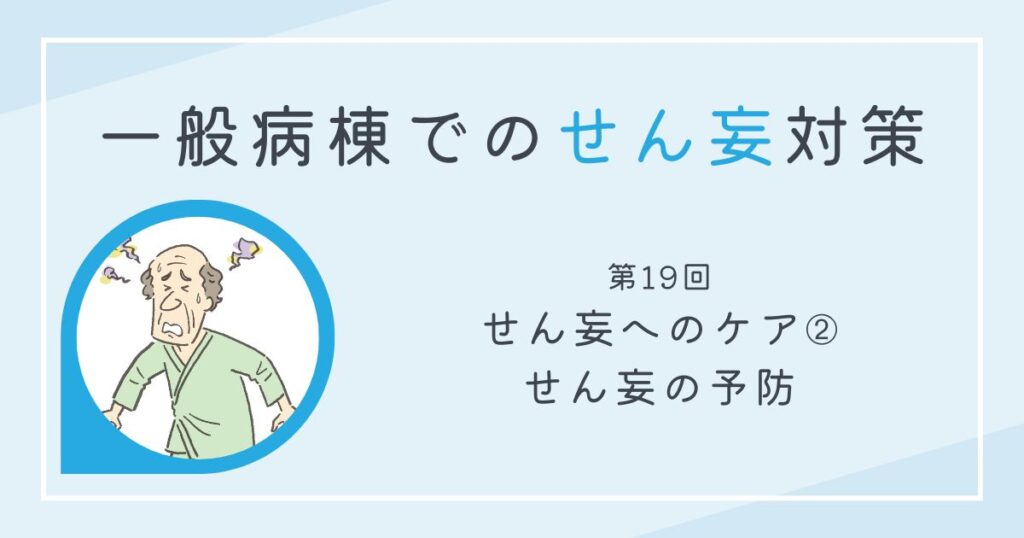せん妄のメカニズムを知れば、効果的な対応・ケアが見えてきます!今回はせん妄の原因となる、睡眠覚醒リズムの障害や、不快感の予防について解説します。
せん妄の原因となる睡眠覚醒リズムの障害や、不快な症状を取り除く
1)睡眠・覚醒リズムの障害の予防
食事、就寝、起床時間のリズムを維持することは、せん妄の予防になります。施設により限界はありますが、就寝を消灯時間にすることにこだわりすぎず、日ごろの就寝時間に近づけるなど柔軟に変更することも効果的です。
また、日中リハビリテーション・離床を促すなど、身体への刺激や室温などの刺激も睡眠覚醒リズムの調整に役立ちます。
なお、朝は明るく、夜は暗くなど刺激のコントロールも睡眠調整ですが、朝日を浴びるなどの光刺激の効果は認知障害においては限定的とされています。
2)疼痛と排泄(便秘・尿閉)の不快感の予防
疼痛や便秘、そして尿閉は、せん妄の発症・悪化に強く影響していますが(図1)、意外に見逃されがちです。せん妄患者はこれらの不調や不快感を言語化して伝えることが困難となっており、適切なケアが受け入れられていないことがしばしばあります。
これらの不快感によるイライラ、暴言、不穏などへの対応として、抗精神病薬が必要以上に投与されていることもあります。
疼痛は、表情やバイタルサインの変化に注意することで早期発見が可能です。疼痛へのオピオイドの投与はせん妄のリスクになりますが、鎮痛など不快感除去でのメリットのほうが大きく、積極的に介入を行うべきです。
便秘や尿閉は、排便・尿量や排尿回数に注意することで早期に発見することが可能です。便秘対策として飲水をこまめに促すことは脱水予防(≒脳血流の維持)にもなるため、せん妄予防として広く行われています。
図1 疼痛・便秘・尿閉とせん妄の関連
この記事は会員限定記事です。