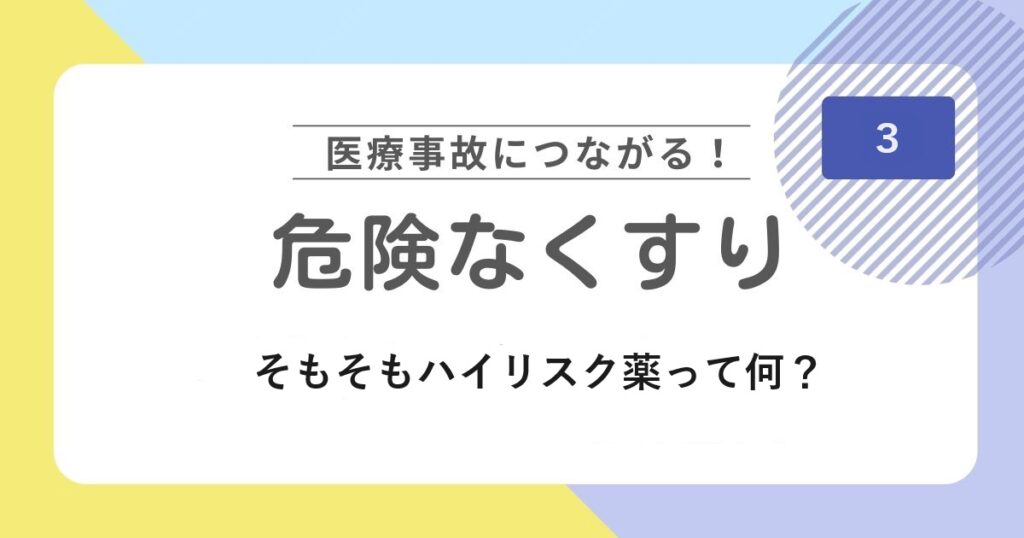医療事故につながる可能性のある危険な薬に注意!今回は、ハイリスク薬の定義や危険な理由、注意点、使用時のポイントを解説。抗リウマチ薬 メトトレキサート、蛋白分解酵素阻害薬 ガベキサートメシル酸塩を取り上げています。
ハイリスク薬を取り扱うために大切なことは?
皆さんは「ハイリスク薬」の定義について考えてみたことがありますか?
ハイリスク(high risk)という言葉から、危険性の高い薬ということはイメージできると思います。ただ、なかには「特に安全管理が必要な医薬品」や「ハイアラート薬」と呼ばれているものもありますが、これらも「ハイリスク薬」と同じ意味で使われています。では、何がどう危険なのでしょうか。
「ハイリスク薬」を取り扱ううえで大切なことは、その特徴と注意点を知っておくことです。
すなわち、“何が危険なのか”“危険を回避するにはどうすればよいのか”を知らない限り、適切な安全対策をとることはできません。ただ闇雲に危険な薬という認識だけでは不十分なのです。“何がどう危険なのか”“投与の際に何に気をつければよいか”を考えることが重要です。
ハイリスク薬の定義とは?
一般的に「ハイリスク薬」は、「医療従事者にとって使い方を誤ると患者さんに被害をもたらす薬」の総称となっていますが、一般社団法人 日本病院薬剤師会の『ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)』1によると、『ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があるので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書(以下、業務手順書)」に定めるものである』と定義されています。
わかりやすく言い換えると、ハイリスク薬は各医療機関において定めてよい、ということになります。
ハイリスク薬には多くの薬剤が当てはまる
「これがハイリスク薬の定義?」と疑問に感じるでしょう。しかしながら、現在のところ、ハイリスク薬の定義として明確な記述はここに示すものしかありません。ただ、ハイリスク薬を自由に定めてよいとは言っていません。「業務手順書作成には以下の項目を参考にしていただきたい」1と書かれています。項目を次に示します。
ハイリスク薬というと、KCLに代表される高濃度カリウム製剤や、インスリンを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、次に該当する薬剤すべてがハイリスク薬であり、項目ごとに数品目の薬剤が存在するため、非常に多くの薬剤が「ハイリスク薬」ということになるわけです。
そのため、「ハイリスク薬」とひとくくりに考えるのではなく、“どのような危険性があるのか” “それを回避するために注意すべき点は何か”を常に意識し、行動することを心がけてください。
業務手順書作成の際に参考にする項目1
A 厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおいて、「ハイリスク薬」とされているもの。
①投与量等に注意が必要な医薬品
②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
⑥心停止等に注意が必要な医薬品
⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤
B 平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬
①抗悪性腫瘍剤
②免疫抑制剤
③不整脈用剤
④抗てんかん剤
⑤血液凝固阻止剤
⑥ジギタリス製剤
⑦テオフィリン製剤
⑧カリウム製剤(注射薬に限る)
⑨精神神経用剤
⑩糖尿病用剤
⑪膵臓ホルモン剤
⑫抗HIV薬
C 上記以外で、(一社)日本病院薬剤師会薬剤業務委員会において指定したハイリスク薬
①治療有効域の狭い医薬品
②中毒域と有効域が接近し、投与方法・投与量の管理が難しい医薬品
③体内動態に個人差が大きい医薬品
④生理的要因(肝障害、腎障害、高齢者、小児等)で個人差が大きい医薬品
⑤不適切な使用によって患者さんに重大な害をもたらす可能性がある医薬品
⑥医療事故やインシデントが多数報告されている医薬品
⑦その他、適正使用が強く求められる医薬品
ハイリスク薬の注意点
例をみてみましょう。例えば、次の2つの薬は同じハイリスク薬ですが、危険な理由も、注意すべきポイントもまったく違います。
抗リウマチ薬 メトトレキサート(リウマトレックス®)3
危険な理由
●過剰な免疫抑制作用により、重篤な副作用、特に骨髄抑制の発生率等が有意に上昇。なかには、致命的な経過をたどった症例も報告されている。
注意するポイント
この記事は会員限定記事です。