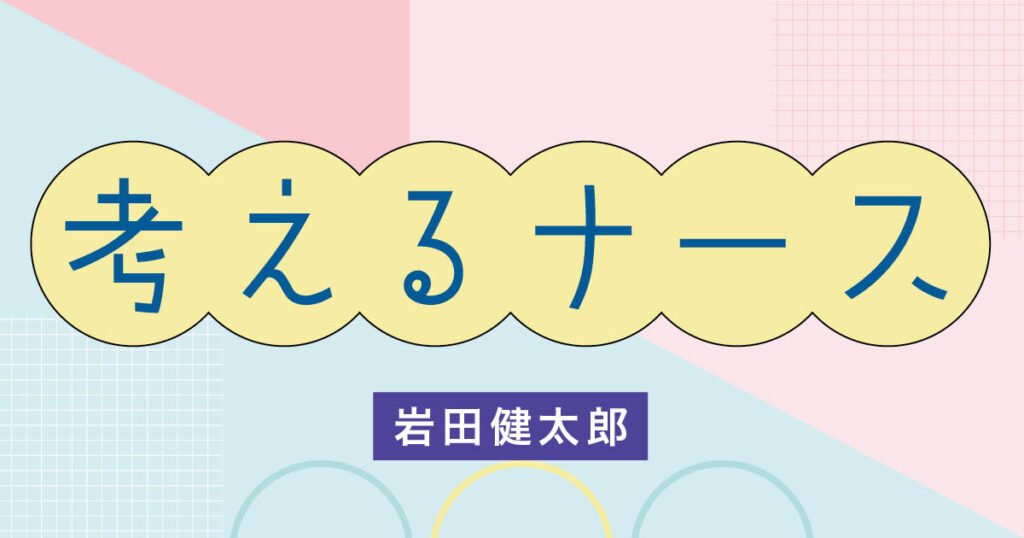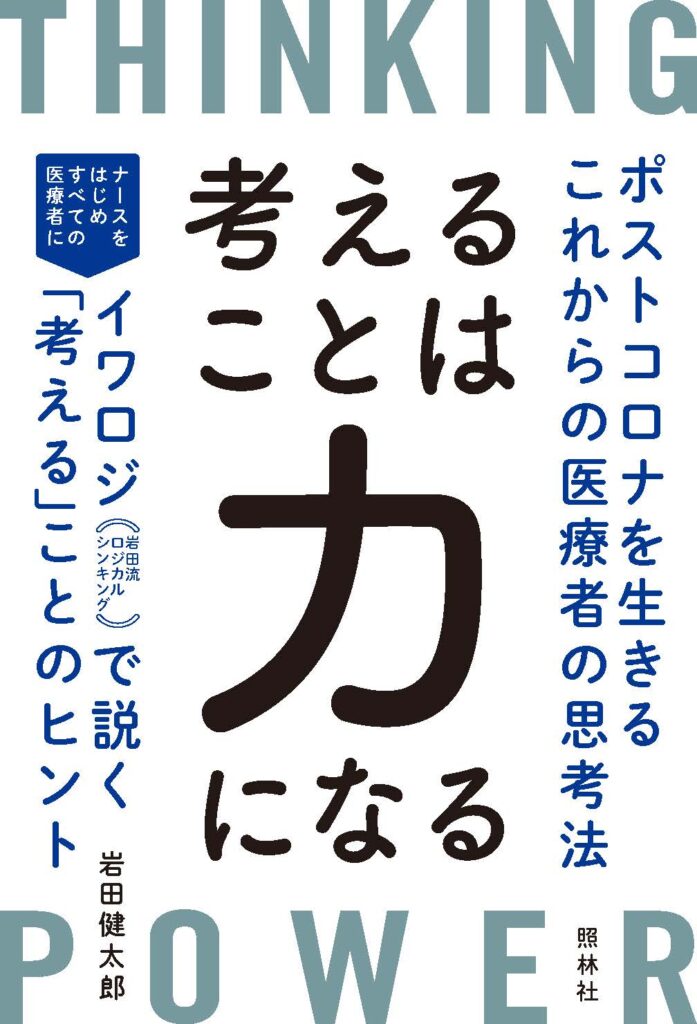岩田健太郎先生が「イワロジ(岩田流ロジカルシンキング)」で説く、「考える」ことのヒントとは。前回に引き続き、ロジカルな思考ができない理由を探っていきます。
質問がうまくできないのはナースだけではない
さて、ここまでお読みいただいた皆さんのなかには、「あれ?」と気づいた方もいるんじゃないでしょうか。それってナースの世界だけの話ちゃうやん。医者だって質問苦手だし、行動主義的、形式主義的でしょ。ついでに権威主義的でしょ。
おっしゃるとおり~。
そうなんです。これって看護の世界特有の問題ではなく、医療界全体にはびこる普遍的な問題なんですね。もっというと、日本全体にはびこる病理といえるかもしれません。「上手に質問を重ねる」訓練を受けていないのは、なにもナースだけでなく、ほとんどの日本人共通の問題ですから、この「上手に質問を重ねられない」問題は、ひいては日本の学校教育の根本問題ともいえましょう。だいたい文科省の官僚たちからして、「答えを出すのがやたら上手で、質問するのが苦手」な代表選手みたいなものですからね。
官僚同様、医者も頭の回転が速くて、偏差値が高いだけに「答えを出す能力」は秀でています。逆にそれが足かせになって、質問をするのはむしろ人より下手だったりします。プライドの高い医者は多いですが、そのプライドが邪魔してさらに質問はできなくなります。質問するとは「私はわかりません」というカミングアウト、白旗をあげることを意味しますから。
知性とは知識の総量ではなく、わからないことがわかること
しかし、「私はわかりません」とカミングアウトするのは無知の表明ではありません。逆です。わからないことがわかる、というのは知性の証明なんです。これを昔の哲学者ソクラテスは「無知の知」と呼びました。
知性とは知識の総量のことではありません。自分が知っていることと、知らないことの境界線がちゃんと引けることをいいます。自分の知っていることの外側には、自分の知らない世界が広がっていることを認識できることをいいます。
そして、「自分の知らない知識」はどんどん増える一方です。
昭和30年代、1950年代には、医学知識が倍になるには50年かかっていたのだそうです。2020年には、これがなんとたったの73日に縮まるんですって(Densen P, 2011)。2か月ちょっとで情報量が倍になってしまうのです。いくらがんばって勉強しても経験を積んでも、知らないことが増えるスピードのほうが圧倒的に速いんです。21世紀はぼくらが知っていることよりも、知らないことのほうがずっと多い時代なのです。
けれども、悲観することはありません。昔と違って今はインターネットがありますから、わからないことがあれば調べればいいんです。すぐに答えは見つけられます。昔よりはずっと手軽に。しかし、そのネット検索をさせるためには「わからないという自覚」が必要です。自分がわかっていないことがわかっていなければ、能動的な情報検索は発動されないのです。
タコツボの中で自分の専門領域の知識の量を誇っている医者は多いです。自分のわかっていないところが自覚できていない医者たちです。このような「わかっていないことがわかっていない」人を、われわれは「井の中の蛙」と呼びます。いくら頭の回転が速くて、記憶容量が大きくて、たくさん知識があっても、自分の知らないことに自覚的でない医者は単に「やたらでかい井戸に住んでいるカエル」にすぎません。そういう医者ってとても多いんです。ほんとやんなっちゃうな……って、皆さんに愚痴っても仕方ありませんが。
というわけで、医者も自分の「無知の知」に無自覚な人がほとんどで、したがって上手に質問を重ねるのが苦手です。つまり、医者も案外、ロジカルではないんですね。口が達者な人が多いので、そのように勘違いされてることが多いだけなんです(これ、絶対隣の医者に読ませないでくださいね)。
もちろん、医者がロジカルではない、という現実をもって、「ナースだってロジカルじゃなくてもいいやん」という結論にはなりません。「それ」と「これ」とは話が別です。むしろ、医者がロジカルではない(ことが多い)からこそ、ナースは積極的にロジカルに考え、医療現場をよくしていかねばならないんですね。
※この記事は『考えることは力になる』(岩田健太郎著、照林社、2021年)を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。