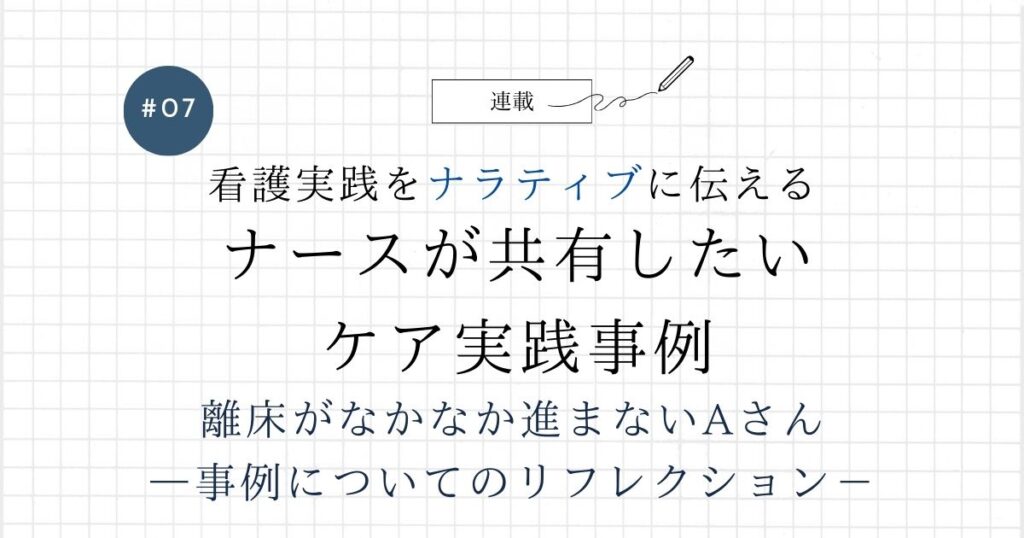事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は離床がなかなか進まなかった患者さんの事例を振り返りながら、別角度から、ナースの“思い”について分析します。
今回の事例:【第5回】離床が進まない患者への看護介入
〈目次〉
患者のプリパレーション(準備性)を判断することの重要性
プリパレーションの範囲は看護チームにも広がる
事例についてのリフレクション
患者のプリパレーション(準備性)を判断することの重要性
本事例において、齋藤さんのケアのポイントは、“人工呼吸器離脱に向けた患者の準備性(preparation)の判断”にあると考えます。この準備性は「身体的側面」と「心理的側面」がありますが、それらは相互に影響しています。
この患者さんの場合、身体的には原疾患の病状も安定し、人工呼吸器の離脱をめざしている段階です。
血液ガスデータとしては人工呼吸器からの離脱は可能だと考えられますが、身体的苦痛やチューブの拘束感のために、咳嗽や呼吸回数の増加で離脱を試みては中断を余儀なくされているという、看護師にとっても閉塞感を感じる状況というところでしょうか。
身体的には離脱は可能なのに、一歩踏み込めないところで、齋藤さんは別の側面から準備性を測定します。
それを齋藤さんは【第6回】のなかで「活力」と表現していますが、髭剃り後のシェーバーの片づけ方や、食後のおしぼりや食膳の整理された様子から、Aさんの周囲への関心や自分らしくものを片づけるという、“生活者としての行動の現れ”を感じ取っています。 そしてその自覚を促すように、患者さんの楽しみや目標としていることを共有することで、Aさんのこころの準備も整えていきます。
プリパレーションの範囲は看護チームにも広がる
この記事は会員限定記事です。