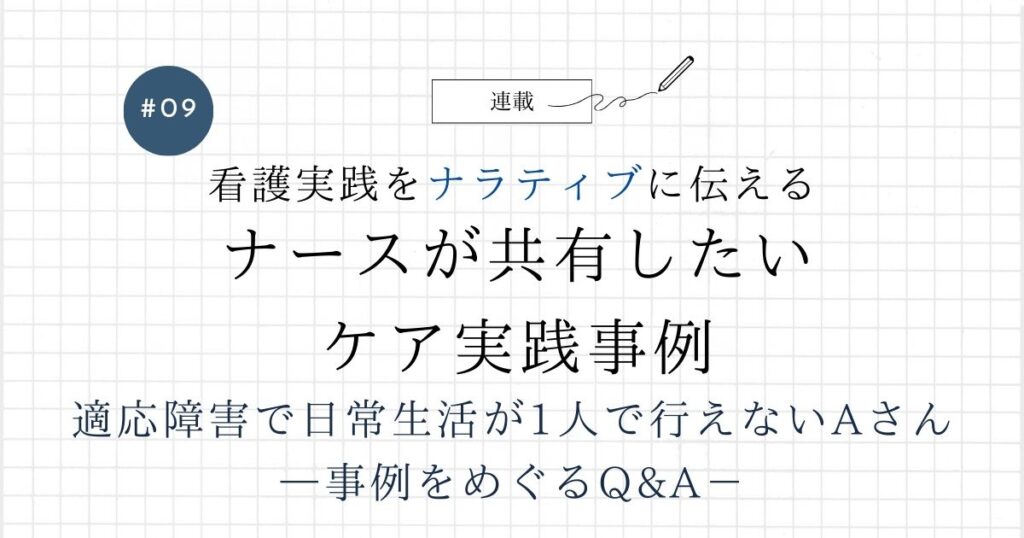事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は適応障害により、日常生活が1人で行えなかった患者さんの事例をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第8回】適応障害でADLが低下した患者への看護介入
〈目次〉
この事例を選んだ理由は?
『ICD-11』における適応障害とは?
病棟看護師とアセスメントに違いが出たのはなぜ?
Aさんのよいところを見つけるための工夫とは?
Aさんの“強み”を重視したケアによる影響は?
事例をめぐるQ&A
この事例を選んだ理由は?
大橋 この事例を、読者の皆さんと共有したいと思った理由をお聞かせください。
矢内 “看護の力”が患者さんに大きな変化をもたらした印象的な事例だったからです。精神科では薬物療法が重要と言われていますが、Aさんにとっては信頼関係を基盤とした看護のかかわりが何よりも効果的でした。
事例を振り返り、読者の皆さんと共有することで、Aさんとのかかわりを看護ケアとして整理できるのではないかと思いました。また、「私たち看護師にはこれだけの力がある!」ということも、読者の皆さんにお伝えしたいと思いました。
『ICD-11』における適応障害とは?
大橋 「適応障害」とはどのようなものですか?
矢内 適応障害(適応反応症)とは、特定の心理社会的ストレス因子、または複数のストレス因子に対する不適応反応のことです。通常はストレス因子発生後1ヶ月以内に現れ、ストレス因子がなくなれば、6ヶ月以内に改善するといわれています。
『ICD-11(国際疾病分類第11版)』では、ストレス因子やその結果に対する過度の心配、ストレスについての反復的で苦痛な思考、ストレス因子の影響についての絶え間ない反芻的思考といった「ストレス因子へのとらわれ」と、ストレス因子に適応できず、個人生活や社会生活、学業仕事などの重要な領域に障害が生じるといった「ストレス適応の失敗」が、診断する上での必須項目となりました。
病棟看護師とアセスメントに違いが出たのはなぜ?
大橋 本当はできるのに生活行動をしないAさんをみて、看護師の皆さんは“依存的で身体愁訴などの訴えが多くて困っている”と話していました。しかし矢内さんは、“慢性的な見捨てられ不安や自己否定感を抱えている”と考えました。Aさんのどのようなことに気づき、注目して、このように捉えたのかを教えてください。
矢内 慢性的な“見捨てられ不安”や“自己否定感”については、情報収集の段階で、家庭環境やいじめなどの生育歴からある程度予測が立ちました。この予測をもとに、肯定的フィードバックを中心にかかわり評価した結果、Aさんの理解につながったと思います。
もう1つは、Aさんに対する病棟看護師の評価と、私が実際にかかわってみて受けたAさんの印象のズレに注目したことです。
病棟看護師の評価は、「訴えが多く依存的である反面、何に対しても拒否的」で、いわゆる“困った患者さん”でした。しかし私が受けた印象は、けっして“何に対しても拒否的”ではなく、“人とのかかわりを求めている患者さん”でした。Aさんの拒否的な言動は、本来の拒否という意味ではなく、本当にかかわってくれる人を求めるための手段であると考えられました。
この記事は会員限定記事です。