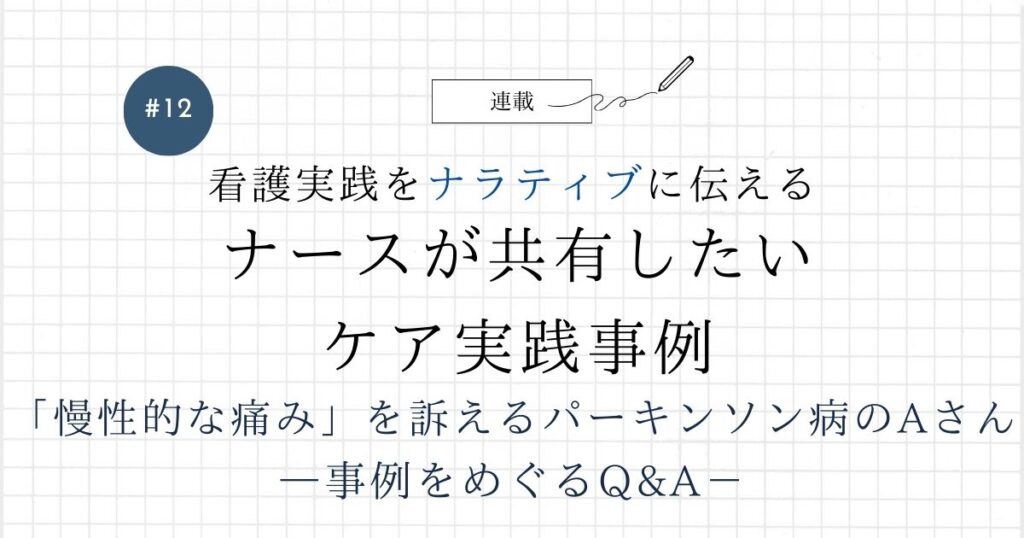事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は慢性的な腰の痛みを訴えるパーキンソン病の患者さんの事例をめぐるQ&Aを紹介します。
今回の事例:【第11回】慢性腰痛を訴えるパーキンソン病患者への看護介入
〈目次〉
この事例を紹介した理由は?
痛みを増強させている要因をどう推測した?
入院前の生活と現状をどう関連づけていった?
Aさんの生活力、セルフケア能力をどう見積もった?
事例をめぐるQ&A
この事例を紹介した理由は?
米田 今回、この事例について紹介しようと思われた理由を教えてください。
佐野 私は回復期リハビリテーション病棟で働いていますが、慢性的な痛みを訴え、なかなか痛みが軽減しない患者さんが多くいます。
“痛み止めなどの治療の効果が不十分で、慢性的な痛みを訴える患者さん”にどのようにかかわったらよいのかは難しい課題だと思いますが、痛みを生じる器質的な原因以外に、心理的な問題など他の要因が痛みを増強させていることも多いと思うのです。
そのような患者さんに対して、例えば心理的な問題にアプローチするなど、看護師が援助することで問題を解決できる場合もあるのではないかと思います。 慢性的な痛みを訴える患者さんに対して看護師ができる援助とは何かを考えていくきっかけになればと思い、この事例を紹介しました。
痛みを増強させている要因をどう推測した?
米田 “痛みの増強“の要因について、「腰椎症そのものから来ている以外にもあるのではないか」と、どのように推測されましたか?このときの思考プロセスを教えてください。
佐野 まず病棟で「生活の様子を観察」して、動作の方法や休息のとり方に問題があると考えたのが1つ目です。
2つ目は「心理的な要因」についてですが、まず医師と、過去と現在の腰部レントゲン写真を比較し、変形性腰椎症は悪化していないことがわかりました。
またAさんは、NSAIDsなど鎮痛薬を使用したのち“最も薬が効いている”と推定される時間帯でも、痛みの訴えに変化がなく、薬剤の量を増やしても痛みの訴えが変わらないなど、痛み止めの効果があまり見られませんでした。
また、他のスタッフからAさんのふだんの動きやリハビリテーションのときの様子について情報を収集したところ、「何か他のことに気持ちが集中しているときには、痛みの訴えがなく動作ができることがある」という情報が得られました。 このようなことから、心理的な問題が痛みに関係しているのではないかと考えました。
入院前の生活と現状をどう関連づけていった?
米田 「Aさんの状況を捉え直してみることにしました」とあります。私もコンサルテーションで行う手法ですが、佐野さんは、どのような側面から状況を捉え直そうとしたのですか? 特に“パーキンソン病とともに生き抜いてこられた体験を、どのように現在の状況と関連づけていったのか”、興味があります。
この記事は会員限定記事です。