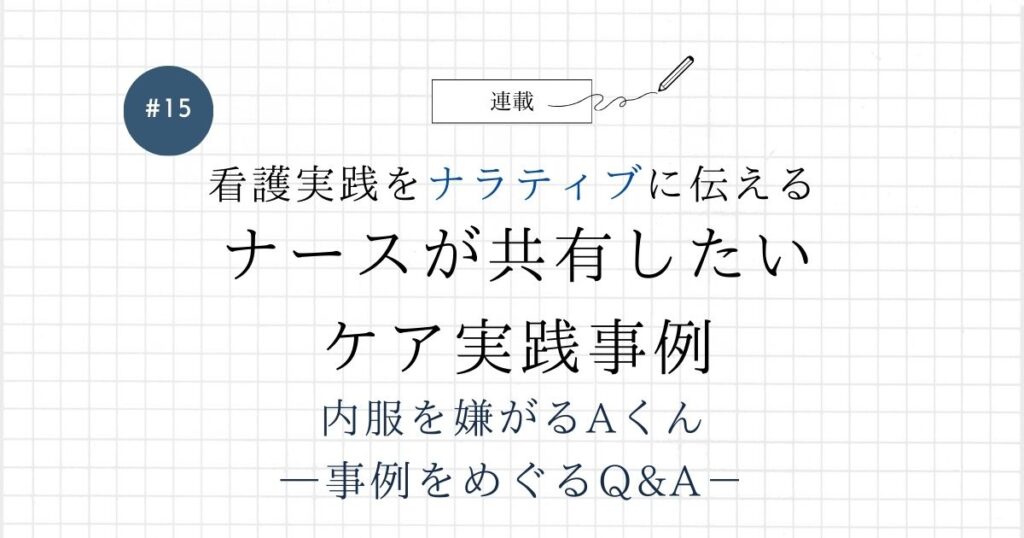事例紹介をもとに、看護介入をナラティブに伝えます。今回は内服を嫌がる6歳の患者さんの事例をめぐるQ&Aを紹介。子ども療養支援士(CCS)についても解説します。
今回の事例:【第14回】小児の服薬拒否への対応は?6歳児への看護介入
〈目次〉
この事例を紹介した理由は?
6歳という年齢への配慮は?
病名と治療予定の説明で注意したことは?
子ども療養支援士(CCS)とは?
精神科医師の助言でわかったことは?
事例をめぐるQ&A
この事例を紹介した理由は?
渡邊 この事例を紹介しようとした理由を教えてください。
杉澤 小児がんの治療過程では、子どもは痛みを伴う処置を何回も受けなければなりません。また、内服も子どもには苦痛です。看護師は子どもに医療処置を行う責任があるため、なかなか内服できない子どもに対して「何とか飲ませなければ」という気持ちを抱くことがあります。
子どもがスムーズに内服できることを目標にするがために、看護師は、子どもの体験を子どもの視点で理解することが難しくなってしまうこともあると思います。 今回の事例では、“内服できない”という目の前の課題だけを解決しようとするのではなく、子どもの体験や入院生活の全体をとらえ、“育つ力”を支援していくことの大切さに気づかされた事例だったため、紹介しました。
6歳という年齢への配慮は?
渡邊 6歳児というAくんの年齢に配慮したことはありますか?
杉澤 Aくんは治療のために、1年生の初めの半年は、本来通学するはずの小学校に通学することができません。
入院治療が終了して小学校に通学するようになること(復学)を前提に、基本的な生活習慣を身につけることや、院内学級で他児や先生とかかわりながら社会性を育むことが重要であると考えました。 “病気で入院していなければAくんがどのような生活を送るはずだったか”に目を向け、退院後を見据えて“生活の整え”に取り組むことが重要な支援だと考えました。
病名と治療予定の説明で注意したことは?
渡邊 Aくんへの「病名」と「治療予定」を説明するときに配慮したことは何ですか? Aくんに伝えたかったことは何だったのでしょう。
杉澤 診断時のAくんへの説明において、“病名を本人に伝えている”という点では、医療者は嘘をついていません。しかし、“バイキンが体の中に入っている”という説明は明らかに事実ではありません。
この記事は会員限定記事です。