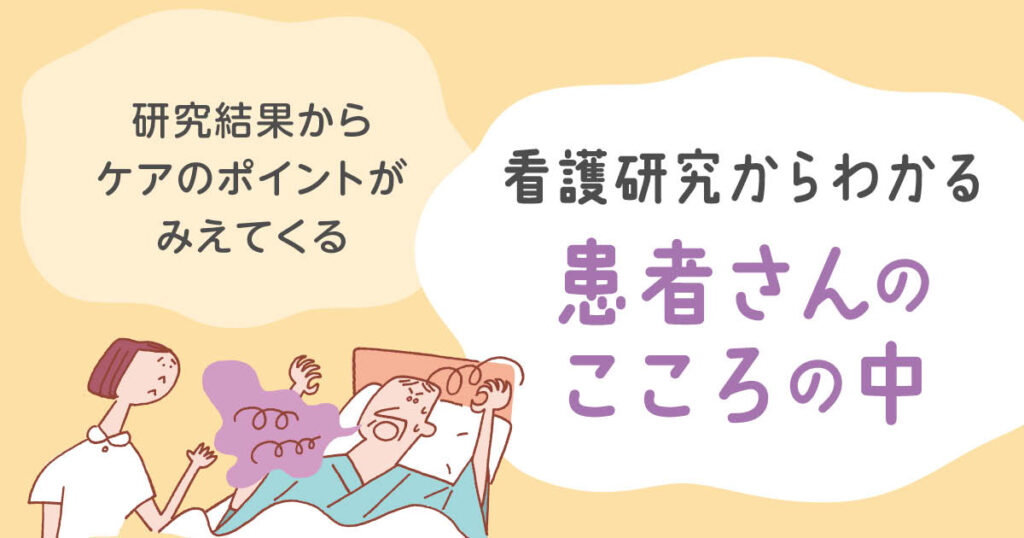未破裂脳動脈瘤により血管内手術を受けた患者さんの心理についての研究結果をもとに、看護師が実践したいケアを紹介します。心情や体験を理解したうえで、患者さんのもつ“不確かさ”を減らしていく支援とは?
前回の記事:脳動脈瘤で“無症状のまま手術”をした患者の不安と対処行動【看護研究#9】
患者さんのもつ“不確かさ”を受け止めて、振り返りを促す
●予防的治療は今後発症しないための治療であるという特殊性から、患者さんの心情や体験を十分に理解した看護支援を行う
●患者さんがもつ“不確かさ”を減らしていくようにかかわる
●疾患の正しい理解を促し、自身に合った予防行動を経て、振り返りができるようにする
研究結果から、未破裂脳動脈瘤患者さんは継続的に“不確かさ”を抱えていることが明らかになりました。そのような患者さんを支えるために、「未破裂脳動脈瘤により血管内手術を選択した患者を支える看護指針」1(下記参照)を作成しました。
未破裂脳動脈瘤により血管内手術を選択した患者を支える看護指針
◆診断
1)期待するアウトカム
“不確かさ”の軽減
2)各経過ごとの看護方針
未破裂脳動脈瘤とその治療に関する正しい理解と混乱の予防
【教育的支援】
●患者の熟知度の把握と情報処理能力の査定
●混乱の程度の見きわめ
●情報提供と情報の整理
【支援体制の整備】
●脳ドックにおけるインフォームドコンセントの整備と医療機関の連携
●患者や家族が相談できるシステムの構築とアクセス方法の整備
◆治療選択~手術
1)期待するアウトカム
“不確かさ”の軽減
2)各経過ごとの看護方針
患者の特性に基づいた破裂予防行動の促進と生活制限予防
【“不確かさ”の受け止めのパターンごとの強化ポイント】
●脅威*1と捉えた場合:認知的再評価の促し
●好機*1と捉えた場合:緩衝方略の支持、誤解の是正
【教育的支援】
●用いている対処の内容の吟味と効果の検討
●後天的危険因子への対処方法の指導(グラフや手帳などのツールの活用)
●あいまいな身体症状のアセスメントと緩和方法の指導
【支援体制の整備】
●緊急時の判断や自己解決困難時の相談外来やtelenursing(テレナーシング)*2の検討
*1【「脅威」と「好機」】=Mishelの病気の不確かさ尺度2における成り行きの予想。“不確かさ”が「脅威」と評価された場合は、“不確かさ”を減らすため用心や情報収集、ネガティブな感情の調整が行われる。「好機」と評価された場合は、不確かさを持続させようとする。
*2【telenursing】=テレビ電話などの遠隔コミュニケーション技術を用いた看護ケア。
この記事は会員限定記事です。