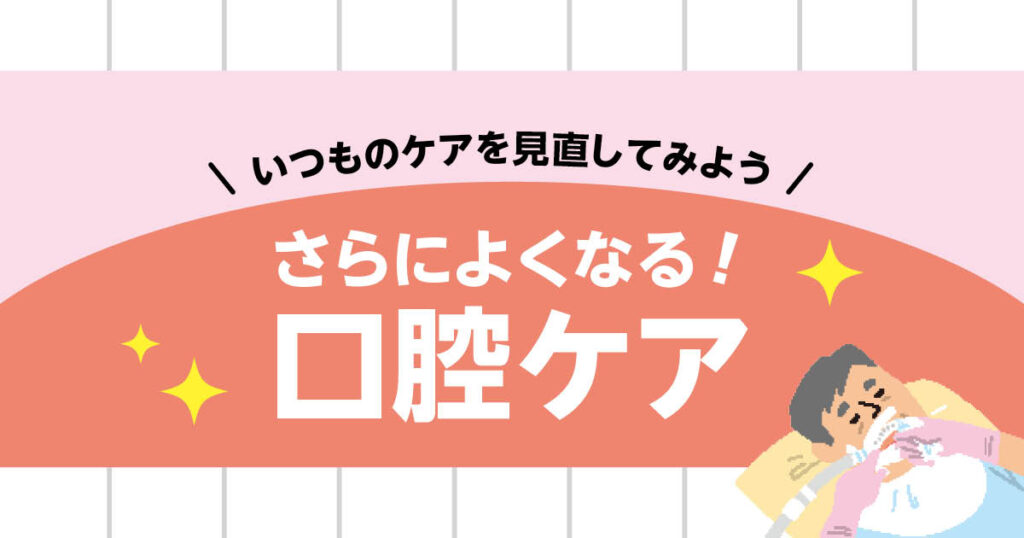口腔ケアはどのような頻度、時間帯で行うと効果的なのでしょうか。ケアを進めるうえで考えておきたい、口腔ケアのスケジュールについて解説します。
●スタッフの多い時間帯に、重点的に1~2回ブラッシング
●乾燥対策などの口腔粘膜ケアを2~6時間毎
夕食後・就寝前の口腔ケアが望ましい
口腔ケアの間隔(頻度)は、各学会のガイドラインにおいても明確に基準は示されていませんが、原則的に経口摂取している患者では、毎食後と就寝前に行うことが望ましいとされています1。
口腔内の細菌は、食後に口腔内に残渣した食物を栄養分として増殖するため、食後数時間で最も細菌が増殖します。また、就寝中は唾液や嚥下回数、口の動きの減少により、唾液による口腔内自浄作用が低下するため、覚醒時よりも細菌は増え続け、起床時に最も細菌が増加する傾向にあります2。したがって、毎食後の口腔ケアのなかでも、特に夕食後、就寝前の口腔ケアが重要とされます1。
ケア回数を増やしても菌数は恒常的に減少しない
一方、絶食中の患者、口腔乾燥が強い患者、汚染状況がひどい患者などの要介護者に対しては、ケア回数を検討し、また粘膜ケアをプラスし対応していく必要があります。
口腔ケアの回数による報告では、口腔内の細菌数は、口腔ケア後4~5時間でケア前の細菌数まで戻るため、1日4時間毎の口腔ケアが必要3という報告があります。しかし多忙な看護業務のなか4時間毎に口腔ケアを行っていくことは現実的でありません。
一方で、非経口摂取患者に対しての口腔ケア回数に関する報告では、1日1~6回口腔ケアを行い、1日当たりの口腔ケア回数とケア後の細菌数を比較検討した場合に有意差はなかった4、あるいは6時間毎にブラッシングした場合と1日1回のブラッシング+6時間毎の綿棒清拭を行った場合、細菌数の増加に両者で有意差はなかったと報告されているものもあります5。
これは、1日当たりの口腔ケア回数を増やしても、 必ずしも恒常的な細菌数の減少にはつながらないことが示唆されています(ただし、意識レベルが低い人、齲歯〈うし/むし歯〉、舌苔、口臭が強い人では、口腔内細菌数が増加する傾向があることが明らかになっています)。
したがって、口腔ケアの頻度を考えるときには、回数に着目するのではなく、患者の口腔内の機能的状況をアセスメントし、個別的に回数を決定していく必要があると考えられます。
理想的な時間帯よりも「できる」時間帯に重点的なブラッシングを
この記事は会員限定記事です。