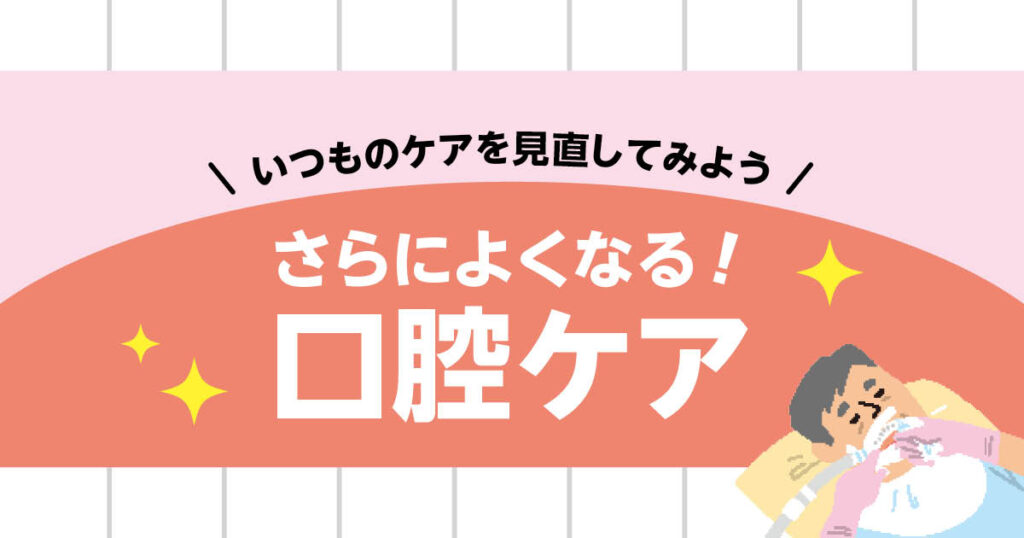口腔ケアを効果的に進めるためには、歯科医師、 歯科衛生士、 言語聴覚士など他職種と連携えをとり、チーム医療として取り組むことが大切。緊急性をアセスメントする、評価・改善を繰り返すなど、ポイントをお伝えします。
*
口腔ケアは、時間的制約、知識・技術不足、患者の非協力的態度、あるいは他人の口を清掃するという心理的障壁などにより、適切に行われていないことが多くあります。また、患者の口が汚いのは看護の恥だと思ってしまい、自分たちだけで何とかしようと他職種の介入を拒むこともよく耳にします。
口腔ケアの考え方として、近年では、口腔ケアはケアだけにととまらず、キュア(治療)という意味も含むと認識されつつあります。したがって、口腔ケアは病棟の看護師だけで行うものではなく、 歯科医師、 歯科衛生士、 言語聴覚士ほかと連携をとり、チーム医療としてかかわっていくものと考え方を変えていく必要があるかと思います。
●緊急性をアセスメントして、他職種を頼る
●看護チーム内での評価・改善を繰り返す
他職種との連携:「必要度×難易度×緊急性」で考え、難しければヘルプを
看護師は毎日、口腔ケアを行うものの、患者の疾患や、口腔内環境に影響を及ぼす因子を考慮したアセスメント、実践している口腔ケア方法の評価が不十分になることがあります。
口腔ケアを進めていくときには、そのときどきの患者の状態に合わせて口腔ケアを行っていく必要があります。具体的には、「①口腔ケアの必要度」「②難易度」「③緊急性」を常に念頭に置き、難しい場合は主治医・歯科医師ほかと連携を考えることが重要です。
①口腔ケアの必要度
意識障害などにより自力で口腔ケアを行えない患者はもちろんのこと、口腔ケアが十分にできない認知症患者や、歯科的ハイリスク患者(唾液分泌量低下、易感染性、出血傾向など)では、ケアの必
要度は増します。
ここで大切なことは、ケアが必要な人を見落とさない視点です。
②口腔ケアの難易度
口腔ケアの難易度は、「患者の協力度」「ケア実施に関連した安全性」「口腔の状態」の3要素からなります1。
●患者の協力度
意識障害や認知症などのためコミュニケーションが十分にとれず、ケアそのものの介入が難しいこと
があります。このような症例の場合、どのようにケアを行っていくのかを考える必要があります。
●ケア実施に関連した安全性
患者の協力度が良好でも、全身状態が不良あるいは不安定なときはケアが難しくなります。このような場合は、患者の全身状態(バイタルサイン、血液データ、出血傾向、易感染状態など)を考慮したうえでケアを進めていきます。
●口腔の状態
開口制限、出血傾向、乾燥状態などを把握し、アセスメントへとつなげていきます。
③口腔ケアの緊急性
この記事は会員限定記事です。