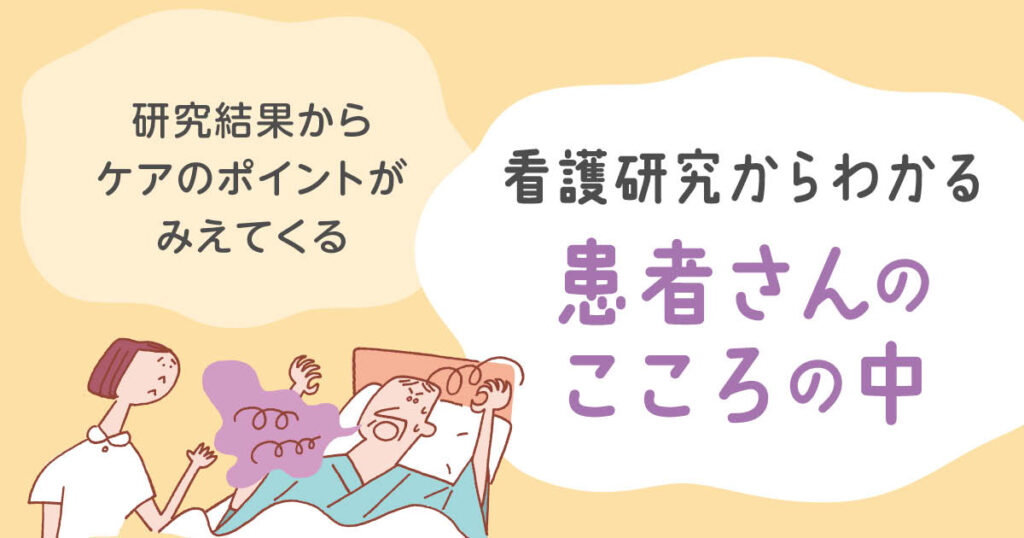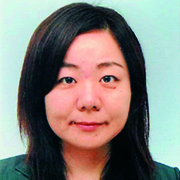パーキンソン病患者さんが、もつ自分の身体イメージは、症状の程度や調子によって揺れ動くことを前回の記事で紹介しました。研究結果をもとに、看護師が実践したいケアを紹介します。
前回の記事:パーキンソン病患者の自己身体像の変化とは?【看護研究#19】
症状や調子でイメージが揺れ動くことを理解し、患者さんを尊重したケアを行う
●周囲の人や看護師自身が患者さんに与える影響に配慮する
●自身の身体像を安定させるために患者さんがとっている行動を尊重する
●日常的な場面から患者さんの苦悩を知り、支える
変化する身体像を抱えながら生きていることに目を向ける
パーキンソン病の患者さんは疾患そのものの影響による動作緩慢に加え、治療薬の副作用症状であるon-off(オンオフ)現象*1やwearing-off(ウェアリングオフ)現象*2、不随意運動などが見られます。
on-off現象は1日のなかで何度も見られ、「調子がよく思い通りに身体が動くと、このまま完治するのではないかと思うときもある」と話される患者さんもいました。
このように、自分の身体への期待をもちながらも完治しない現実を、“1日に何度も”“調子が悪くなるたびに”自分の身体を通して実感させられることは、患者さんにとってはとても苦しいことだと思います。 このような体験を繰り返しながらこれまで生きてきていることに、看護師は目を向ける必要があるのではないでしょうか。
*1【on-off現象】服薬時間とは関係なく症状がよくなったり悪くなったりする現象。
*2【wearing-off現象】薬効時間が短くなる現象。
1)他者の存在に振り回されることに配慮する
パーキンソン病の患者さんは、他者、つまり、家族や友人、近所の人、病院であれば同室者や廊下ですれ違う患者さん、そして、看護師や医師などの医療従事者の発言や態度に大きく影響を受けていることがわかりました。これは「よくも悪くも」です。
まれな病気であるため、なかなか理解を得られずもどかしい気持ちをもつこともあれば、パーキンソン病の患者さんどうしや理解を示してくれる人の存在で気持ちが楽になることもあります。
看護師には、パーキンソン病患者さんがどのような人と接することが有効であるのかを考え、その橋渡しをしたり、相談にのるといった調整役としての役割が必要です。
また、看護師がなんとなく発した言葉に患者さんは敏感に反応します。
例えば、患者さん自身は調子がよいと感じているのに、「調子が悪いですか? 大丈夫ですか?」と看護師に言われると、「何だか調子が悪くなってくるような感じがする」と話された方もいました。
専門職としての意見であると患者さんが認識していることを念頭に置いて、かかわっていくことが大切です。
この記事は会員限定記事です。